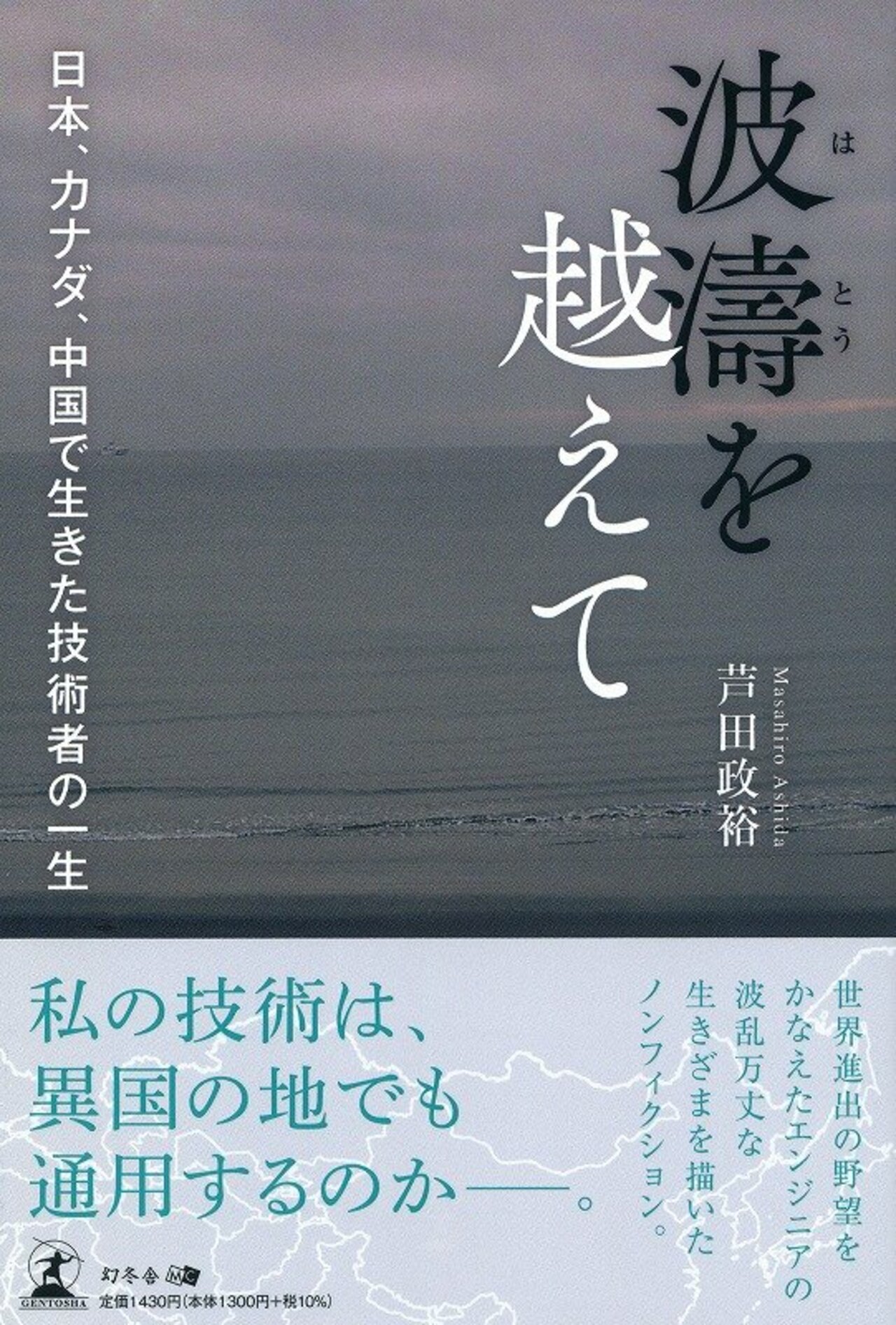神経痛を患っている祖父と元気そうだったが腰の曲がった祖母、祖父は八十歳、祖母七十六歳。政裕が福岡から着いた時、どんな事情か知らないが借家に住んでいた。
政裕はこの村の国民学校に集落の子供たちと隊列を組んで軍歌を歌いながら登校した。みんな藁草履を履いていた。政裕もどこへ行くにも藁草履を履くようになった。運動靴を履いている子はいなかった。
政裕の言葉は博多弁だったのでいじめられ、祖父の名前を政裕のあだ名につけられた。ここでも独りぼっちだったが泣くことはなくなった。
ある日、上空にB二九爆撃機の編隊が飛行機雲を描きながら悠々と通り過ぎていくのを見た。
銀色の機体が美しく輝いていた。丹波の山奥でも時折空襲警報が発令され村役場のサイレンが村中に響き渡った。
福岡では何度か夜に空襲警報のサイレンを聞いて近くの証券取引所ビルの地下室に避難したことがあった。終戦の年の六月福岡の大空襲でこの地下室に避難した人たちが爆弾の直撃で全滅だった。政裕の兄たちと同居していた親戚の家族たちは焼夷弾の雨の中を海岸の岸壁に逃げて全員無事だった。
もしこの時海岸に逃げるのを躊躇して証券取引所ビルの地下室に避難していたなら兄たちと叔父叔母の家族はどうなっていたか。福岡との手紙のやり取りが絶えていたので政裕はそのような経緯は知らされていなかった。
これらの出来事はあとになって聞いた話だ。政裕は丹波にいたのでそのような生死が決められるような体験をせずに済んだのは幸運だった。
六年生の夏休み中の八月十五日、隣家の素封家の主が近所の家々に触れ回り、その家に集まるよう告げられた。そして正午の時報のあと天皇陛下の玉音放送を聞いた。
政裕には全部を理解できなかったが大人達は涙を流して聞いていた。戦争に負けたのだなと感じた。
放送が終わりみんなはしばらくの間茫然としていたがやがて誰ともなく、恐いことが起こるのではないか、殺されるのではないか、などといい出した。
その数日前、広島と長崎に新型爆弾が落とされたニュースも聞かされていたし、一億玉砕という言葉が頭に浮かんでいた。
その年の十月だったか、小学校に三人のアメリカ兵が乗ったジープが一台乗り入れた。
校長室で校長先生と話していた。先生は英語ができる。こんな山奥の村にも進駐車が来るとは。その後どれくらい経っていたか、近くの佐治川の河原に一人乗りのアメリカの小型戦闘機が不時着した。すぐその手前にあった橋に衝突せず、大破はしたが消防団員が駆けつけパイロットは無事救出された。
その翌日、生徒が講堂に集められそのパイロットが話をして校長先生が通訳した。内容は覚えていないが、敵対の雰囲気は全く感じなかった。そんなことがあってアメリカ人が身近に感じられるようになった。
終戦の日に感じた恐怖はいつの間にか薄れていった。
こんな新しい世情のなかで政裕の丹波の生活が始まった。前からの算段だったのか、政裕が着いた翌年、周りを山に囲まれた十軒ほどの集落の一番奥の敷地に家の新築が始まった。
この敷地には以前祖父母が住んでいた家があり、父も子供のころ養子に取られて住んでいたが、祖父母は何かの事情でこの家を処分して実子の住む朝鮮の京城に渡ったということだった。父の死後、祖父母は丹波に帰って借家に住んでいたのだった。
その屋敷の周辺に三反ほどの広さの畑があり、近くの山二か所に山林を所有していた。なぜ、それらを放置して朝鮮に行ったのか。そのころの祖父母は七十歳台だったはずだが老齢化のせいで百姓ができなくなったためか。