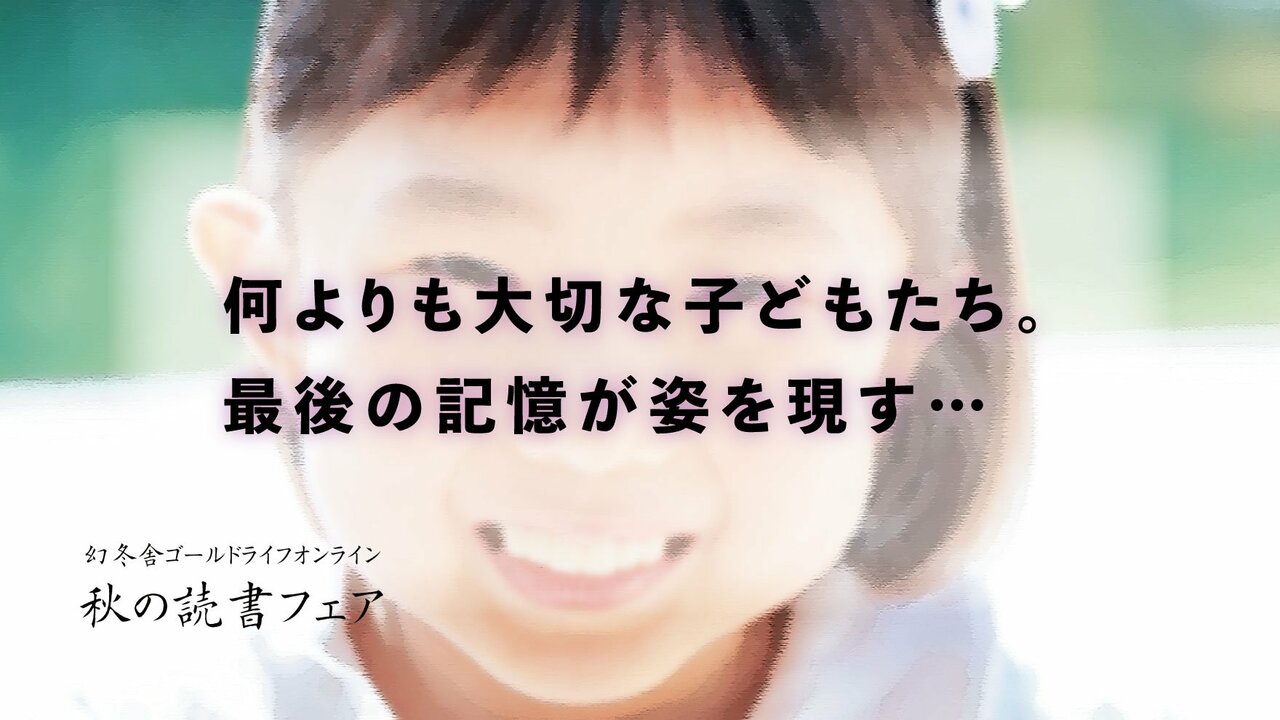別れ
「まさか多恵さんとの結婚は、偽装結婚ではありませんよね」
庄兵衛はどういうわけかひどく狼狽していた。わたしは力強く首を横に振った。今回の欠片は今までと異なり、もどかしくもじれったい。
「たしかに結婚したての当時、わたしは眞理のことを引きずるあまり、多恵と家族になりきれないでいた。だがな、ここはまだ家族の階段をのぼる途中だ」
わたしと多恵は、それから多くの時間を供にし、かけがえのない想い出を経て、真の家族になった。
陽菜や智が生まれたことで、ふたりの絆はより強固になった。
子供たちの存在はやはり大きかった。陽菜や智が、わたしと多恵の架け橋になってくれた。なんだ、わたしには家族がいるじゃないか。なにものにも代えがたい存在が。
「このとき多恵さんが身籠っていたのが、陽菜ちゃんというわけですね」
わたしはこくりと頷いた。家族を想うと、自分のなかに陽だまりが生まれた。その温もりがわたしを強くさせる。陽菜の、智の、多恵の姿を心に思い浮かべる。わたしは決してひとりではない。
「陽菜ちゃんは、どんなお子さんだったのですか」
「陽菜はお転婆だったよ。わたしたち夫婦と母さんに甘やかされて、我が家のアイドルとして長らく君臨していたからな」
それでいて家を出た途端に火が消えたように大人しくなるから、内弁慶だったようにも思う。
まあ、人攫(さら)いも横行していた時代だけに、箱に入れるように育ててしまった弊害かもしれないが。
「なにか、想い出に残っていることはありますか」
「そうだな。陽菜が幼稚園の年中さんの頃だったかな。お絵描きでわたしの似顔絵を書いてくれたことがあったんだ」
記憶に間違いがなければ、あれはたしか、父の日を記念してのことだったように思う。
「その絵がすごく前衛的だったんだ。右手はなくて顔は身体のゆうに五倍はあった。髪はウニのように一本一本が鋭く、顔は黄色だけで塗られていたんだ。けして褒められた絵ではなかった。けれども多恵はそれをまじまじ見るなり『あなたって、こんなに黄色い顔だったのね』って笑うんだ」
なにを言うんだ、似ているじゃないか。ムキになったわたしは、親馬鹿の類いかもしれない。
「そう言われると可笑しくて、陽菜に隠れて多恵と一緒に笑い転げたんだ。それを見つけた陽菜が、これまた自信満々に胸を張るもんだから、あのときは笑い死ぬのを覚悟したよ」
「陽菜ちゃん、真実を知ったら悲しむでしょうね」
そう言いながらも庄兵衛の声は愉快そうだ。