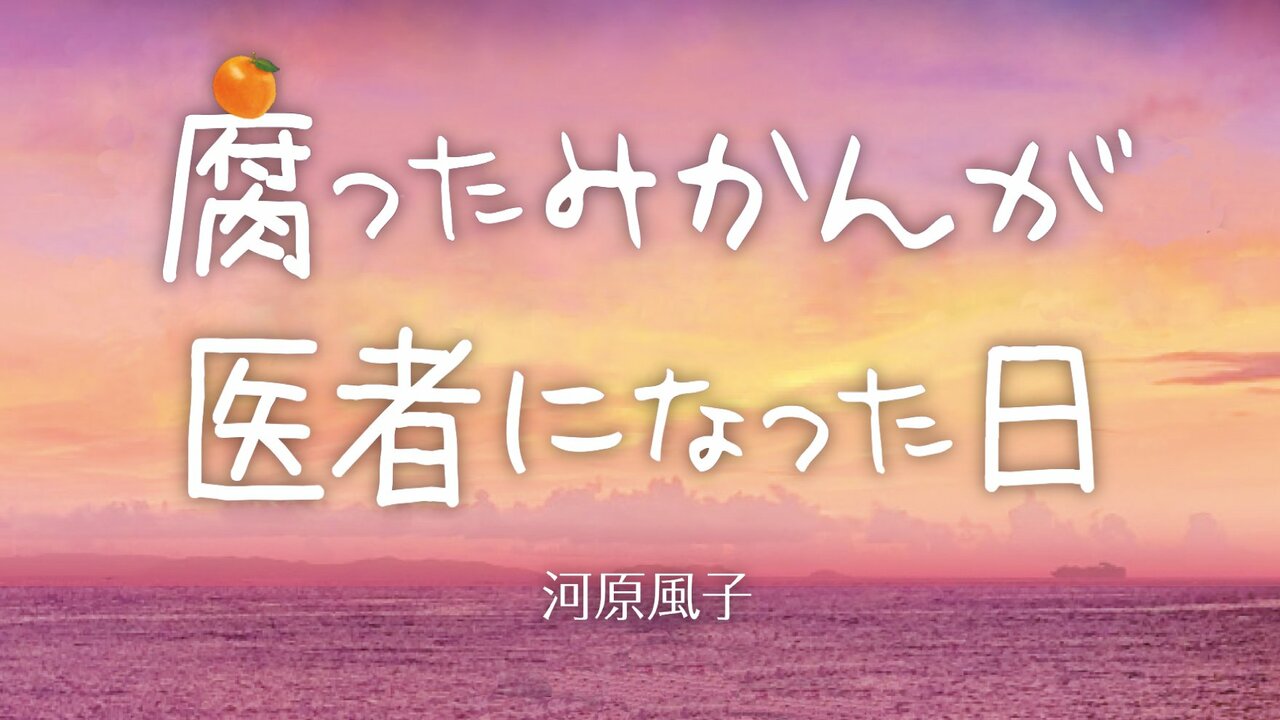野宿
刺激的な中学生活を満喫していたある日、母の乳癌が発覚した。
当然手術をするものだと思い込んでいたが、母はしないと決めているようだった。民間療法で治すというのだ。
私と母は口論になった。
子どもの浅い知識だが、初期の乳癌だし、手術をすれば治るかもしれないのに、と思った。
しかし母は強情である。私の意見はまたも聞き入れられず、私の心はついに温度を失ってしまう。
私は家を飛び出した。あたりは真っ暗。この日から私の深夜徘徊は始まる。
夜は毎晩のようにゆうすけたちと集まり、たわいもない話をし、朝方帰る。夜中家族が寝静まった頃に家を出るのだが、帰った時にカギが閉まっていることがよくあった。そんな日はカギが開く朝まで待たなければならない。
春先でも朝方は寒い。夜中に風が来ない場所を探し回り、やっと見つけたのが、住んでいたマンションの貯水タンクの下にあるスペースだ。高さ70センチメートル、幅1メートル、奥行き3メートルほどで、しゃがんで入ると風がほとんどこない。
雨が降った日は最悪だ。地べたに座れないから、中腰で朝まで過ごすことになる。窮屈だが、誰にも邪魔されない安心感がある場所だった。
数々の野宿の中で忘れられない夜がある。
ある春の日、友達カップルと私の3人で、若松駅近くで遊んでいた。
ポンポン船で帰ろうと思っていたのだが、最終便に乗り遅れてしまう。途方にくれ、屋根しかないポンポン船乗り場で朝を待つことにした。お金もほとんどなく、他にいい手段が思いつかなかった。
最初は楽しく話していたが、だんだん冗談も言えないほど寒くなる。
彼らは2人でくっついて何だか楽しそうだが、私はくっつく相手がいない! 足を組んだり、手をこすったり、自分で自分を温めるのに必死である。
深夜2時くらいになると手足の感覚がなくなってくる。ましてやそこは海沿いであり、海風が寒さに拍車をかけた。
あまりに寒いので、どこか暖かい場所を探そう、と歩いているうちに、小屋を見つけた。バスの待合室なのか、ベンチもある。入口の扉はないが、開いているのは海と反対側なので風よけにはなる。私たちはそこに入り、朝まで過ごした。
その小屋には海が見渡せる窓があり、遠くの明かりや船を見ながら、自分の運命を恨んだ。朝までの時間は途方もなく長い。本当に朝は来るのだろうか、とさえ思う。
何を伝えたいかといえば、こんな状況になっても家に帰りたくないということだ。母に迎えに来てもらおう、なんて全く思わなかったし、それだけは絶対に嫌だった。どんなにつらくても家よりましなのだ。
そんな夜を過ごしながらタバコを吸い始めるようになる。
初めて吸った時、喘息があるせいか、胸が締めつけられるように痛くなった。
でもそれが心地よかった。自分を痛めつけ、その実際の痛みで心の痛みを紛らわせる。
そしてそれを見て傷つく母をみるのが快感であった。
「あなたの子育ては間違っている」そう伝えたかった。