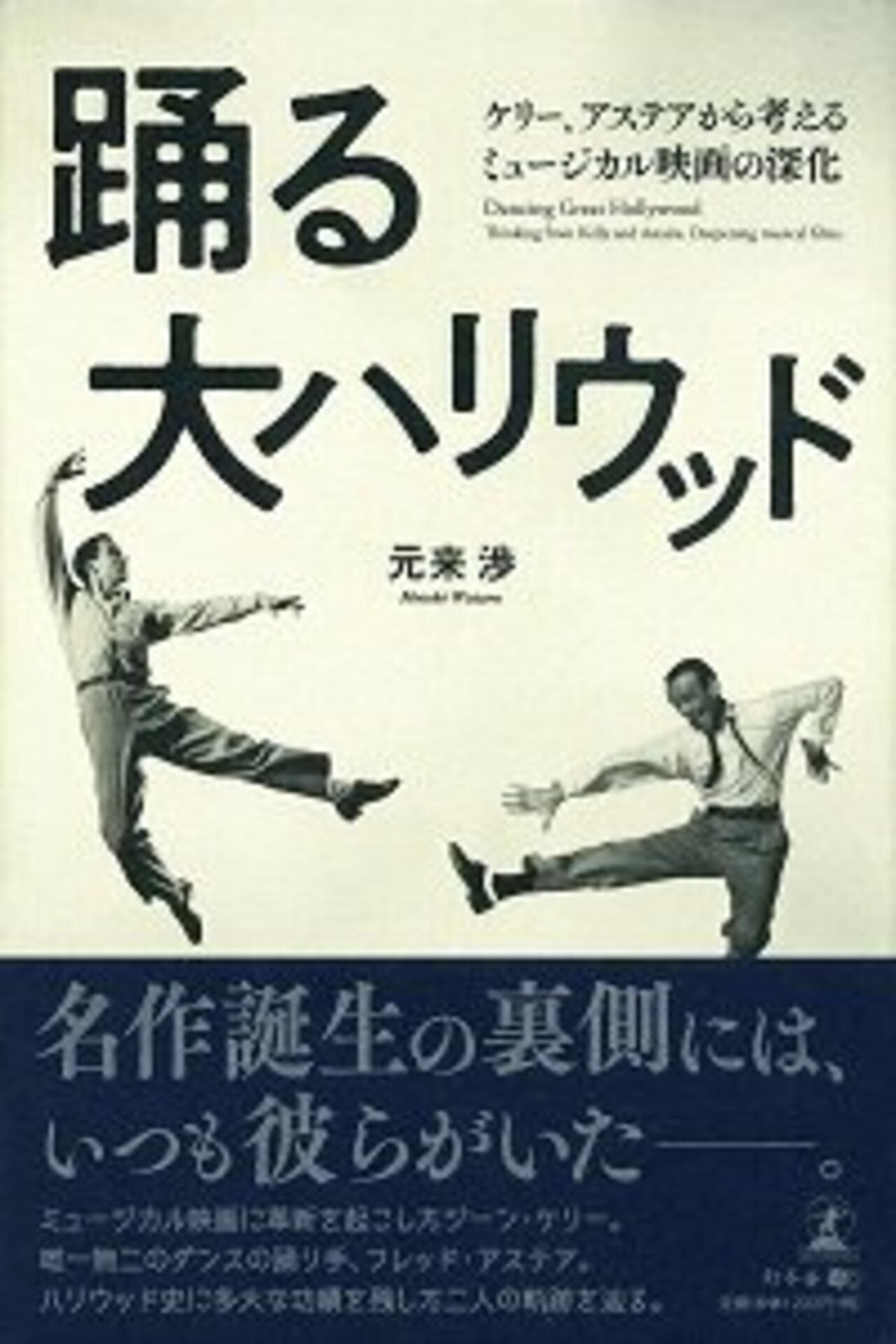「いつも上天気」は「踊る大紐育」に比べシニカルで、単純に楽しめるミュージカルにはならなかった。
反面、テレビへの風刺、人間の裏の感情を描くなど、より新しい時代のミュージカルへの移行をうかがわせる作品でもあった。
批評家には概ね好評だった。しかし、製作の現場はもはや以前とは異なっていた。
予算は削られ、これまでの映画に比べセットも貧弱になった。
ジーンに忠誠を尽くしていたキャロル・ヘイニーはブロードウェイ・ミュージカル「パジャマゲーム」で成功し、すでにチームを離れていた。
共同監督のドーネンはかつてのジーンを師と仰ぐ存在ではなくなっていた。
単独で監督を務め自信をつけたためか、互いの方針は折り合わず、撮影中もジーンとの反目が続いた。
後にドーネンはこの頃のことを次のように語っている。
「当時ケリーとは本当に共同監督はしたくなかったんだ。
……僕らは初めから終わりまで争わなくちゃならなかった。断言できることは、あれは一〇〇%悪夢だったってことだ」
マイケル・キッドは自身のナンバーが公開版から削られたことを侮辱と捉え、後にジーンを激しく批判することになる。
本来調整役になるべきはずのフリードだが、映画プロデューサー協会の会長職で忙しく、不在がちだった。
そしてミュージカルに対するMGMの扱いもこれまでとは違っていた。
ミュージカル映画として丁寧に大衆に浸透させることをせず、ドライヴイン・シアターでは現代版西部劇とでも言うべき「日本人の勲章」(’55)と二本立てにして上映された。
シネマスコープを上映できない映画館も多く、画面の両側や下部がカットされて映写されていた。
一九五五年九月に封切られた「いつも上天気」は、公表されている数字でも経費二〇六万ドルに対し興行収入は二四八万五千ドルにとどまった。
エディ・マニックスの原簿によると、この作品も実際は大幅な赤字だったという。
娯楽メディアとしての映画の凋落やジーンの奮闘を支えるはずのスタジオの衰退は明らかだった。
もはや彼に活躍の余地は残されていなかった。