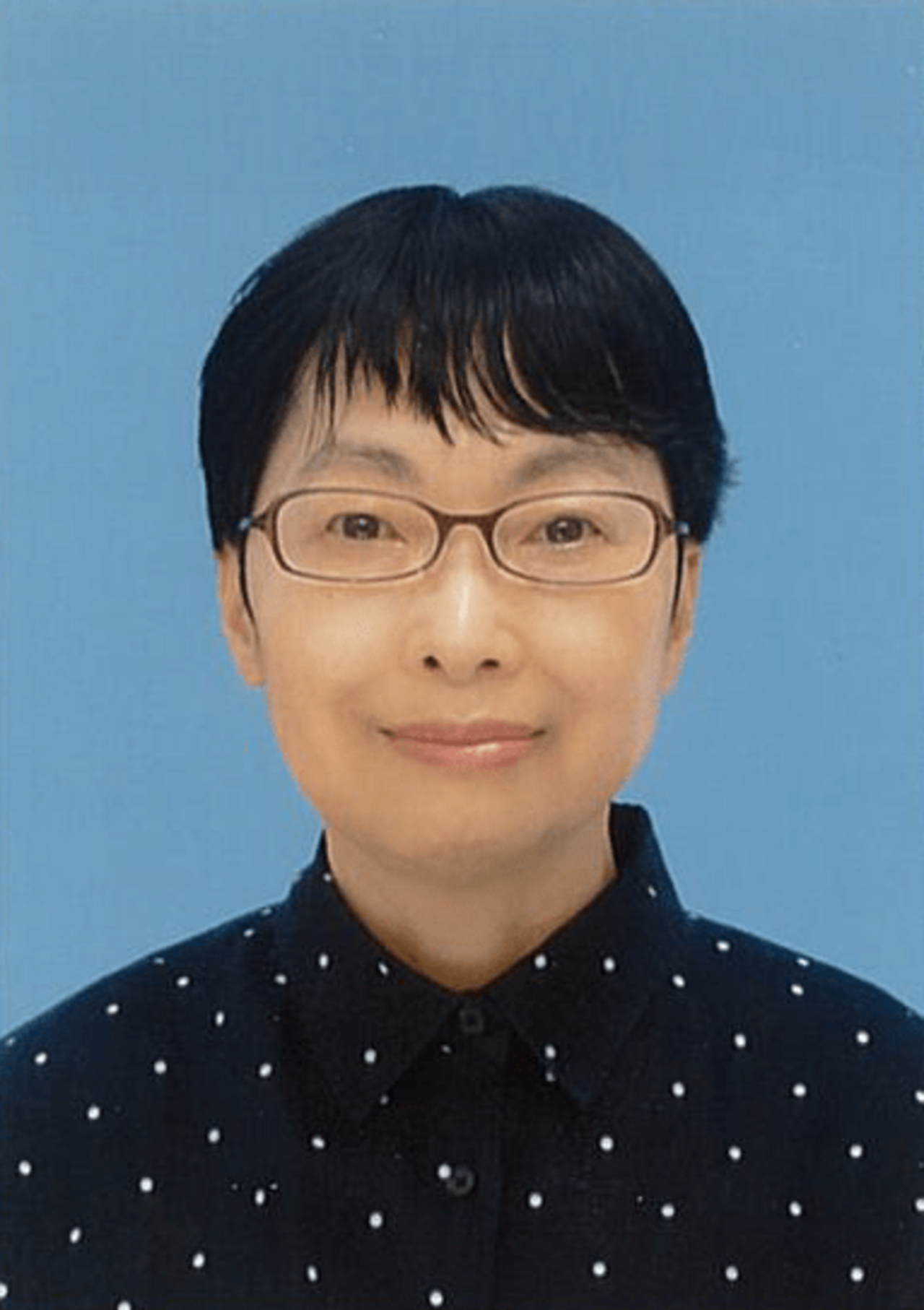キッチンで一緒に
弓子は、その頃、不倫をしていた。
「僕には、守るべき家族がいるから。でも本当に愛しているのは、弓子のことだよ。」及川は言った。
「そういう風に、私の気持ちをもてあそぶようなこと言わないで欲しい。」弓子は涙を流していた。
弓子が及川と出会ったのは、大学三年生の時、大学のキャンパス内であった。弓子は、一限目の授業に遅刻しそうで、キャンパスの廊下を走っていた。その時、反対側から走ってくる男子学生とぶつかって、弓子は、手に持っていた本を廊下に落としてしまった。
「あっ、ゴメンね」と言って、男子学生は、本を拾うと弓子に手渡し、そのまま廊下を走って行ってしまった。
それから数日後、弓子は、学生食堂で、一人で昼食をとっていた。
「このあいだは、ゴメンなさい。」弓子は、食事していた手を止めて前を見た。身長が一八〇センチくらいのスーツを着た男性が立っていた。
「ほら。このあいだ廊下でぶつかってしまって。」その男性が言った。
「ああ、あの時の人? 私こそゴメンなさい。」弓子は、その男性が、先日、廊下でぶつかった男子学生であることに気づいた。
「スーツ着ていてわからなかった? 僕、今、就活中なんだ」
そう言うと、その男子学生は、手に持っていたカバンを椅子の上に置き、弓子の前の椅子に腰掛けた。
「僕は、及川光。商学部の四年生」
「私は、川上弓子です。文学部の三年生です」
弓子と及川は、このようにして知り合った。しばらく雑談をすると、二人は、お互いのメールアドレスを交換し合った。弓子は、身長が一六〇センチのセミロングヘアで、色白のきれいな肌をしていた。及川は、背が高く、手の指が細く長く、男性としては美しい手をしていた。それから二人は、キャンパスの中で待ち合わせの約束をしては、一緒に行動するようになっていった。
八月になったある日、弓子と及川は、大学の近くにあるイタリアンレストランで食事をしていた。及川の就職先が決まり、二人で、そのお祝いの食事会をしていたのである。及川は、大手町にある大手商社に採用が決まり、安心していた。弓子は、及川が一段落している姿を見て、自分の気持ちも落ち着くのを感じた。