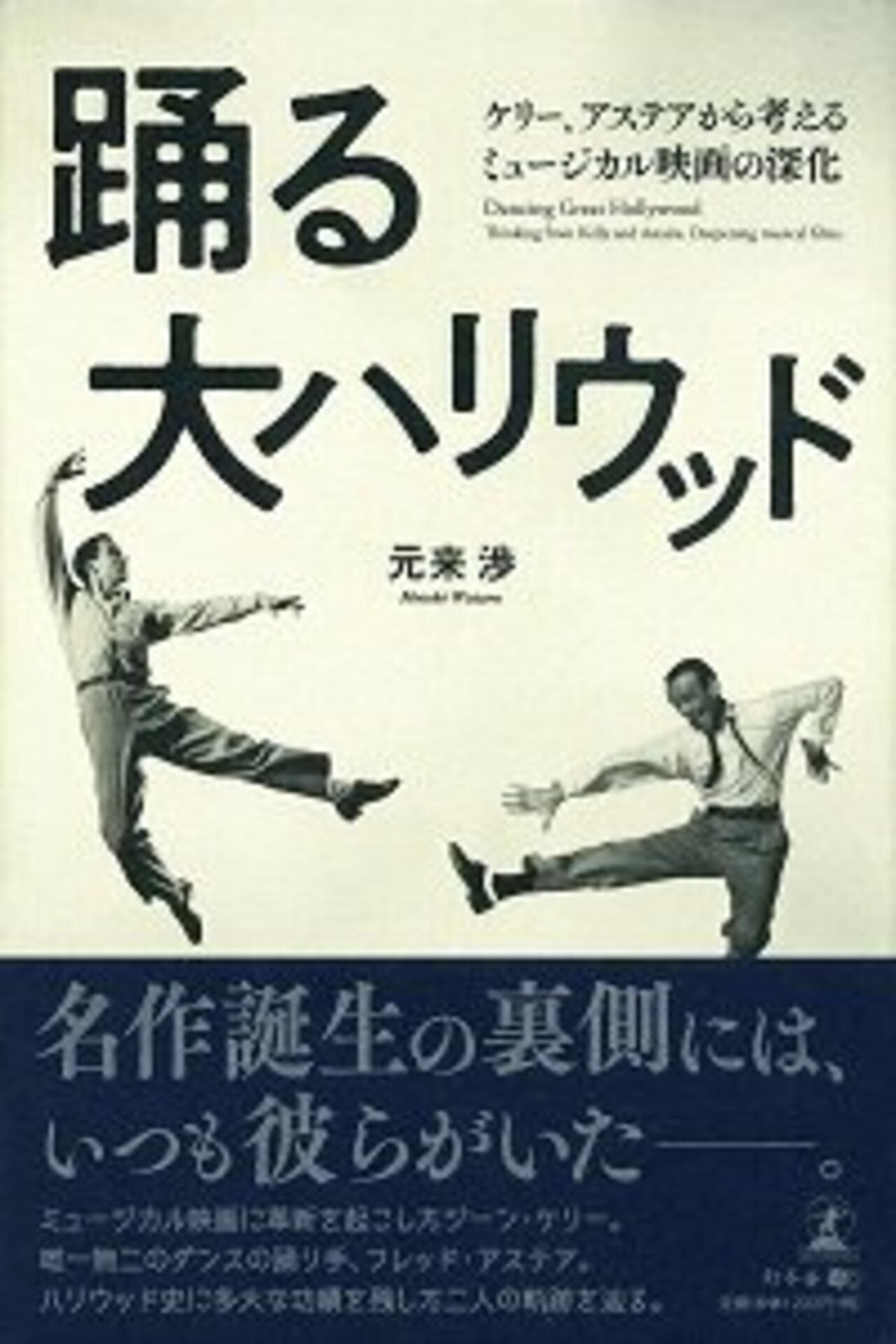物語の本筋ではないところでも力を抜いていない。このことにより、観客の興味を途切れさせず、そのままストーリーに引き込むことができた。
たとえば冒頭、プレミア公開された映画「宮廷の反逆児」の場面。ジーン扮する主人公がアクロバティックな動きでダグラス・フェアバンクスばりの華々しい活躍を見せる。観客は映画の中の観客と同じ気持ちになり、活劇シーンについ見入ってしまう。
ドンがスタントマンをしていた頃を描く映像では、小屋の爆破シーンにしろ、高い崖からオートバイごと飛び降りるシーンにしろ、「ミュージカル映画のおまけのシーンでここまでやらなくても……」と思うほど危険なスタントを演出している。
こういったことの積み重ねが、作り物である映画のリアリティーを担保している。物語の時代背景を的確に描くことによっても、映画の真実味を増すことに成功している。これには俳優やスタッフの実際の経験や知識が大きく貢献していると思われる。サイレントからトーキーへの移行期は、撮影時から二十二~三年前のことにすぎない。スタッフの中には当時から映画界で働いていたり、親が働いていたという人も多かった。
事実、撮影中ジーンの下へは、MGM各部門のスタッフが当時のエピソードを伝えたいとよくやって来たという。また、ジーンらのようにその時代を観客として体験している人間も多い。そう言った人々が作りだすリアリティが、コメディーであっても物語の真実味を裏から支えていると思われる。衣装デザインのウォルター・プランケットは一九二〇年代からデザインを手がけていたベテランで、時代背景にあった衣装をデザインするのは容易なことであった。
しかし、風刺的な意味を強めるため、スカートの丈をわざと当時より短めにするなどの工夫をしたという。美術監督のランドール・デュエル、セット担当のジェイクス・メイプスは当時のマイクロフォンや撮影機材を見つけ出し、ガラス張りの録音室やカメラを収める覆いを再現するなどして、当時のスタジオの雰囲気を作り上げた。