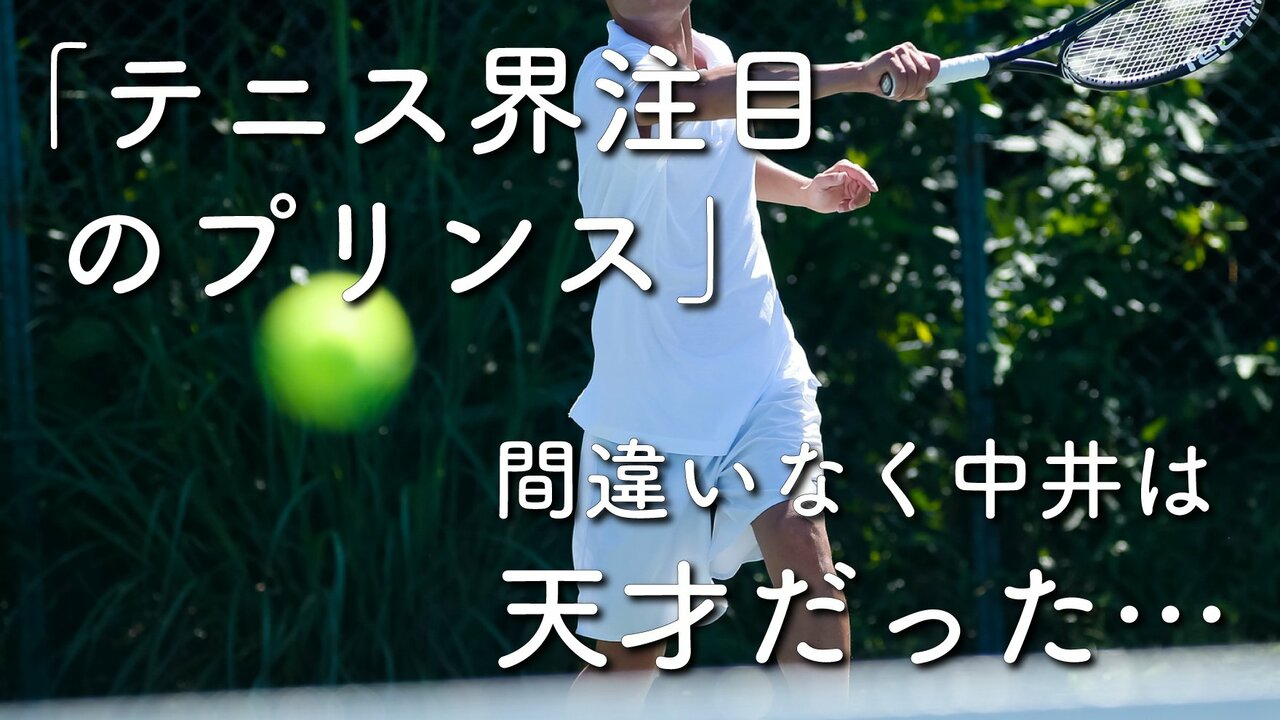中井①
十九年前。
『中井』は有明にいた。決勝戦だった。
人生に「たら、れば」は無い。もしあの時こうしていたら、もしあの時こうしていなければ。後悔したその時に時間を戻してやり直したい、もう一度その状況になったら今度こそ間違いなく失敗しない。人はそう思う。
だが、躓いた人にいちいち時間を戻していたら、この世の秩序は保てない。そんな都合のいい話はないのだ。
しかしそれでもテニスプレーヤーの中井にとって、この日だけは無かった事にしておきたかった。悪夢の一日だった。
当時の中井の宣伝文句は
「慶聖大学三年、長身に精悍なマスク、天才プレーヤー、テニス界注目のプリンス」
だった。取って付けた様な、歯の浮く様な、今の時代から見れば何とも陳腐で古臭い広告だった。
ただこの申し分の無い、隙の無いキャッチフレーズが、後々中井を苦しめる事になる。
人は実は少しの欠点を与えられる事によって楽になる。もし中井が慶聖大学生でなかったら、低身長のずんぐりむっくりのブ男だったら、泥臭い粘りのプレースタイルだったら。その一つでも当てはまるものがあったのなら、運命は好転していたかもしれない。
ただ当時の中井は悲しい程に、表面上だけはその紹介状通りだったのだ。天才。そう、間違いなく中井は天才だった。
中井は中学二年まで野球をしている。レギュラーだったが、部活に燃えているといえるほどの熱量は無かった。テニスに触れる、結果的にテニスに転向する切っ掛けとなったのは友人だった。
その兄貴がテニスクラブ会員だという。中学の部活で行う軟式ではなく、硬式だ。週末兄貴とプレーをするから一度見物に来てみれば、というものだった。中井は渋々と快諾の中間ぐらいの気持ちで了解した。
当日は当然流れで一緒にプレーをする事になるが、中井は初体験だ。だが天才は最初から凡人とは違い、三十分程の練習でほぼ完璧にそのコツをつかんでしまう。ルールは知っていたので、とりあえず友人からミニゲームをしてみようという事になった。
話にならなかった。一応経験者のその友人を、中井は一蹴する。中井が軽く打った打球に、友人は右往左往する。中井としては不思議な感触だった。
中井が振り回した打球に、友人は必死に追いつき喰らいつき、やっとの思いで打ち返すのだが、友人は何故かわざわざ中井の居るところに返球してくるのだ。無意識だった。
中井は本能的に返球される位置にポジショニングしていたのだ。予測。一流プレーヤーに絶対必要な条件である。フィニッシュは友人の到底追いつけないガラガラのコート上に、ボールをポンと置いてくるが如く軽く打つだけだった。
次の対戦は兄貴と。年齢は中井の友人と十歳ほど離れていたので当時二十四、五歳であろうか。鼻息荒くテニス歴十年の自称上級者を名乗り、弟のリベンジの勢いで試合に挑んできた。
結果結論相手にならず。中井が兄貴にではない。兄貴が中井の、だった。だがさすがの中井も十歳も年上の対戦相手に空気を読まざるを得ない状況だったので、表面上は兄貴を勝たせる事にした。
相手のプライドを傷つけない程度にギリギリのところで負ける芝居(芝居と悟られない)をさせられたのには苦労した。プロのコーチがスクール生によく行う接待テニスを中学生で既に行っていたのである。
中井が接待テニスをしたのは後にも先にも生涯ただこの一回だけだった。
後日、さらに強い相手と。現役の大学四年生テニス部。ややこしいが、友人の兄貴の弟の同級生だ。こうなってくると、中井ももう直接の人間関係ではないので遠慮する必要は無かった。