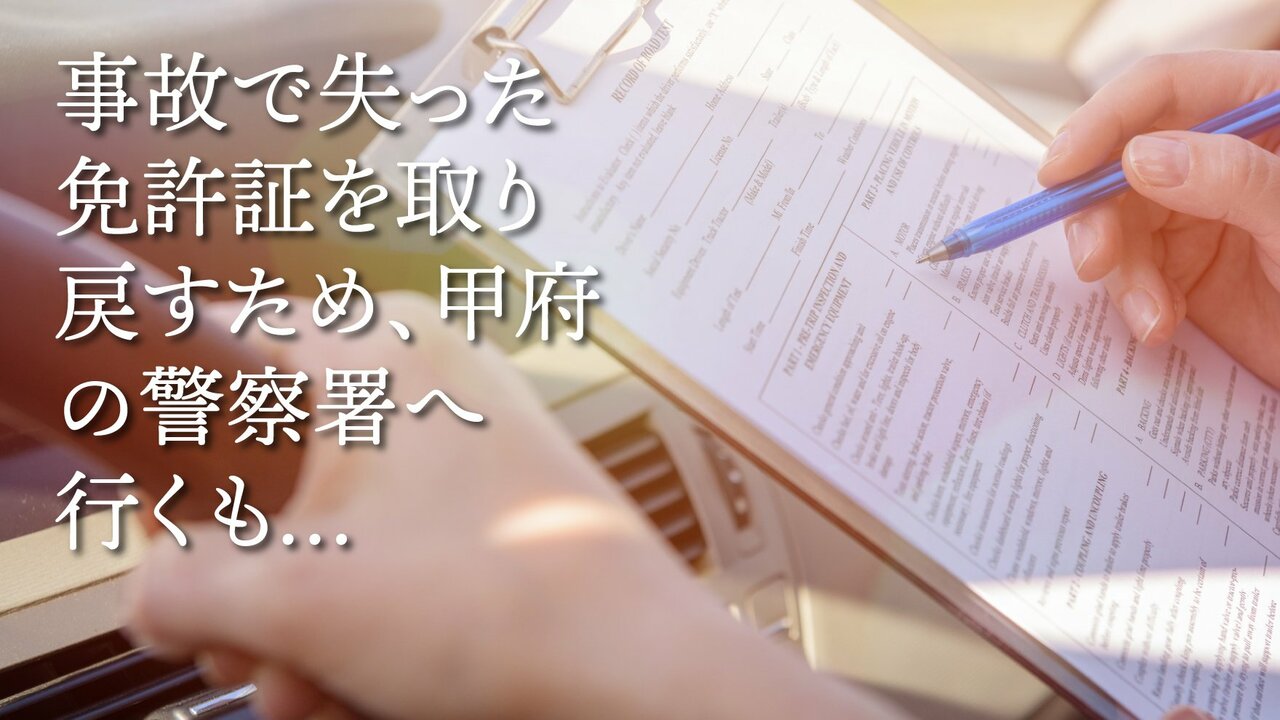別れとリハビリテーション
結局退院後には津久田先生が仕事をしている言語治療室に身を置くことになり、その前に一年間英語の本を訳すことになった。
とはいえ、この勉強の結果を見て研修生になれるかどうかを決めるということ、その後研修生になったからといって仕事に結びつくかどうかは全く分からないと強調していた。
「これを読むように」と渡してくれた本は、アメリカ人の外交官と日本人妻が太平洋戦争の渦中でそれぞれの国のために懸命に生きるという物語だった。
同期生が卒業して二年三カ月後、卒業が認められた。世田谷区の大学敷地内にある建物のプールの飛び込み台が見渡せる教室で、学長以下数人の関係者が並んでいた。
残された単位の何科目でも取得できる方法はないかと聞いていたが、まさか卒業を認めてもらえるとは思っていなかった。参加した試合が全日本選手権であったことや特待生だったことなどが考慮されたのであろうか。
ただ四年に組まれている教育実習に行けなかったので、教員試験を受ける資格は当然のことながら認められなかった。受傷時に病室を訪れてくれた学長の日焼けした顔に向かって感謝の気持ちを表したかったが、殆ど言葉は交わさなかった。
無事卒業してからある日、甲府の警察署へ作業療法士の斎藤先生と出かけた。
事故のために一度失った免許証をなんとか取り戻したくて、その可否について尋ねるためだった。両手の指が全く動かなかったが「なんとか運転がしたい」という思いから、作業療法室で運転用の補助具を作ってもらい運転の練習をしていた。
決して手指にフィットしたものでもなく、格好もいかにも素人が作った作品であったが、運転ができればどうでもよかった。面接室に通されると、紺の制服を着た五十半ば過ぎくらいのやや恰幅のいい人が待っていた。
「実は私の勤めている病院に入院していまして、どうしても車の免許が取りたくてご相談に来ました。私は作業療法士の斎藤と申します」
先生は自分のこれまでの経過や医学的な事柄について説明してくれた。署長さんらしきその人は、
「それでは伊庭さん、いくつか聞かせてもらいます。まず歩くことはできませんか?」
車椅子の自分に向かってそれはないだろうと思ったが答えるしかなかった。
「はい歩けません。両足とも全く動かすことはできません」
「じゃあ手はどうですか、動きますか」
「このくらいまでは上がりますが……」
両手を頭の近くまで上げた。
「指はどうですか」
そう右手を開いたり握ったりして真剣な顔で自分を見たが、
「駄目です、動きません」
自分は右腕を前に出すのが精一杯だった。
「こっちの手はどうですか」