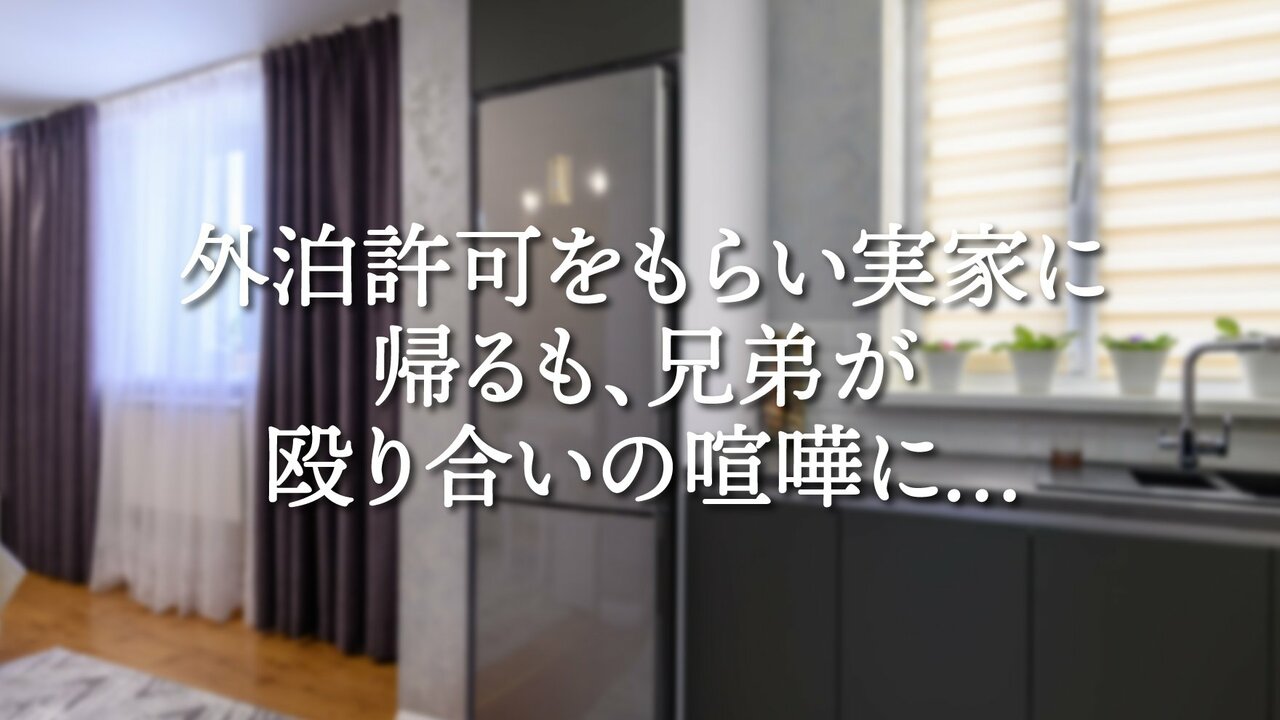第三章 石和 別れとリハビリテーション
「久しぶりでしょう」
「いやー気持ちいいね、連れてきてくれてありがとう」
しばらく川下に向かって車椅子を押してもらった。今までの病院生活で味わった暗くて重苦しい感情が風とともに流れていくような気がした。
少しでも長くこの場所に留まり、目と耳と肌で贅沢なくらいの自然を感じたかった。
八月に外泊許可をもらい実家に戻った。仕事で石川にいた父の姿はなかったが、久しぶりに兄弟四人が顔を合わせた。昼も夜も友達が来てくれ、布団の上に伏している自分に声をかけ元気な頃の話で盛り上がった。
病室から持ってきたテープデッキで、ヘッドホンを耳に当てながら音の凄さに興奮気味な友もいた。思っていたほど治っていないと感じながらも、
「良くなったなー、前はここまでしか動かなかったよ」
などとややオーバーな笑顔で励ましてくれた者もいた。しかし三日目の夜、友達が帰ってからそれは起こった。
「いい身分だなー克彦、動けなくてもこれだけ集まってくれるんだから」
長兄から不機嫌さを隠さない言葉を投げかけられた。
「何が言いたいんだよ」
「もう少し考えたらどうなんだ」
「何がだよ」
「そんな高いもの買って、うちが今どういう状況かお前にも分からんはずないだろ」
小樽からの入院以来、家が大変なことは知っていた。入院費だけではなく介護費もかなりかかると聞いていた。
「俺にだって分かってるよ。無駄遣いなんかしてねーよ。これだってスキー部の連中がお見舞いにくれた中から使わせてもらったんだ」
「それでもお前は甘いんだ」
長兄の言うことは確かに正論だったが、悔し涙が滲んだ。
「なんの楽しみもねえんだから、それぐらいいいだろうが」
三番目の兄がつっかかった言い方で長兄を責めた。
「うるさい、お前は黙ってろ。金のことだけじゃないんだよ、精神的にもっと大人になったらどうかと言ってるんだ」
「だからといって何すりゃいいんだ、手も足も動かせんし、ただ寝ているだけでいるしかない克彦の身にもなったらどうなんだ。子供が一人増えたと思って一生克彦の面倒は見るって言ったのは兄貴だろ」
いよいよ体を長兄の方ににじり寄せれば、
「うるさい、そういう問題じゃないんだ」
ついに長兄は三男を両手で突き飛ばした。カーッとなった三男が長兄に殴りかかったとき、突然ガチャンという大きな音がした。
テーブルで叩き割ったビール瓶を振り上げたのは、
「いい加減にしろよ、みっともねえ」
二十代のときに事故で聴力を失った次男だった。何のことで兄弟喧嘩をしているのか分からなかった彼は、かなり興奮した表情で怒鳴っていた。自分のことで言い争っている兄たちを止める術も持てない惨めさと悔しさが胸を突いた。