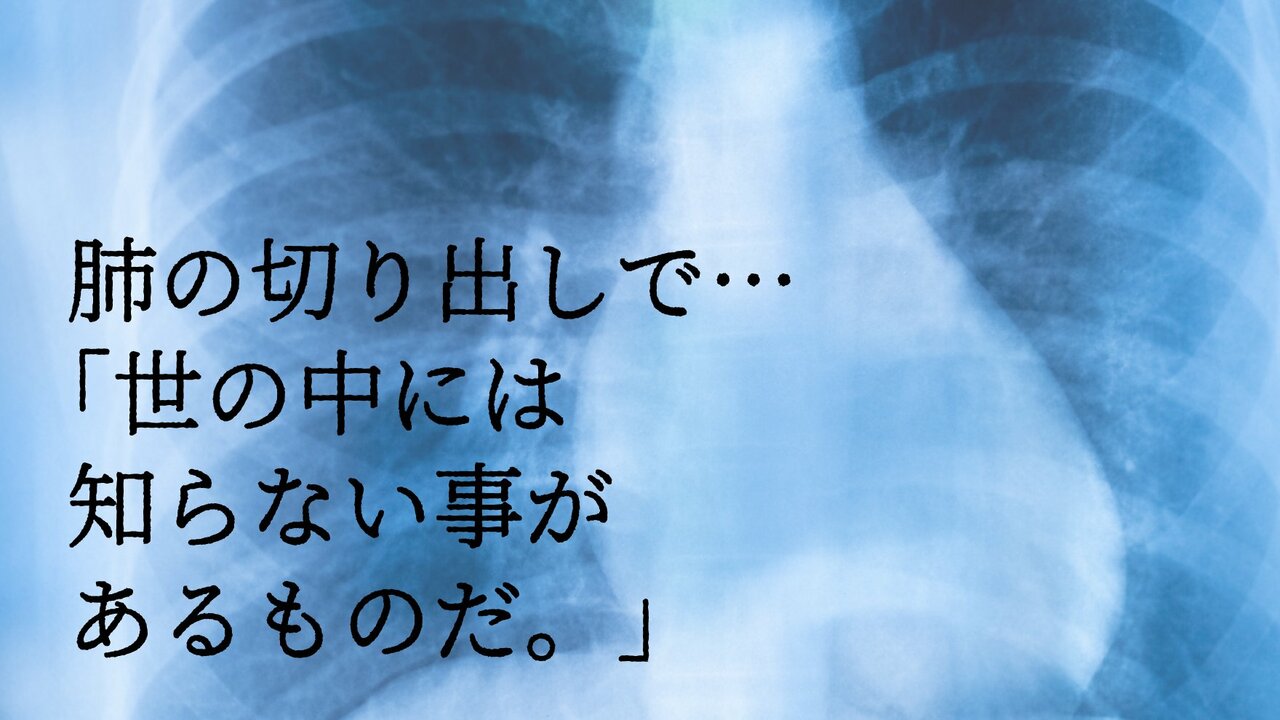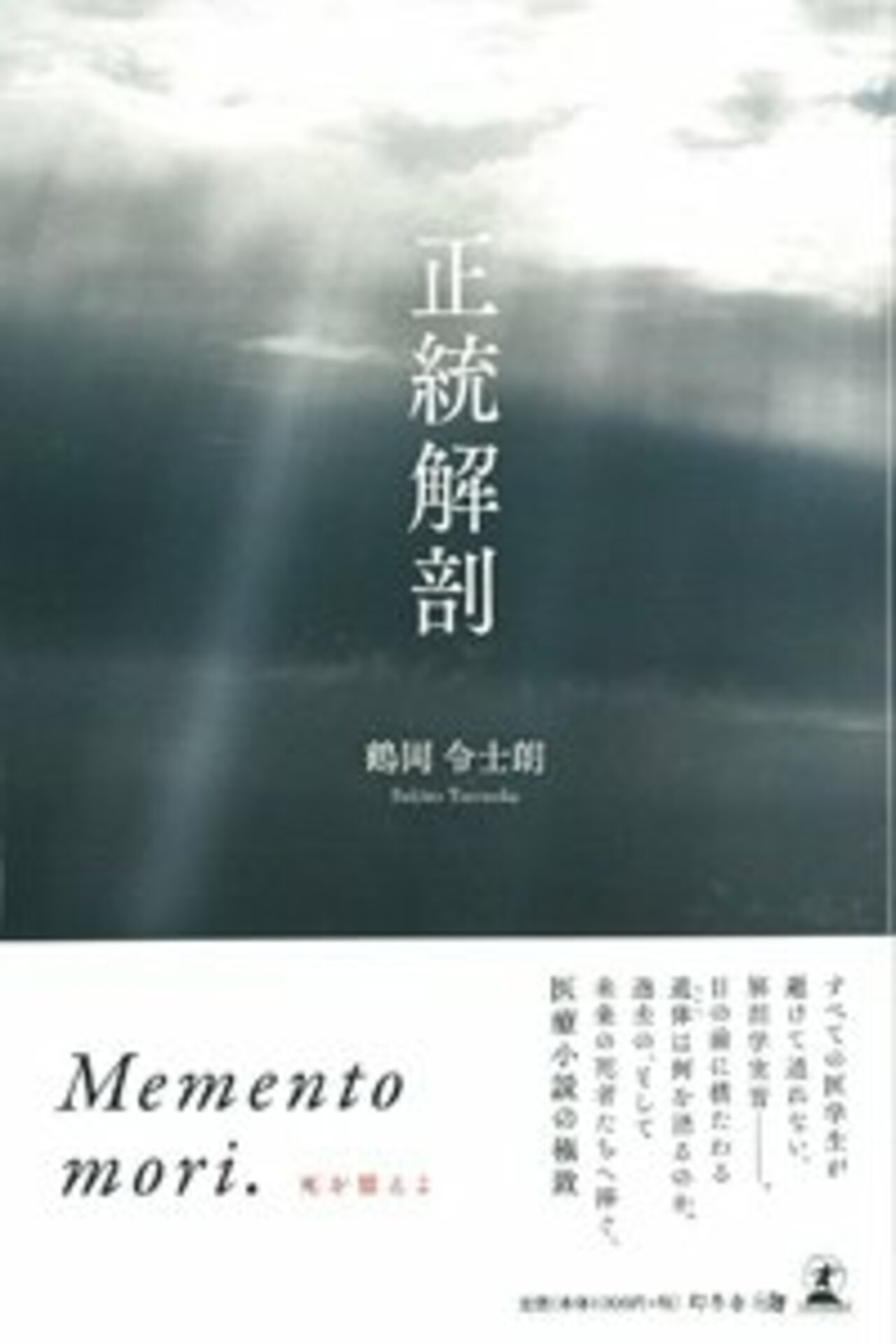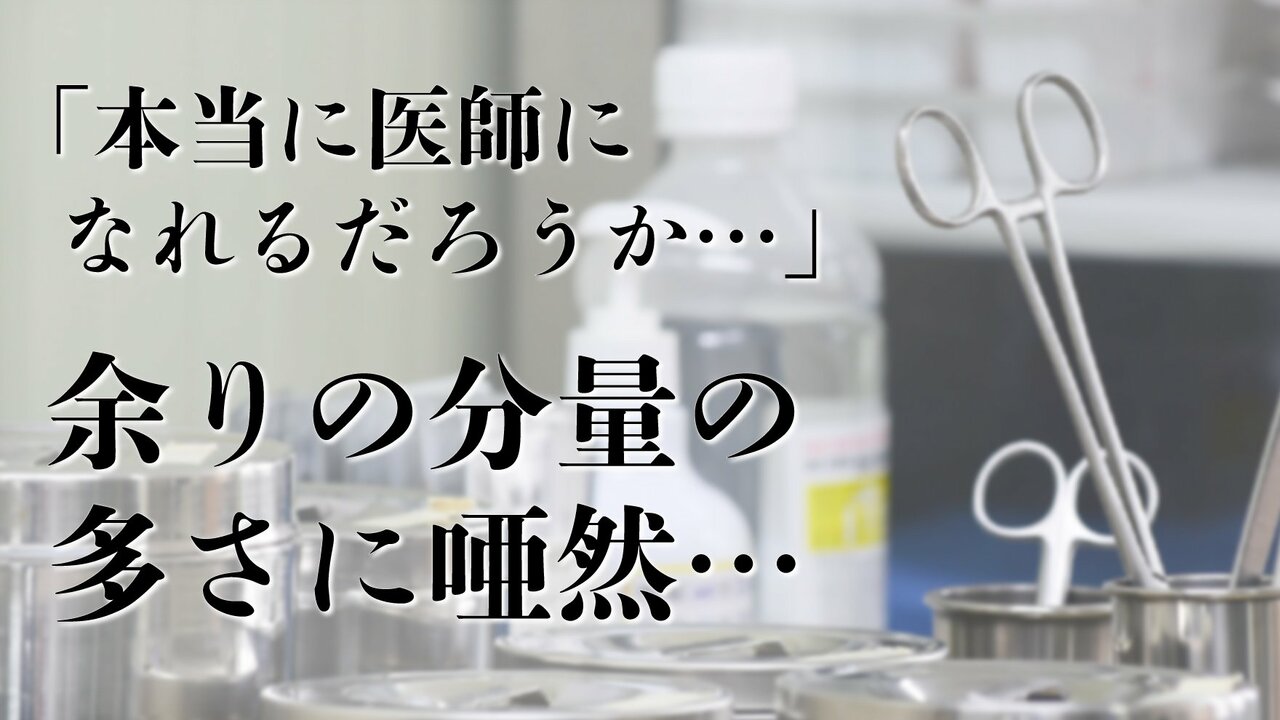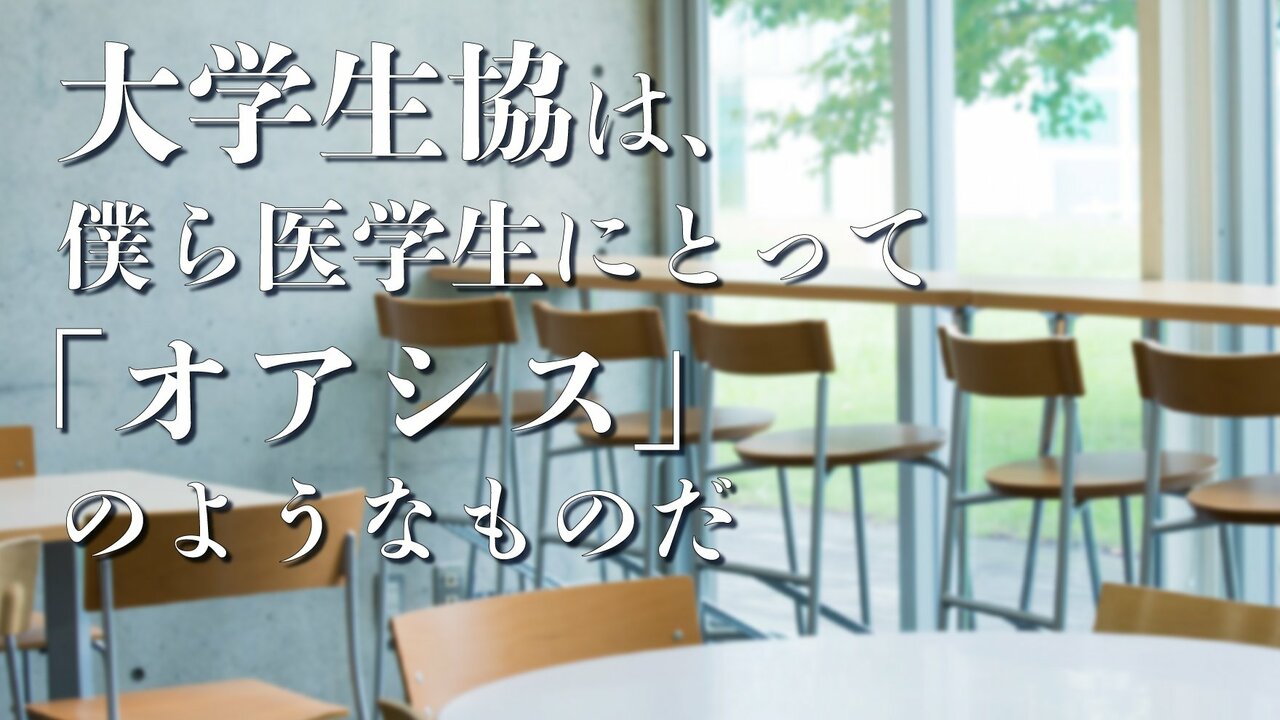肺が姿を現し、取り出す
*壁側胸膜を縦に切開すると、本来は何もないはずの胸膜腔(肺表面と肋骨の裏側の間の空間)の向こうに肺が現れるが、表面を肺胸膜がくるんでいるので、光沢を成して見える。
多くの遺体では、壁側胸膜と肺胸膜の間に病的癒着があり、これを剝がす必要がある、とテキストに注意がある。それは胸膜炎による瘢痕化で、大抵の人にあるという事は、誰でも知らない内に大なり小なり、風邪をこじらせた時などに胸膜炎を起こしている訳だろう。
テキストにはそのメカニズムが解説されている。胸膜炎すなわち炎症が起こると、浸出液が胸膜腔に溜まり、液中に溶けている線維素がやがて析出し、胸膜の癒着が起こる、と。
つまり接着剤の働きをして、壁側胸膜と肺胸膜をくっつける訳だ。そして、その線維素の塊に血管や細胞が侵入して、生きた組織になってゆくと説明してある。その結果を器質化と言う。
大きい血管が出来ている場合には、人工気胸の際に大出血を起こす事があるので注意が必要だ。
他にもいろいろ説明してあるが、呼気のときに比べ吸気時は肺の体積が増えるので、その分の胸膜洞という余分の空間があること、胸腔と胸膜腔は異なるというのが印象に残った。
いよいよ肺を切り出すのだが、予備知識として、説明を読むと、右肺は上葉・中葉・下葉の三つの区分に分かれるのに、左肺は上下の二葉にしか分かれないという。
肺が幾つかの部分に分かれているとは知らなかったし、左右その数が違うというのも、初めて知ったがなぜなのだろう。そもそも、解剖学はどのように発達してきたのだろうか。
もともとは、やはり、誰しも自分の身体がどうなっているのか、知りたいという好奇心があるのは当然だろう。
しかし、普通、血を見るだけで本能的に顔を背けたくなる。それを上回る恐いもの見たさ、好奇心から始まったのだろうか。次に、肺を切り出す。
肺根と呼ばれる、大きな血管と気管支の束がまとめて肺間膜に包まれ、一本の木の幹のような、茸の足のような形になっている。この束を切断して、ついに人間の肺を取り外す。
片手で肺の全体を押し退けて、なるべく肺根を見えるようにし、メスを刺入する。強い抵抗を予測したが、思いのほかすんなりと、まるで豆腐、ネギでも切るような具合にあっけなく切れた。
切り口を見ると、気管支も血管も、厚さの薄いゴムのチューブみたいだった。次に肺を取り出すが、この時は、さすがに四人とも緊張した。
そっと両手でくるむように包み持って、ゆっくりと持ち上げると、約600、700グラムの重量が両手にはそれ以上に感じられる。右の肺の方が左の肺より、50から100グラムほど重いらしい。
切り出した肺を観察する。指で一部を押すと、内部の空気が他の部に移動する、捻髪水泡音と呼ばれる音がする。成人では、肺表面は、灰青色をしている、とテキストに書いてあるが、保存していたためか、そんなふうには見えず、むしろ煉瓦色だ。
そして、喫煙家らしく、黒い粒が転々とまぶされている。斑状の模様だ。おそらく、外からは見えないが、内部の肺胞の一つひとつにこのように沈着しているのだろう。肺癌になるはずだ。世のヘビースモーカーたちは知らぬが仏な訳だ。