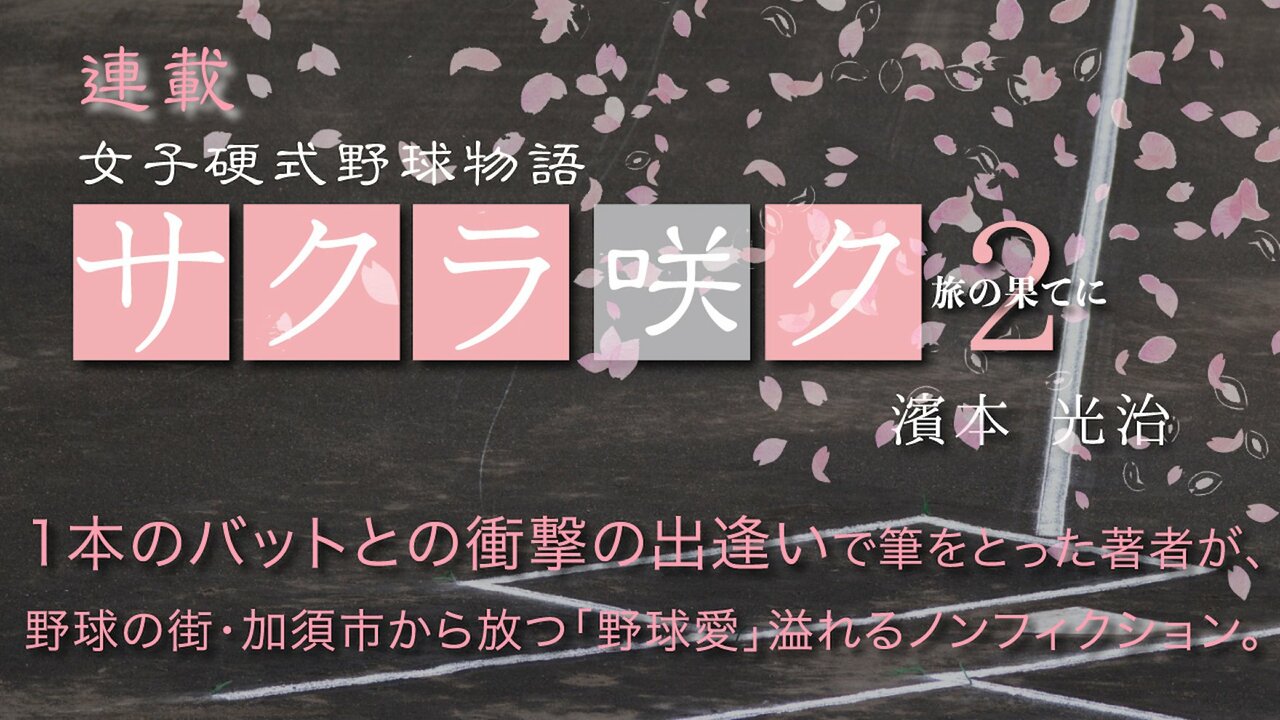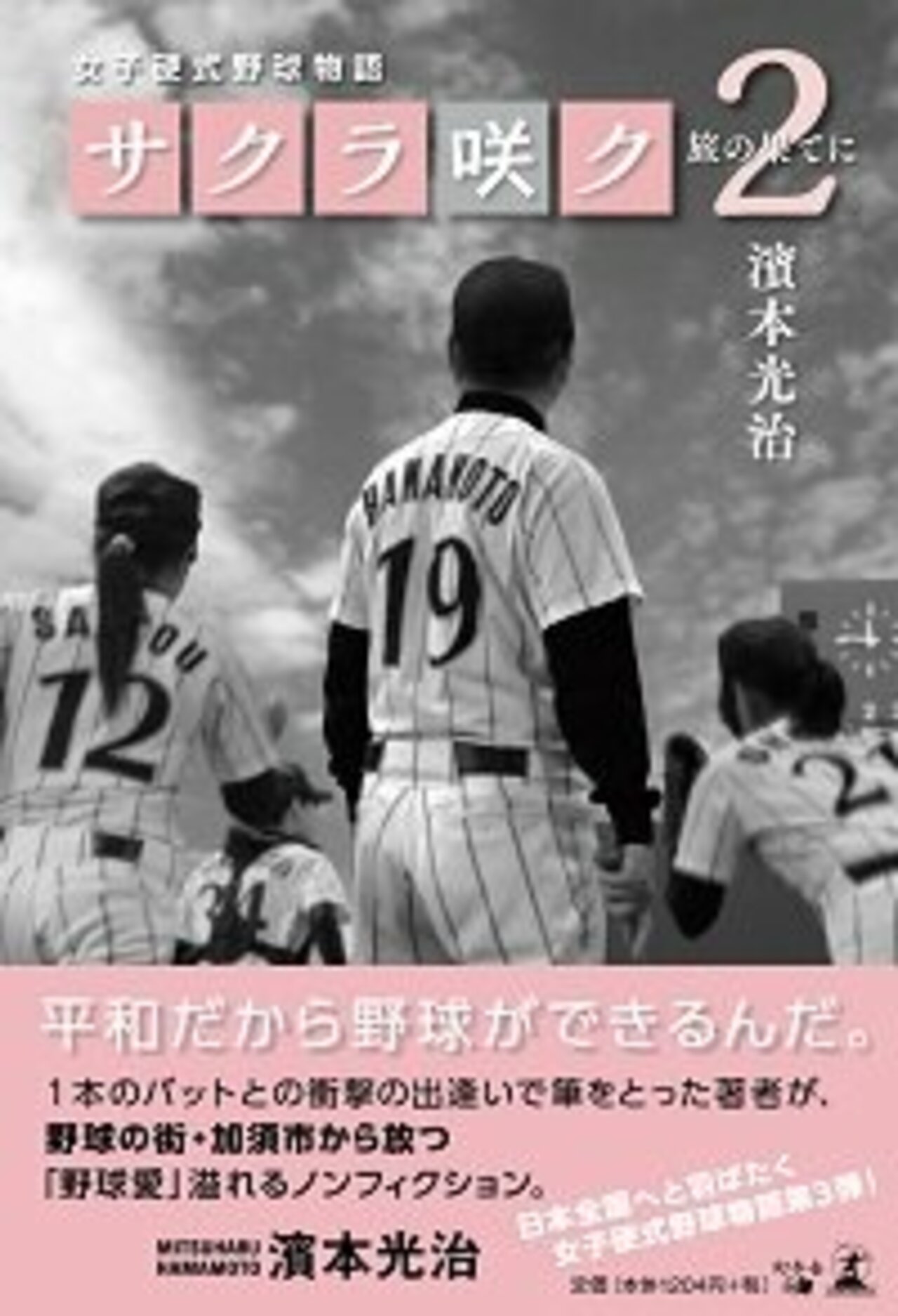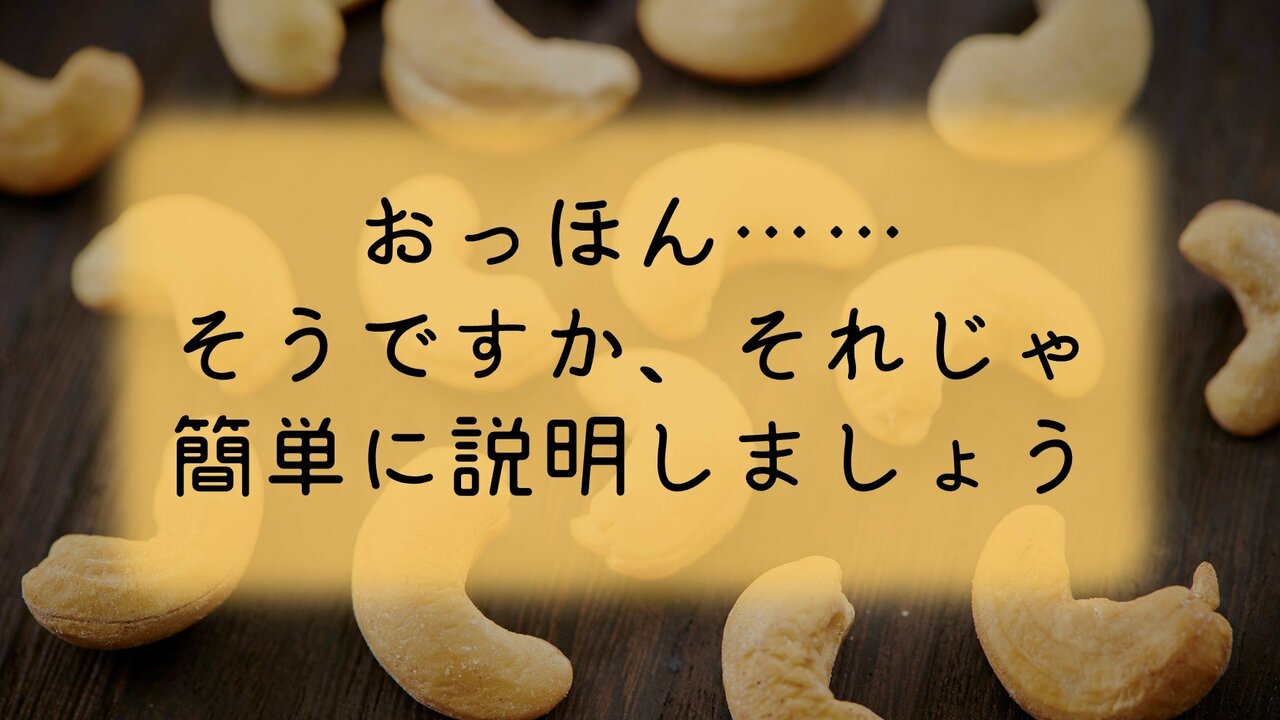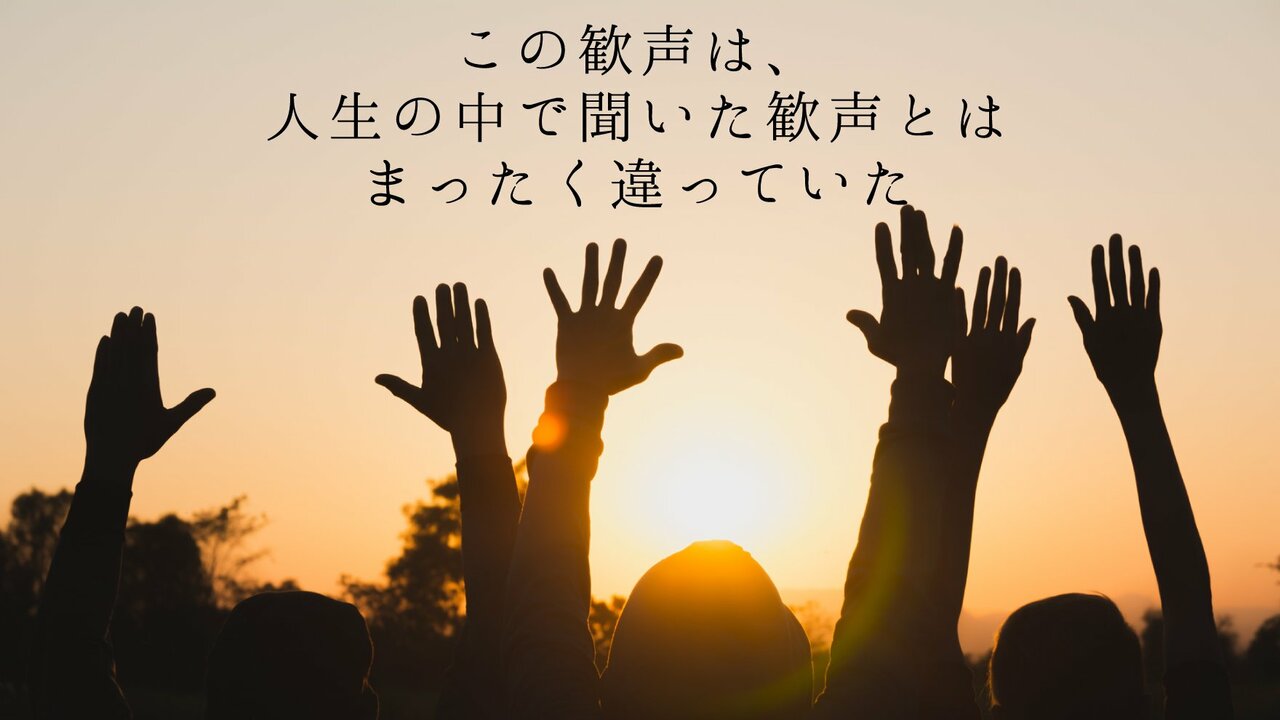第二話 東日本大震災物語
1
関東平野のほぼ真ん中に位置する人口約11万4千人の街、埼玉県・加須(かぞ)市。
2017(平成29)年2月26日、東京都心から約40から60キロメートルのエリアをぐるりと囲む首都圏中央連絡自動車道(圏央道)がほぼ開通した。
千葉県・成田空港や神奈川県の両方に行きやすくなり、加須市はまさにアクセス、流通経済など関東の中心となり、四季折々の豊かな自然のなかでますます発展する街になるであろう。
私はその市内にある花咲徳栄高校に勤務していた。出勤の朝、車で市内を通って、東武伊勢崎線を横切る陸橋の頂点に差し掛かったとき、何百キロも先が見通せる快晴の日、真正面には白い雪をいただいた霊峰富士が関東平野を見渡すように峻厳とそびえ立っていた。
その右側には秩父連山の厳かさが美しく醸し出されていた。
(なんてきれいな景色なんだ……。群馬県の方を見ると赤城山が、茨城県の方を見ると筑波山が鮮明に見え、こんな景色を眺めながら通勤できるなんて、僕は幸せだなあ)
と、加須市で生活することに喜びを感じていた。
2011(平成23)年3月10日は花咲徳栄高校の第27回の卒業式であった。
第1回から厳粛に挙行されている本校の卒業式は日本一だといっても過言ではないと思っている。各担任が事前に何回も練習をして、思いを込めて最後の呼名をした際、全員の生徒たちがはっきりとした返事をし、一礼をする所作は美しく、見事な光景である。
2時間あまりの間、生徒は微動だにせず、3年間の思い出を瞼に浮かべながら緊張感を持続していたため、最後には在校生たちの鳴り止まない祝福の拍手の音の渦の中を、お世話になった担任と共に退場するときは、男女問わず多くの生徒が落涙し、私も泣き虫ハマーになっていた。
卒業式後、各クラスで最後のホームルームが終了し、各運動部の卒業生たちは3年間所属していたクラブが待ち受けるそれぞれの場所で最後のお別れの集まりをしていた。
女子硬式野球部の卒業生たちも恒例の場所である校舎の2階に少し広くなっているピロティーに集まる予定であったが、今回はキャプテンの父であった須藤陽治氏が昨年10月に亡くなられたため、昨年の第1回ユース大会で優勝した「メタルテック香港」の代理監督をした宮野友宣(とものり)氏が企画し、須藤陽治氏の思い出のDVDを放映するために、教室で最後のお別れ会を催すことになった。
卒業生部員がそれぞれの思いを、後輩、保護者に伝え、私も、
「3年間で培った貴重な体験を今後の人生に活かしてください。最後に、キャプテンのお父さんであった須藤陽治さんには本当にお世話になり、感謝しております」
と、教室内にいる人たちに力強く発していた。
この年から毎年1月、栃木県・佐野市「本光寺」に永眠されているお墓に一人でお参りをし、手を合わせながら毎年のユース大会開催の御礼と女子硬式野球の現況を報告している。
帰り際、お寺の名称が「本光寺」であるのに気づき私の濱本光治という名前の間をとったお寺なんだと奇妙な縁を感じていた。
また、ここから冬晴れの日に遠くに見える富士山が、やさしく須藤氏のお墓を見つめているのに気づいたのであった。
卒業式後の夕方は、毎年恒例になっている卒業生の保護者の方々が主催の「謝恩会」に全職員が招かれ、美味しい料理をいただきながら卒業生の3年間の思い出話に花が咲いていた。
女子硬式野球部の保護者をはじめ、授業を受け持った生徒の保護者もわざわざ私のところに来て、お世話になったご挨拶をされるので、大変恐縮していたとき、
「先生、まさか親子で先生にお世話になるとは思いませんでしたね」
と話しかけてきたのは花咲徳栄高校第1期生で、私が3年間担任をした田た 鎖ぐさり洋子であった。
「はい。蓮田市の救急病院の看護師をしています」
「あっそう。それは知らなかった。じゃあ、俺がなんかあって倒れたときには、洋子の病院に搬送してもらい、お前、俺の面倒をみてね」
「先生、そのときは任せてください。最後まで面倒をみますから」
「うれしいね。これで何があっても思い残すことはないな」
と、二人して笑いながら、今日の卒業式を祝っていた。
それから3か月後、
職員室の内線電話の呼び出し音が鳴った。
「はい。職員室の濱本です」
「鈴木さんという方から外線です」
「先生、田鎖洋子の娘です」
「おー。元気か、卒業後はどうですか」
「先生、母が亡くなりました。先月、子宮がんが見つかり、進行が早く昨日亡くなりました」
「…そうですか。……」
そしてお通夜に向かった。
夕方、お通夜に参列すると当時の同級生たちが集まり、悲しみに満ちた表情で私に挨拶をしてくれた。
一通り読経、焼香が終わり落ち着いたところで私は、
「ご主人、すいませんが奥様のお顔を拝顔させていただけますか」
「先生、どうぞ、しっかり見てやってください」
と、ご主人はやさしく棺の前まで私を案内してくれた。
見ると、棺桶のふたはすべてガラスのふたになっていて、献花された花で包まれている洋子が安らかな表情で横たわっていた。
私は手を合わせて、
(なんであなたが先に逝くんだ……。順番が逆だろ。逆縁じゃないか。)
と、こころの中で叫んだ瞬間、今までこらえてきた感情が堰を切ったように、洋子の遺体を見つめながらあたり構わず号泣していた。