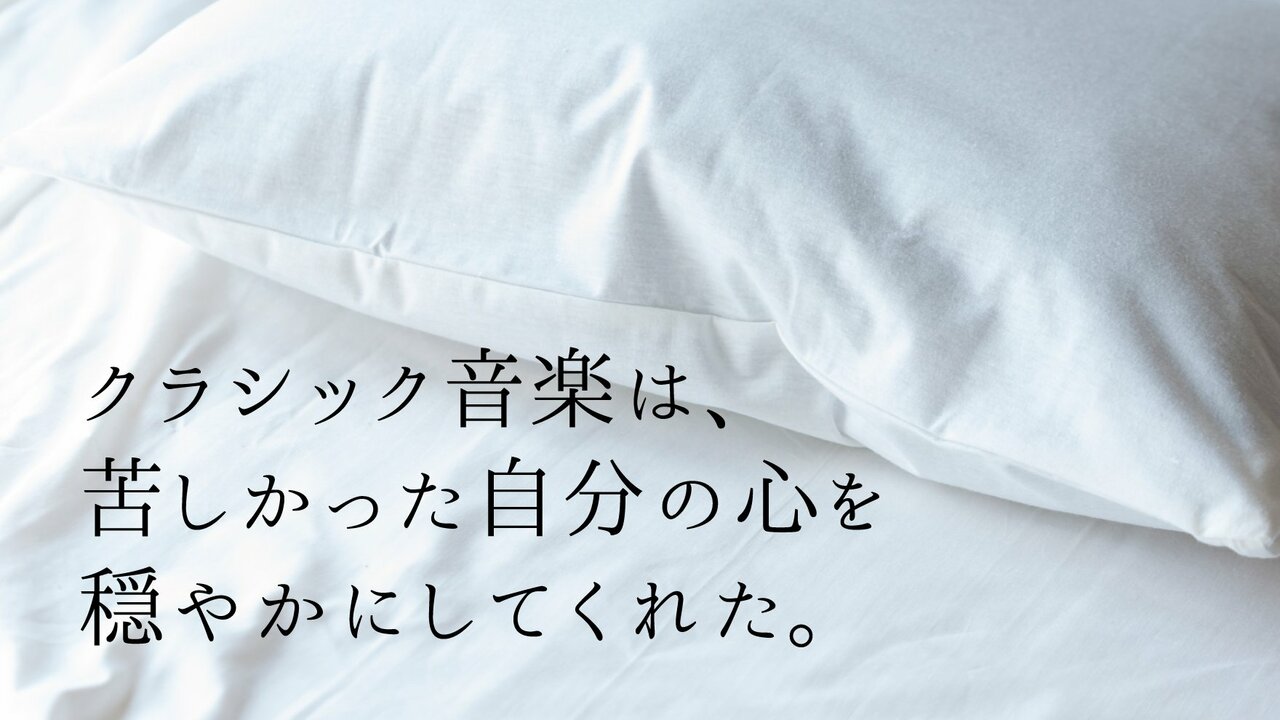【関連記事】「出て行け=行かないで」では、数式が成立しない。
第三章 石和 別れとリハビリテーション
夏休みも終わりに近く、合宿所に戻ってから十和田湖での夏期合宿に参加するため準備を始めた。
結局二カ月近い休みの中で聡子には一度しか会えなかった。この間に世田谷の合宿所と、小学二年生のときから高校を卒業するまで育った雪深く長野県との県境に近い津南を四度往復した。
八月の末の早朝、合宿所を出発した。三国峠を越えて新潟県に入った頃、だるさと眠気を感じるようになってきた。峠を下ってから新潟市まで約百三十キロ、ほぼ平坦な道を走り続けた。
新発田を過ぎたあたりで体力は限界を感じていた。昨夜合宿所で久しぶりに顔を合わせた仲間と五時過ぎまで語っていたためである。
コーヒーでも飲むところがないかと道路沿いのドライブインや喫茶店を探したが、国道七号線とはいっても殆ど民家と畑や田んぼばかりの田舎道であった。
時々ハンドルを握る手に力が入らず、やばいなと思いながらも気持ちよさでふーっと意識が薄らぐ瞬間を二、三度体験した。
突然車が傾き、直後に景色が消えた。目の前にコンクリートの壁が現れたとき、咄嗟にハンドルを強く握ると「ブシュッ」というような小さな音が聞こえた。
目が覚めたときには村上病院の病室で長兄が傍にいた。長兄が話すには、
「葡萄峠という場所で緩やかに左にカーブした坂道の、トンネルの入り口の右端に車をぶつけ、通りがかった大型トラックの運転手がこの病院まで連れてきてくれたらしいんだ」
「なんていう人?」
「病院の人が聞いたんだが、名前は言わなかったそうだ」
「ああ、そう」
「お前もいい加減にしろよ。いつまでもこんなことをしてたら他人ひとに迷惑をかけることになるんだから」
「分かったよ」
「見つけたとき両手でハンドルを握っていたそうだ。ぶつかる直前に強くハンドルを握ったために胸に当たらなかったらしい。鼻から血も出てたし、意識もなかったので駄目かなと思いながら連れてきたと言っていた」
「そう」
「ハンドルもそのときの衝撃で曲がっていたってさ」
その夕方、
「イバ、大丈夫なの? もうびっくりさせて」
清美と、とし子の二人が見舞いに来てくれた。とし子は将来漫画家を志していたが体はあまり丈夫ではなかった。それにもかかわらずこんなに遠くまで見舞いに来てくれたことが嬉しかった。
「どうしたんだ?」
「どうしたんだじゃないわよ。和夫君から電話があったから」
「いやー申し訳ない」
「どこか痛いとこないの?」
「大丈夫。大丈夫。俺は不死身だから」
駆けつけてくれた彼女たちの気持ちが嬉しかった。三日ほどで退院できたが、十和田湖の夏期合宿には行かなかった。いくつかの思い出が蘇ってきたが、現実の場に戻され、石和での入院生活は続いていた。
冬になっても聡子は毎週のように来てくれた。少しずつであるが確実に彼女に対する申し訳ない気持ちや、会えば会うほど辛くなってしまう切なさを感じるようになっていった。