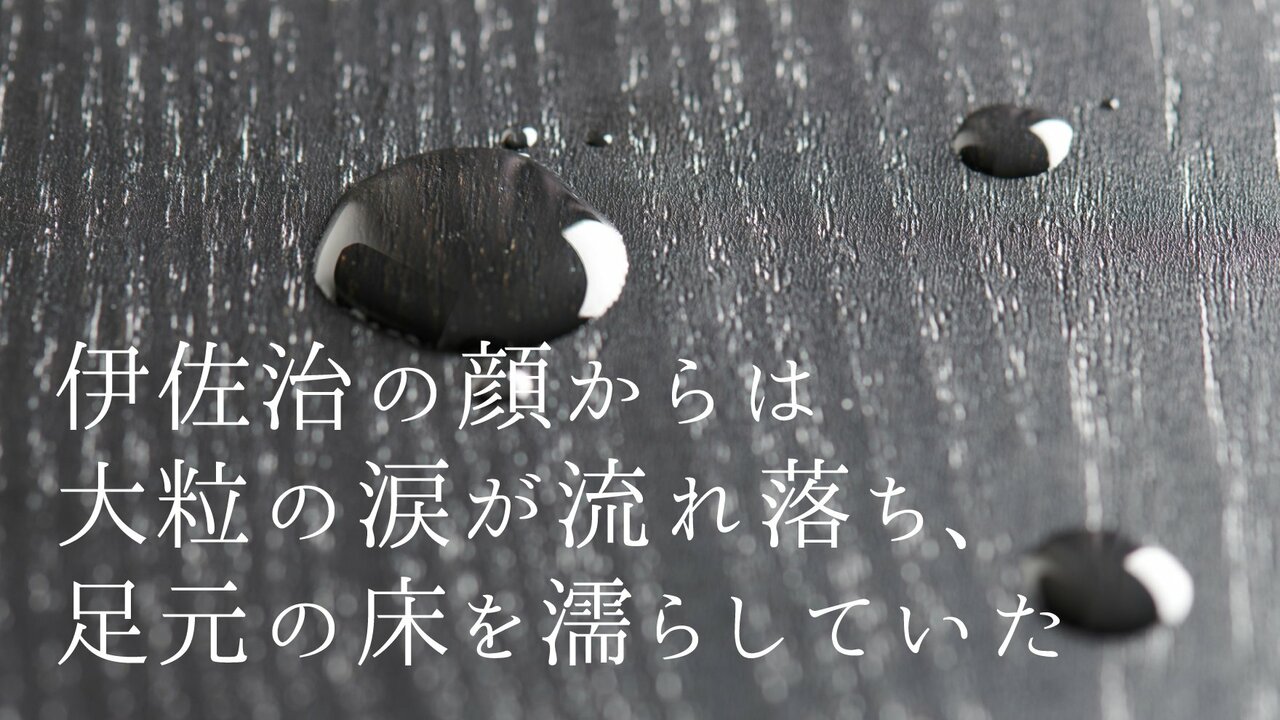「実はジャンクにはね、娘が一人いるの。不思議そうな顔をしないでよ。その娘がね、風呂から出て来た時、私に言うのよ。
『いやだな、胸がだんだん大きくなってきちゃった。お父さん、ボインの女の人って好き?』突然聞かれて、なんて答えれば言いのかわからずに、頭が真っ白になっちゃった。
その娘がね、母親に話していたの。『お母さん、お願いだから、お父さんを残して先に死なないでね』だって。さすがにショックよ。でも、ジャンクはまだまだ死にませーん。これからも頑張るぞ」と、こぶしを高く突き上げ話は続いた。
潤子には、どうしても伊佐治に聞いておきたいことがあった。「お父さん、もし私が先に逝っても子供たちと上手くやって行く自信はあるの。もう、現役の警察官じゃないのだから、鬼のような形相は卒業にして少しずつ変わらないとね」
潤子の真剣な言葉に、
「そんな縁起でもないこと言うものじゃない。むしろ、順番からすればワシが先だ」と、口を尖らせていた。
「そんなに威張って言うことじゃないでしょう。今のままだったら、私、死んでも死にきれませんよ」
潤子の優しい眼差しに、「ウーン」と、伊佐治は唸り声を上げ、空になったジョッキを恨めしそうに眺めていた。
「お客さんは神様で~す」
今日のジャンクは絶好調だった。
「ジャンクね、先月の誕生日で六十才になったの。いやね、あっと言う間に還暦よ。今日は再婚した妻からもらった赤いパンツを履いてきたからね。再婚した相手は、元妻よ」
一瞬ポカンとしているお客さんをよそに話は続けられた。
「この間、スーパー銭湯にデップリしたお腹で禿げ頭の中年男が入って来たかと思ったら、体も流さないで湯船にいきなりダイビングしてきたの。マナーの悪さに皆は大迷惑。でも、両腕に龍の模様が入っているものだから見て見ぬふりよ。だけど、ジャンクはどうしても我慢ができなかったから、静かに後ろに回り禿げ上がったおじさんの頭にジャンクのピンちゃんを乗せてやったの。『許してチョンマゲー』って、そうしたらね、銭湯にいた人たちから大爆笑が起きたの。そのおじさんたら、皆の爆笑に圧倒されたのか逃げるように出ていったわ」
舞台には、笑い声に交じって指笛が鳴り響いていた。
「そうそう、ジャンクが沖縄で実際に体験した話よ。ジャンクが興行先の社長と山道を歩いていたら、ハブが鎌首を挙げてこちらを睨んでいるの。そしたら、社長が、『動くな、ハブは自分より大きな蛇には決して向かってこないから、ジャンクの巨大なピンちゃんを見せてやれ』って言うの。本当かどうか分からなかったけど、言われた通りにズボンを下ろして見せてやったわよ。そしたら、『パクッ』と、思いっきりピンちゃんの頭を噛まれたわ。人の話を簡単に信じるなんて、バカでしょう」
手で噛まれた部分を押さえているジャンクに、「痛そうー、大丈夫だったの」と、真剣に心配している人もいた。
「あなた、ハブにかまれたんですって、本当かしら」潤子は大笑いしながら伊佐治の方に顔を向けると、
「作り話に決まっているだろう」
潤子は今まで、伊佐治の前でこんなに楽しそうに笑っている姿を見せることはなかった。おそらく、潤子はジャンクのショーを見せることで、伊佐治になにかを伝えようとしているのだと想像がついたが、凝り固まった性格と、いかつい顔つきは天変地異でも起きない限り簡単には変えられそうになかった。