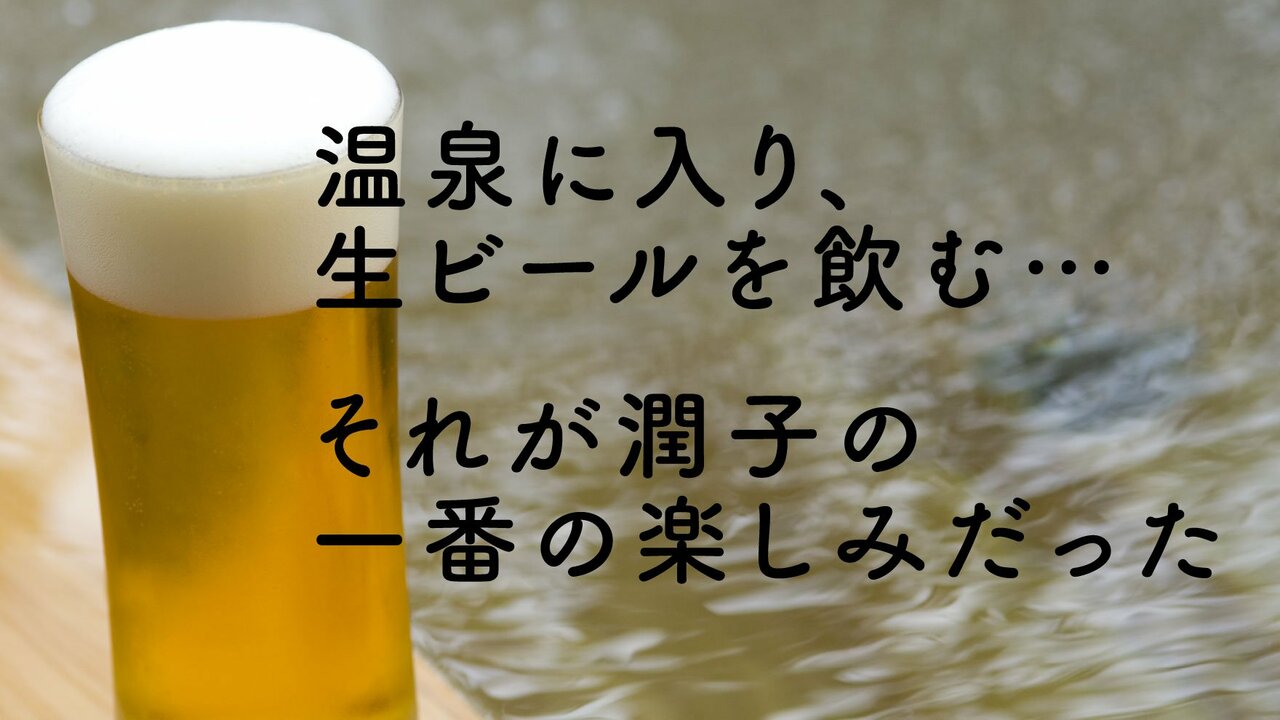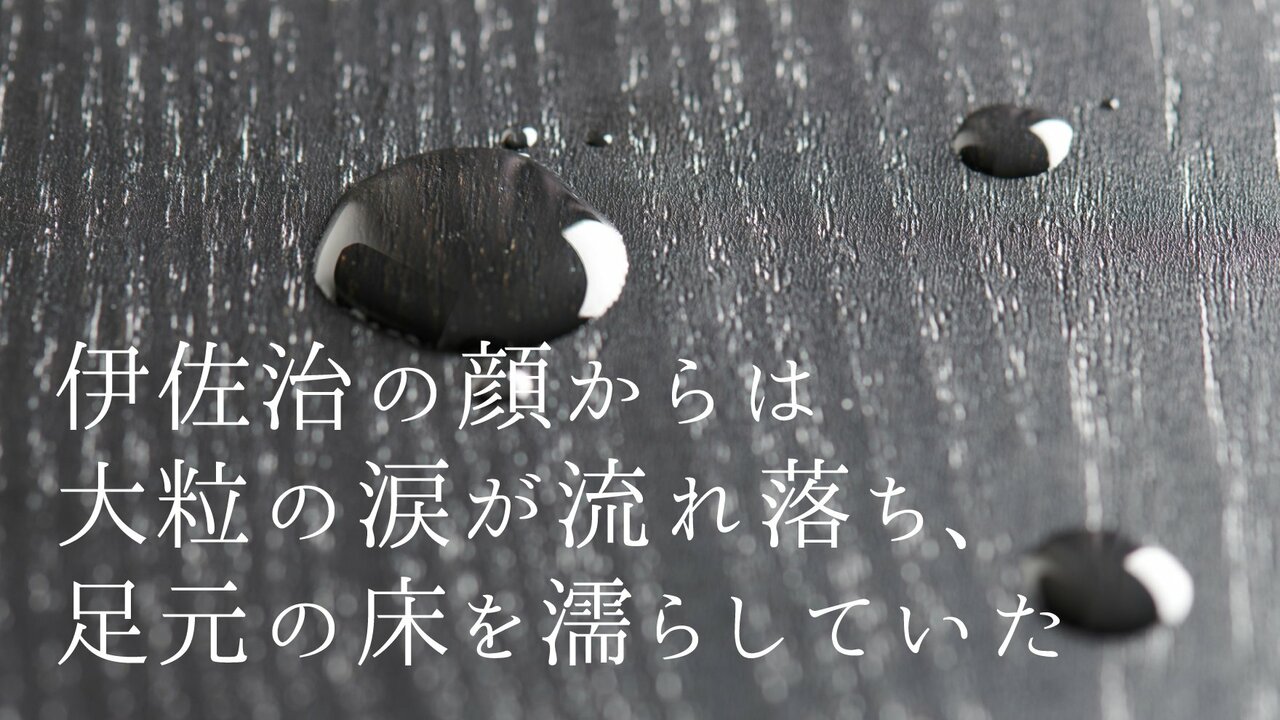【関連記事】「出て行け=行かないで」では、数式が成立しない。
伊佐治
その晩、伊佐治は先輩の言葉を思い出していた。
「声を聞きたければ、自分から電話すればいい。会いたければ自分から会いに行けばいい。意地を張るな。素直が一番だぞ」
「この人しかいない」と、自分の気持ちを固めた伊佐治は電話のプッシュボタンを押していた。
「こんな私で本当に良いのですか。後悔しませんか。ずっと、私の側にいてくれますか」
と、伊佐治は潤子の気持ちが変わっていないことを願い、自分の想いをはっきり伝えていた。
「はい。私は嬉しいお返事をお待ちしておりました」との言葉が、昨日のことのように思い出された。
もともと体が丈夫ではなかった潤子だが、日常生活にはなんの支障もなかった。翌年桃子が誕生した後、体調を崩してしまい健太が生まれたのが五年後、その二年後に悠子が生まれた。
定年を数年後に迎える伊佐治は大きな事件を抱え、帰りが不規則になることが多かった。毎日の食事は父の帰りを待つことなく、母潤子を中心に大学生の桃子・高校生になった健太と中学二年生の悠子の四人で食卓を囲むことが自然と多くなった。
潤子の作る料理は栄養のバランスを考えて作られているだけでなく、見るからに美味しそうだった。話の中心はもっぱら悠子で部活のことや友達のことが多く、桃子と健太が割って入る隙はなかった。
しかし、まれに、伊佐治が早く帰って来た時などは健太と悠子は波が引くように席を離れ自分の部屋へと消えて行った。二人は特に父親が嫌いという訳ではなかったが、それまで楽しかった食卓の空気が途端に重くなることが要因だった。
伊佐治は風呂から出ると難しい顔をして朝読んだはずの新聞を開き、出された料理をつまみにビールを飲むのが習慣になっていた。
「お父さん、不機嫌は無言の暴力ですよ。スマイル、スマイル」
と、潤子が良く話していたことが懐かしく思い出された。桃子はあたり前のように過ごしている時間があたり前でなくなる日が来るとは思ってもいなかった。
潤子の楽しみ
近くにオープンした湯楽の里村温泉で日がな一日、過ごすのが五〇歳を過ぎた潤子の一番の楽しみだった。
施設は一一時から二三時まで年中無休で営業し、一日三回、舞台でショーも行われた。温泉や食事の他にマッサージルームや仮眠室も無料で利用できるので、潤子にとってはお城のお姫様気分だった。
潤子は心臓に負担を掛けないよう長く湯船に浸かることは避け、主に足湯や半身浴を楽しむように気を付けていた。手入れの行き届いた中庭に出て籐の椅子に腰かけ、日本庭園を見ながらのんびりした時間を過ごすのも大きな楽しみだった。