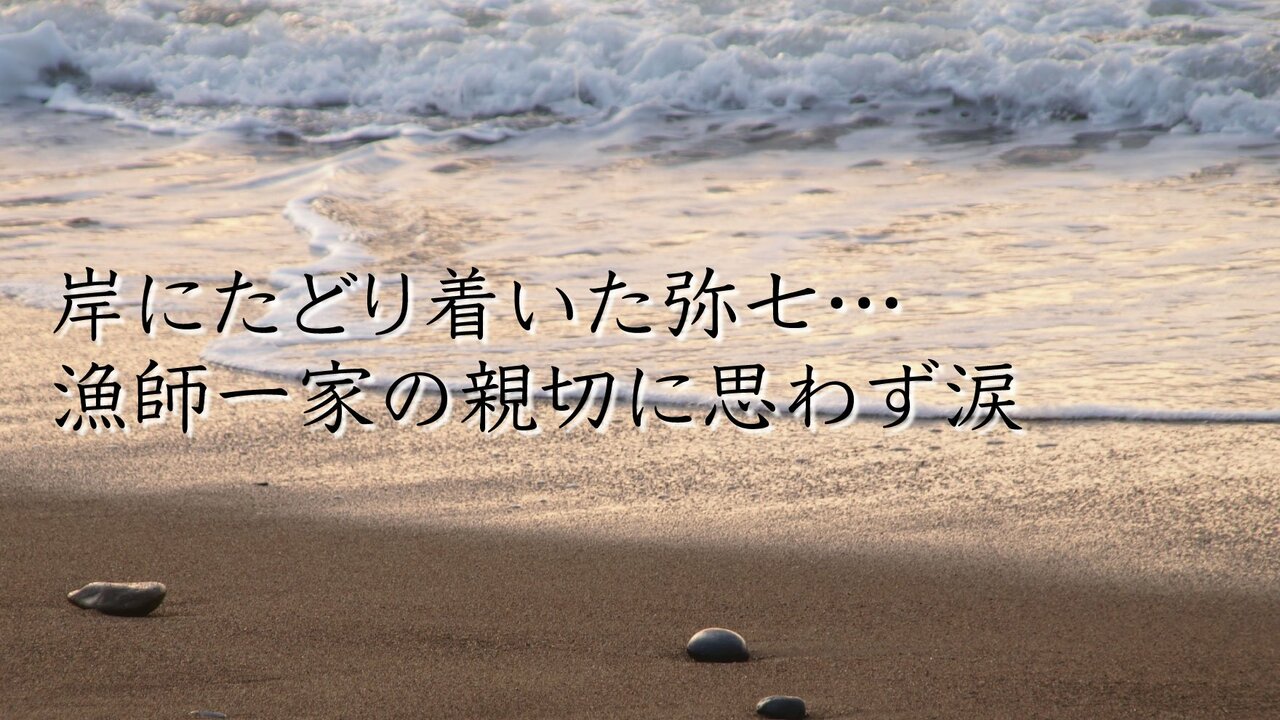「是非もありませぬ」
紐を解き、蓋を開け、錦の包みを除けたその中身は、長い緑青の塊にしか見えない。これが渡辺家の家宝だと言われてよくよく見ると、元は小刀のようであった。
「本当かどうか、遠く神代から吉備氏に伝えられた品だそうで、なんでも旅立つ者に幸運をもたらすとか」
と四郎が言う。
「ほたら、持って行かれた方がよいじゃね?」
「それではまるで、戻ってこないようではありませんか。それに、佳代を救わずに、家宝を持ち出したと千代に怒られます」
そう言われては、やむを得ない。だが悠堂は、他家の家宝を預かることに、一抹の不吉さを感じずにはいられなかった。
準備の整った、五十人を超える侍と百人近い兵が、航海の安全を祈って郷の社に参拝したのち、八艘の小船に分乗し、それぞれ莚の帆を張って出発した。水軍が使うのは、櫂を多く備えた機動性の高い小船であり、襲うとなればこれで交易船を取り囲む。普通は根拠地から遠くには行かないが、宇和島の衆にとって、馬関海峡までは掌のうちである。門司の関あたりで、その先の水先案内人を雇えばよかろう。
小船が人で満載であるので、たびたび陸に寄って、補給と休憩をしなければならない。
その夜は、日振島で野営をした。
六百年前には、藤原純友がここを本拠地として千艘もの船を指揮し、瀬戸内海全域を支配したが、はるかな過去の栄光で、今は海賊まがいの漁師が少しいるばかりである。
浜辺に出た千代が、満天の星空を見上げている。
河後森の城からは、残念なことに海が見えなかった。佳代がもう少し大きくなったら、海を見せてやりたかった。ついこの前まで、この腕の中で泣いたり笑ったりしていた佳代を想うと、胸が塞がる。その一方で、この海がどこまでも続き、それを今まさに自分が往こうとしていると思うと、佳代には申し訳ないと思いつつも、今度は胸が高鳴った。
そっと後ろから歩み寄った四郎が、「泣いているのか?」と声を掛けると、千代は振り返り、「四郎様、私にも剣術を教えてつかあさい」と言った。
四郎は頷いた。
「私も剣の腕を磨き、河後森に戻りこの手で弾正の首を刎ねる。一緒に修練しよう」