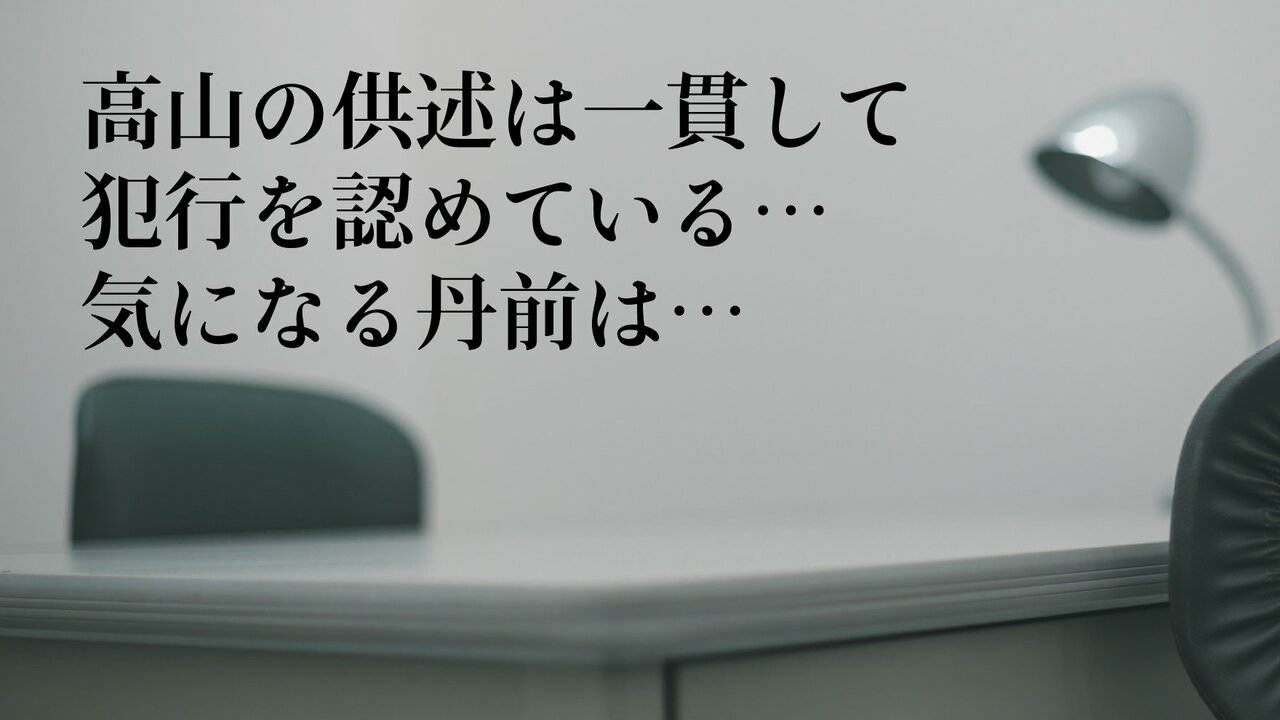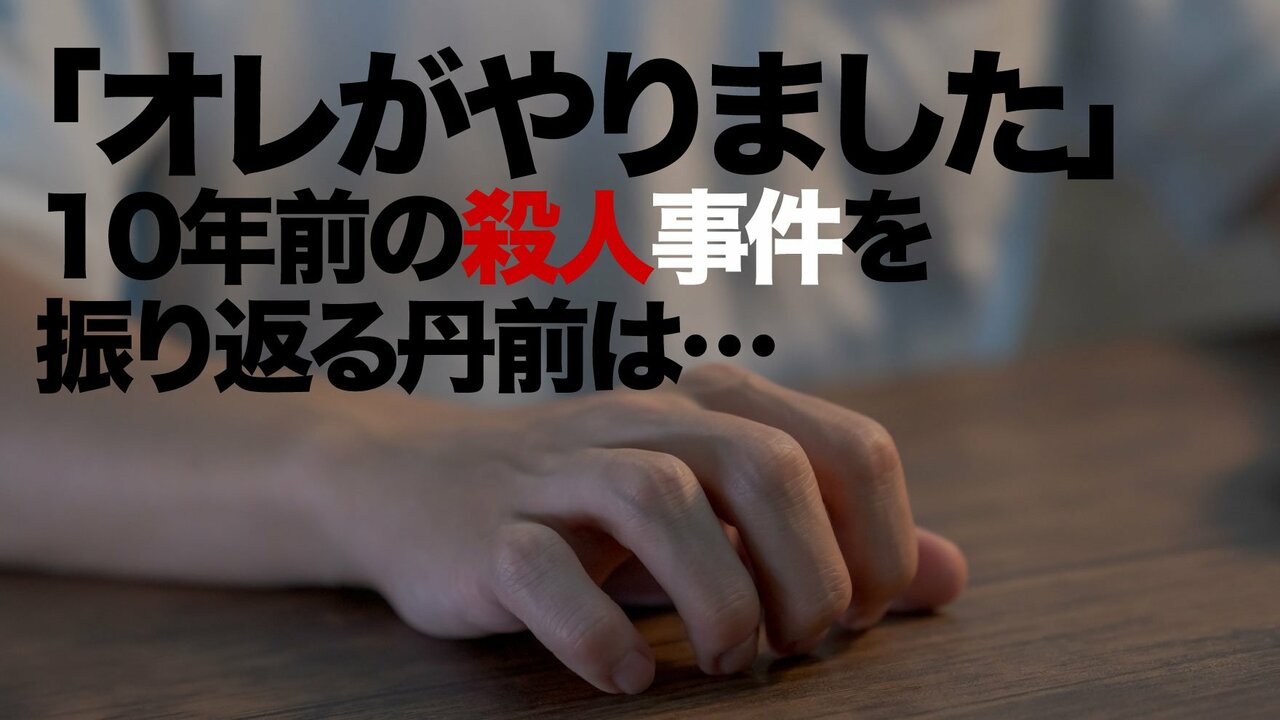真相―ヤメ検が暴く
あの電話は、いったい何だったんだろうか?
【人気記事】JALの機内で“ありがとう”という日本人はまずいない
丹前健(たけし)は、今朝も、自宅の明石からJR神戸線を使って神戸三宮の事務所に向かいながら、三日前に一人の男からかかってきた電話のことを考えていた。
朝といっても、JR三ノ宮駅から事務所に向かう道々の飲食店の前は、そろそろランチメニューを掲げた看板も並びだしている時間帯だ。とっくに一〇時を回っている。
自ずと急ぎ足になっていることに気付く。何も急ぐ用はないのにと、皮肉の言葉が頭をよぎる。道々の街路樹もすっかり葉を落としている。路上の落ち葉がカサカサと冷たい風に飛ばされて足元を転がる。
もう一二月、初冬に差し掛かっていた。ビルの谷間を吹き抜ける冷たい風に、丹前は、思わずコートの襟を立てて首をすぼめた。
丹前は、平成二七年七月、二九年余りにわたって務めた検事を退官した。定年まであと一年半ほど残っていたが、体力と気力があるうちに、元々の志望だった弁護士をしようと思ってのことだった。
東京霞が関の法務省中央合同庁舎一九階の最高検察庁ナンバー2の次長室。退職の意向を告げたとき、次長が神妙な顔つきで念押しした。
「後悔はしませんか?」
即座に答える。
「はい、後悔することはありません」
次長の顔を見据えながらきっぱりと答えた。丹前が検事時代、何度も経験してきた場面。被疑者が取調べで検事から
「事実に間違いありませんか?」
と問われて、
「はい、間違いありません」
と答える心境と重ね合わせる。潔いものだった。というより、そう気張って見せたというのが本音だろうか。
丹前は、日本弁護士連合会に弁護士登録された平成二七年九月一日から、神戸のJR三ノ宮駅から徒歩五、六分ほどのビルに小さな一室を借りて弁護士事務所を開いた。