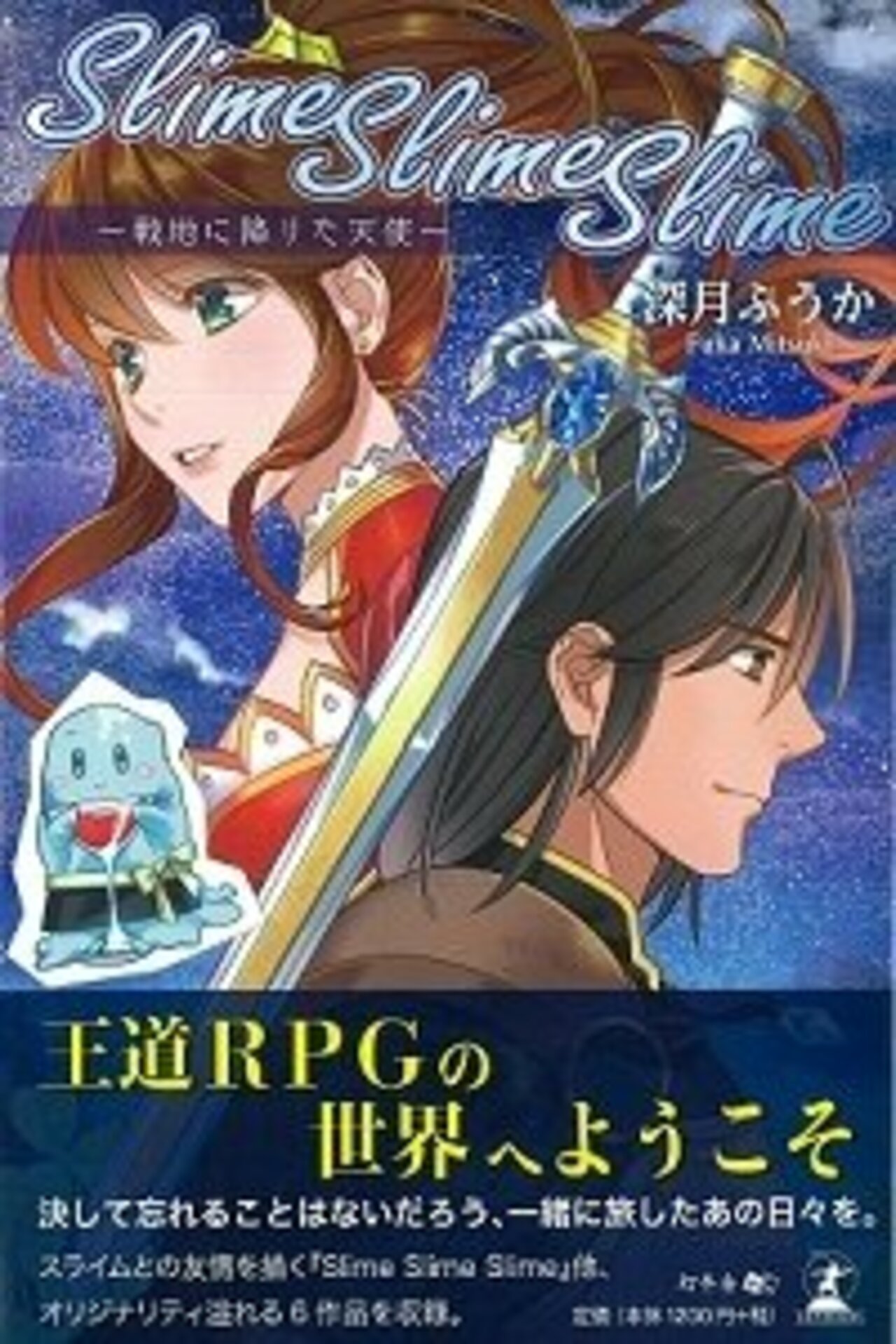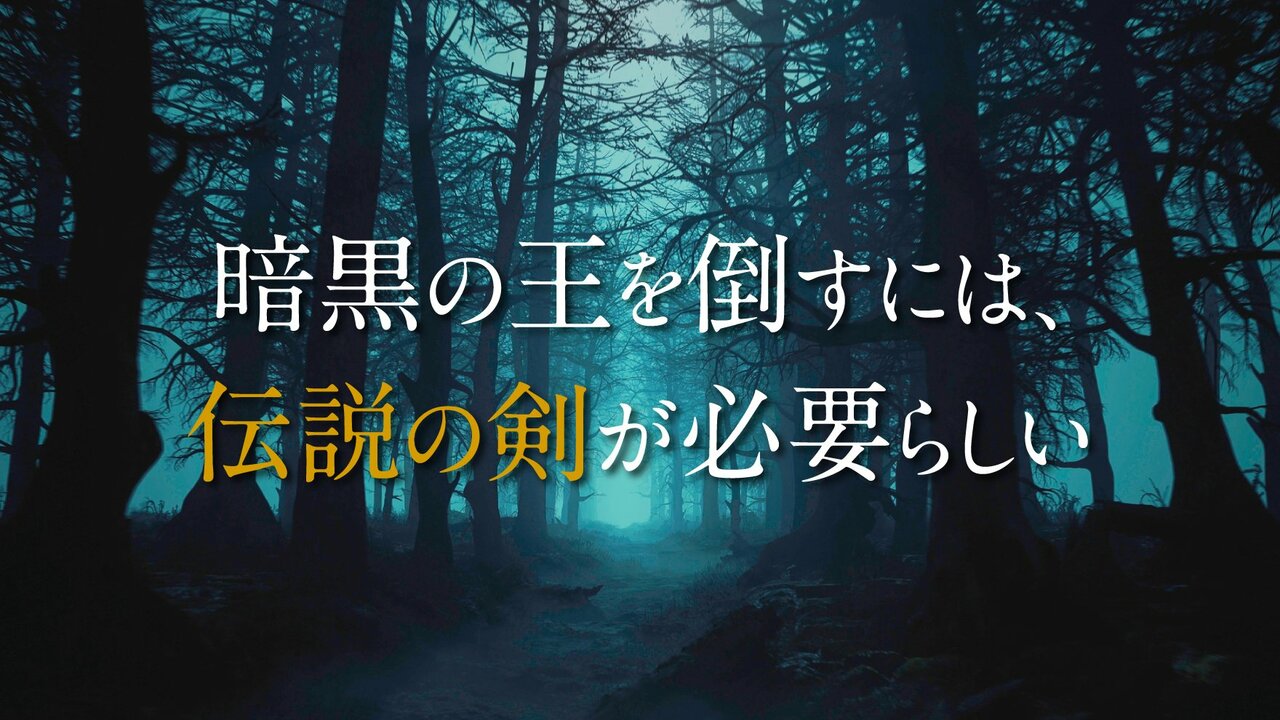警備員達の動きが止まった。会場はにわかに騒がしくなっていった。
すると王は、ミコトをあざ笑うかのように口を開いた。
「ミコト、やはりそなたには私だと分かっていたのか。だが、そんな小さなナイフで私は死にはせん!」
王はそう言ってミコトの腕を振り払おうとしたが、ミコトの力は想像よりもはるかに強く、ビクともしなかった。
「なら王様? この小さくて鋭いナイフで、首の頸動脈を切ったらどうなるかしら? 切れ味を試すおつもり? 間違いなく死ぬわよ! 分かったら、早くタクさんを放しなさい!」
王の顔からサーッと血の気がひいた。これ以上は危険だ! タクはすぐに解放された。
だが実は、この一連の騒ぎには裏があった。全ては王が、自ら仕組んだことだったのだ。
風の噂でミコトが最強女戦士であるということを聞き、どうしても真実を確かめたかったのである。王は二人を王の間へ通すと、重い口を開いた。
「二人には、すまないことをした。言い訳をするつもりはないが、今の世の中は本当におかしい。これを元に戻すのは、ある意味私の役目でもあると思っていたのだ。私には妻と娘がいたが、妻は病で亡くなり娘は何者かにさらわれた。だからなおさら、再び平和が訪れることを願っておる。この城には、古くからの言い伝えがあるのだ。……真の勇者が現れし時、伝説の剣が光を放ち、その者によって引き抜かれると。」
王がミコトを真っすぐに見て言った。
「そなたが、真の勇者ではないかと思ったのだよ。ミコトなら、この世界を救えるかもしれないと。だから、あんなことをしてしまった。だが、やはり私の目に狂いはなかった。ミコト、その伝説の剣は、我が城の宝物庫の中で眠っている。」
ミコトとタクは、伝説の剣がこの城にあると知り、顔を見合わせた。
そして王は、ミコトを自分の近くに呼び寄せると、黄金の見事なナイフを手渡した。そのナイフには、大変美しく大きな真紅のルビーがはめ込まれている。
「王家に古来より伝わるナイフだ。ルビーには、不滅の炎が宿ると言われており、ラトラナジュという別名がある。ルビーを身に着けた戦士は、無敵になるという言い伝えだ。これをミコトにやろう。その小さなナイフよりはいいだろう。」
王は静かに笑っていた。ミコトは、王家のナイフを受け取った。
「そしてもう一つ。」
王の手に、光輝くダイヤモンドのネックレスが乗っていた。
「これも持っているとよい。ダイヤは、誰にも支配されることのない、不屈の精神の象徴とされる石だ。ミコト、まるでそなたのようだな。」
ミコトにネックレスを手渡すと、王はゆっくりと二人に向かって語り始めた。