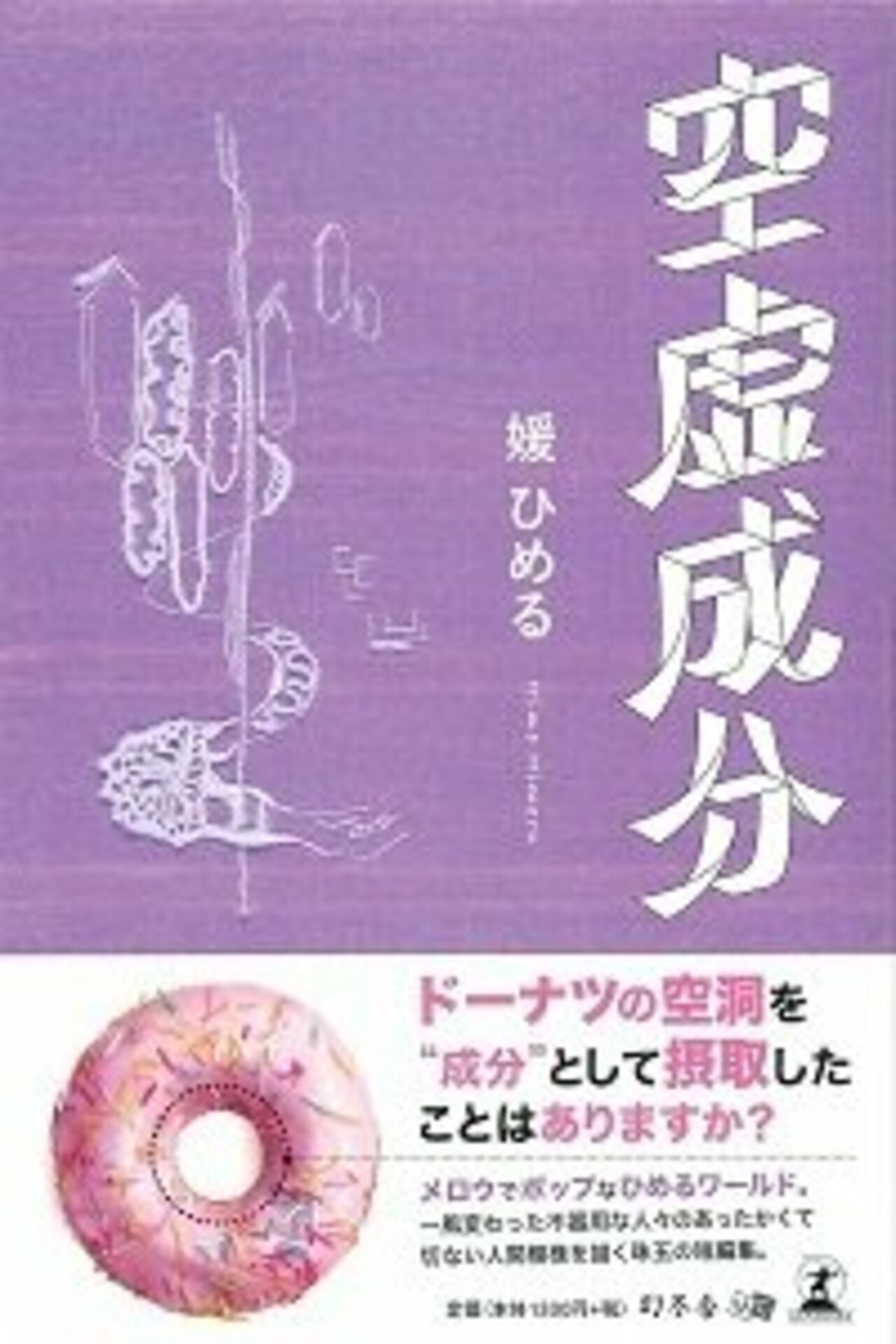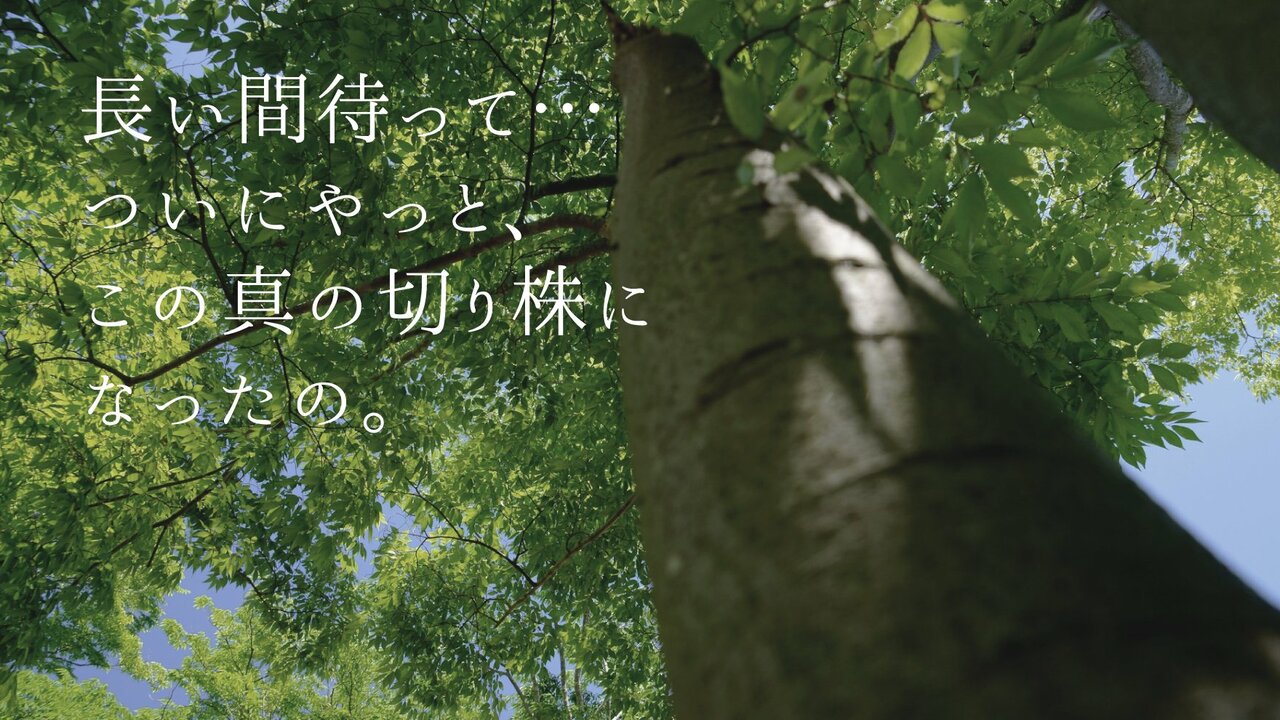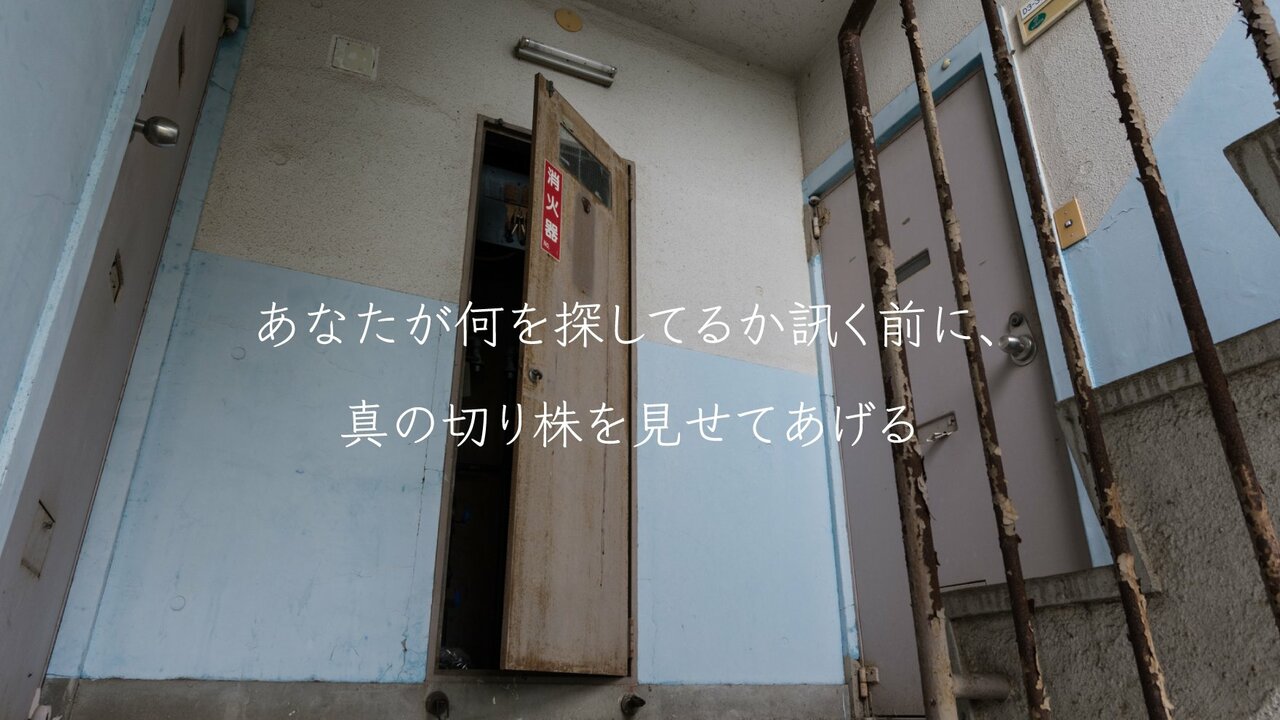洋一はしばらくのあいだ、郷田と書かれた表札の前に立ち尽くしていた。まるで根が生えたように、足を動かすことができない。
ふいに角から現れた車の強いヘッドライトに、やっと我に返った。のろのろと足を動かすと、洋一は元来た道を駅に向かって歩き始めた。
その夜はベッドに入ってからも意識が高ぶって眠れなかった。新宿駅から男を尾行したときのことを、頭が勝手に再現してしまう。瞼を閉じれば、郷田と彫られた表札や巨大な家が浮かんでくる。結局、少しうとうとしただけで朝になってしまった。
ベッドから体を起こした洋一は、あの男が自分の父親であるという確信を固めていた。でも、だからどうというわけではない。何かをしたいわけでもなく、何かをしてほしいわけでもない。父と母は大昔に離婚したのであり、成人した洋一には、幼い頃別れた父などほとんど他人に等しい存在だ。
しかしそれでも考えずにはいられなかった。あの男が自分の父親である、ということを。もし自分の確信が間違っていなければ、あの豪邸には妹も住んでいるはずだ。妹。特に遊んだ覚えもないし、顔だって何も覚えていないけれど。
休みの日に洋一は、東急世田谷線の山下という駅まで歩いた。散歩にはもってこいの、気持ちのいい天気だった。
山下駅から電車に乗り、二駅目の終点、下高井戸で降りる。そこから京王線に乗り換えた。下高井戸から桜上水は一駅だった。思えば洋一の住む経堂から桜上水は、とても近いのだった。頑張れば、歩いても行けるだろう。
明るい日差しの中で見る桜上水の住宅街は、夜見たときとはまったく違っていた。まるで別の街のようだ。途中で、大きな白い犬を連れている老人とすれ違った。身なりの良い老人で、余裕がある空気を感じた。すれ違う人はどの人も、だいたいにおいて似たような感じだった。