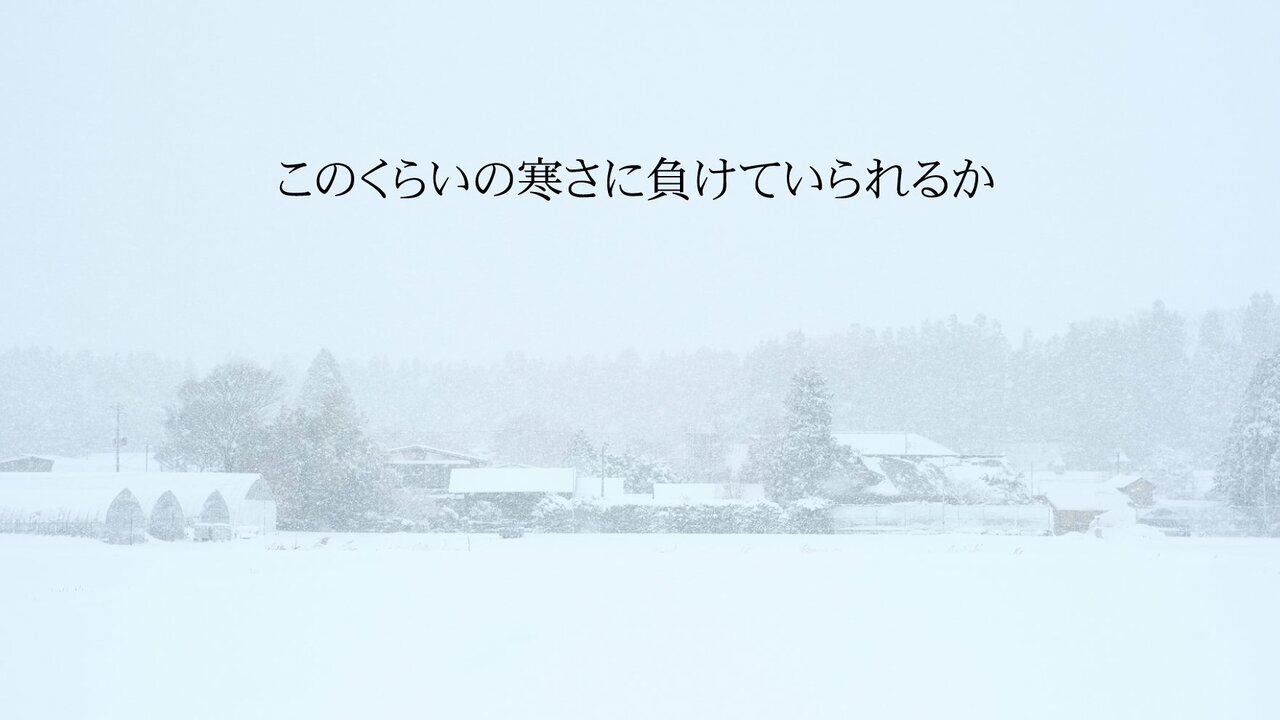第一章 小樽 人生の転機は突然に
ガラス窓に目を転じれば、流れてゆく夜景とつまらなそうな顔をした男が映し出されていた。ふと別れの挨拶を交わしたときの聡子のぼんやりした顔が浮かんできた。車窓を見つめ始めてからあまり時間はかからなかった。いつだったか聡子の顔を「ぼんやりしている」と表現したら「馬鹿言え、あれは潤んでいる瞳なんだよ」と吉越が言ったことがあった。少しにんまりしている自分に気づいた。
高三の春、入学したての初々しい聡子に初めて会った日をはっきり覚えていた。体育館へ通じる廊下で、後輩からアルペンスキーがうまいのでスキー部へ勧誘してほしいと言われ紹介を受けた。口数が少なく幾分影が感じられるようなおとなしい女性であったが、一目見るなり惹かれてしまった。それから今日に至るまで、少しずつではあるが確実に聡子の存在が大きなものになってきている。このままいけば将来をともにするんだろうなという気持ちも徐々に強くなっていた。そんな聡子のことを考えていると、じんわりとした幸福感と合わせてゆったりとした時間の流れが、駅での緊張感や疲れを癒してくれる気がした。加えて、ゴトゴト、ゴトッ。ゴトゴト、ゴトッ。という規則正しいレールを刻む音と、風を切る心地良い騒音が次第に瞼を重くしてゆくのを抑えることはできなかった。
「は、は、は、は……んだども、なんもできなかったでや」
「んだ、おらもよ、そこさ行ったことはねー」
「もっと早くに行ぐべぎだったのよ」
「んだ、んだ。分かってたらなー」
数人のおばさんたちの周りを気にしない大きな話し声で目が覚めた。熟睡している間に青森県に入るあたりを通っていた。