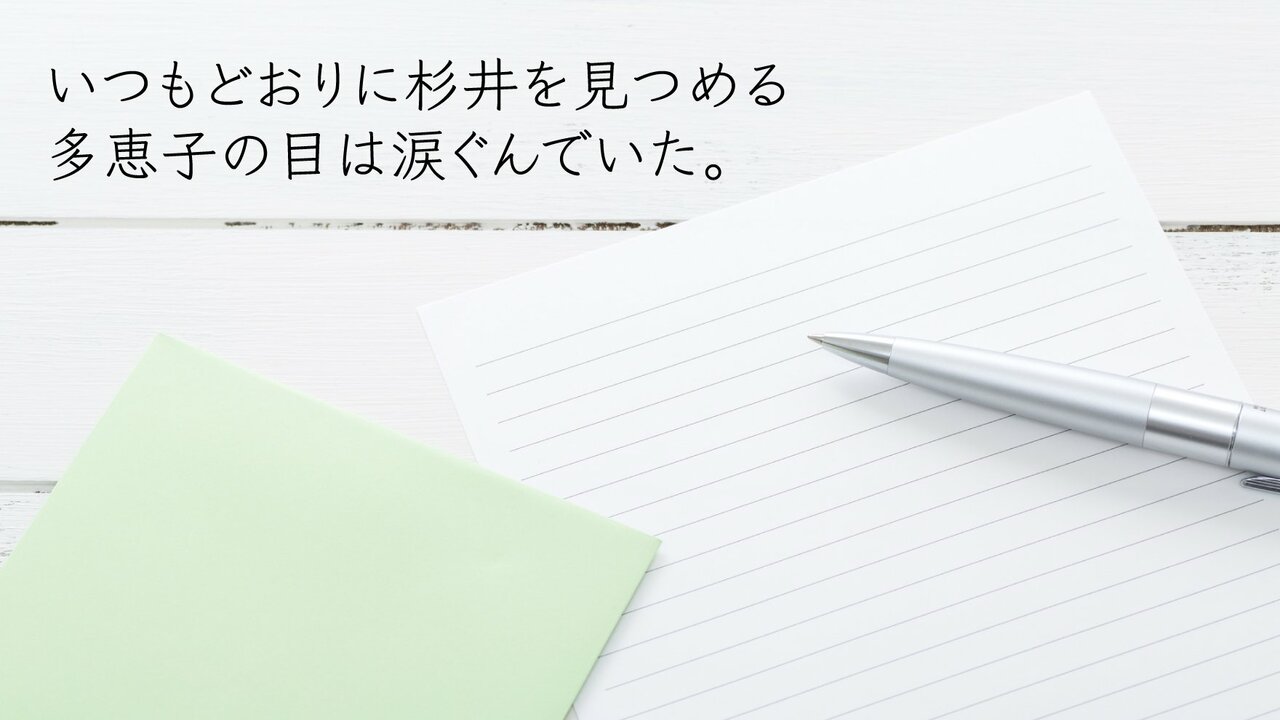ある時、梅木が、
「助手の森高上等兵を抱き込もうと思うのだが、仲間にならないか」
と言ってきた。特に必要性も感じない一方、マイナスになる話でもないと思い、杉井は誘いに応じた。梅木に言われて、勝俣も参加することになった。
日曜日は、馬の手入れのあとは、衛兵や厩舎当番にならない限りは外出は可能であったため、三人は次の日曜日、早速森高を連れ出した。森高は、観測担当の助手で、伊豆の農家出身の無口で陰気な男だった。
一緒に話をしていても決して楽しくなる人間ではなかったが、森高の方にしてみれば、昼食代から喫茶代まですべて杉井ら三人が負担するのであるから、誘いを断る理由はなかった。また、部下から誘いを受けるとそれだけで自分は人望があるという錯覚に陥るのは人間の一般的な傾向ではあるが、森高も例外ではなかった。
四人で外出する際、昼食はその時々でいろいろな食堂に行ったが、喫茶店は必ず広小路裏の小さな店に行くことに決まっていた。ここに弘子という顔立ちの整ったポッチャリ系のウエイトレスがいて、森高のお気に入りだったからである。
この店に行くと、梅木と勝俣は、わざと周囲に聞こえるような声で、
「上等兵殿の指示は本当に分かりやすいですね」
「上等兵殿のような方がいらしてくれたので、自分たちは本当に毎日が楽しいです」
などと、露骨に森高を持ち上げた。歯が浮くようなお世辞というが、杉井はそれを聞いていて実際に自分の奥歯が浮いてくるような感覚を覚えた。
同時に、折角同席しているのだから自分も同じことをしなくてはという一種の義務感が芽生えたが、どう考えても、梅木や勝俣に比べると、この種のことについては技術的に劣位にあると自覚し、二人が何か言うと、
「本当にそのとおりですね」
「自分もそう思います」
などと調子だけ合わせておいた。