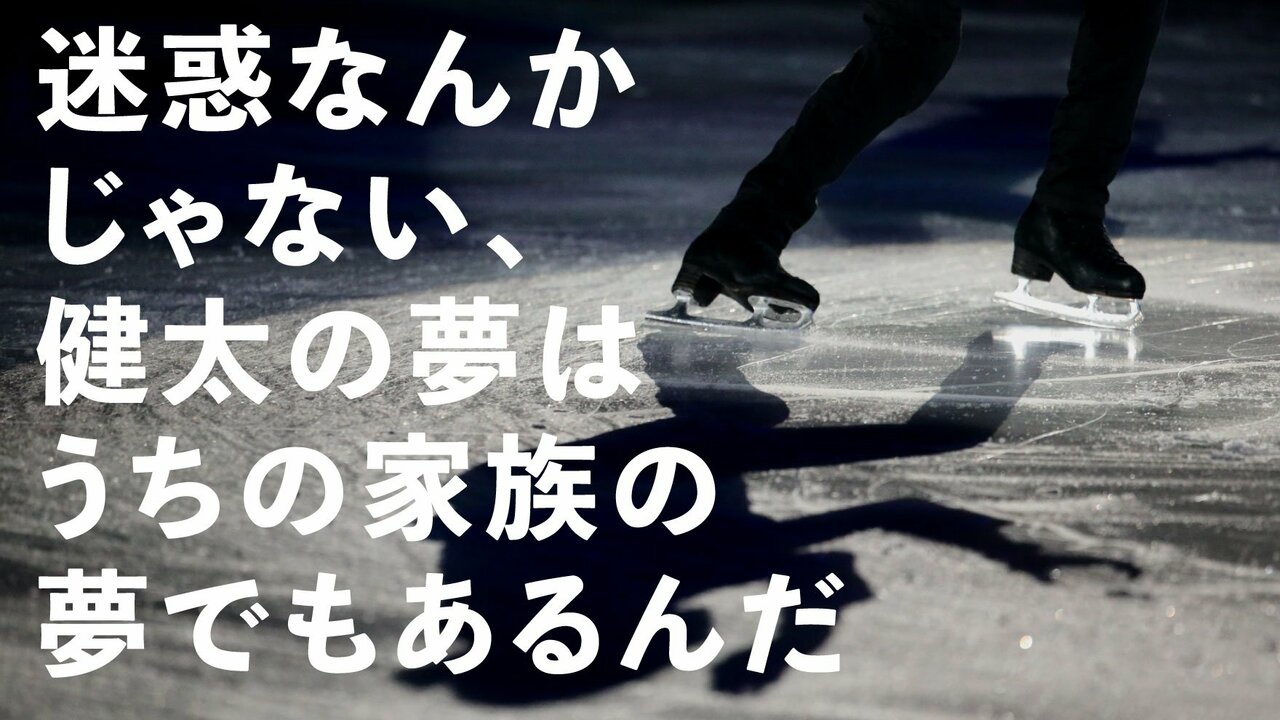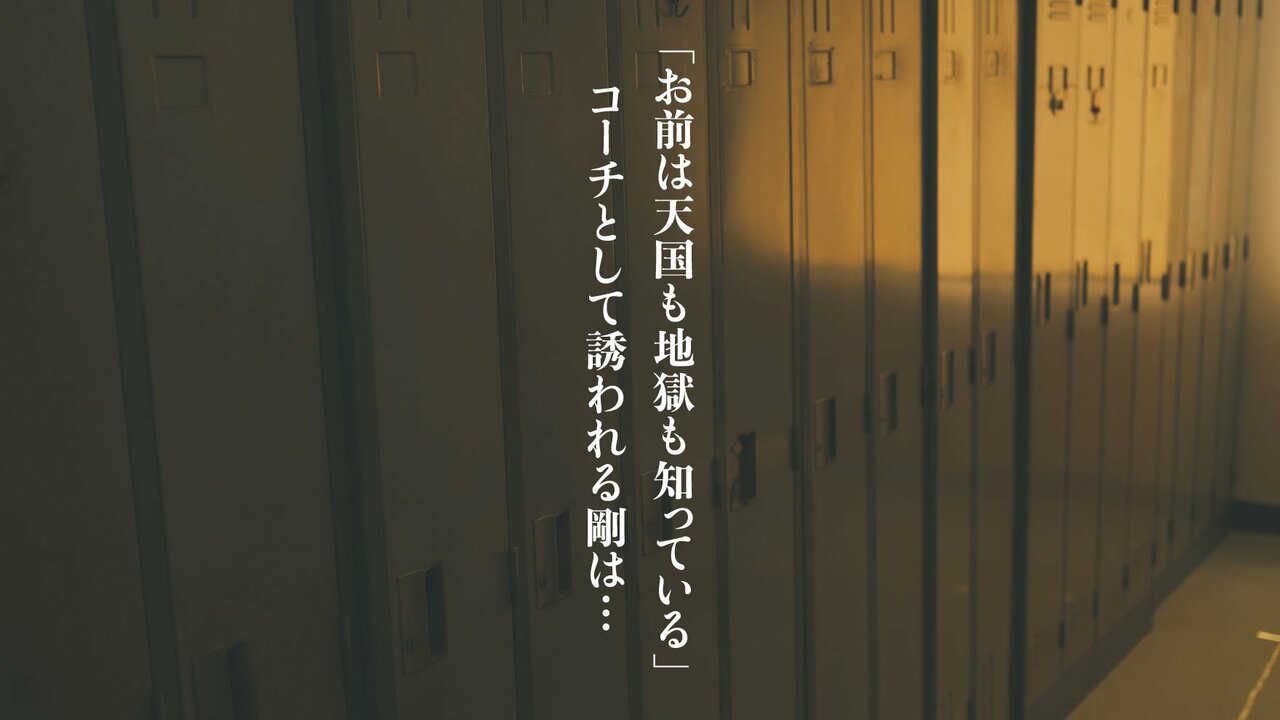ダンボール箱の1つにはオリンピックで優勝した時の表彰台での写真や、たくさんのトロフィーが詰め込まれている。これだけが、彼の過去の栄光の片鱗がみえる唯一のものだ。
携帯電話が鳴る。小さい時から切磋琢磨してスケートをやってきた五十嵐だ。五十嵐は今、連盟強化委員になっている。
「五十嵐、なんだ?」
「剛、あるスポンサーがおまえを迎えてスケート教室をやりたいと言ってる」
「スケート関係の仕事はしたくない」と吐き捨てるように言う剛。
「剛、いつまでそんな生活しているんだ」
「おまえの言ったとおりにコーチもやってみただろ。でも、教えたいと思う選手には出会えなかった。そもそもコーチに向いてないのかもしれない」
「続けてれば心から教えたいと思う選手に出会うよ」
「しばらく放っておいてくれ」
「スケートの仕事したくないって言う割には近くのスケートリンクに行ってるみたいじゃないか?」
「俺は小さい頃からスケートリンクに毎日行ってたんだ。あそこにいると落ちつく。氷の音は俺にとって心地いい音楽なんだ」とはっきり言い切る。
「わかったよ。何かやる気になったらすぐ俺に言えよ」
「わかった」
電話を切る剛。冷蔵庫を開けてビールを取り出す。