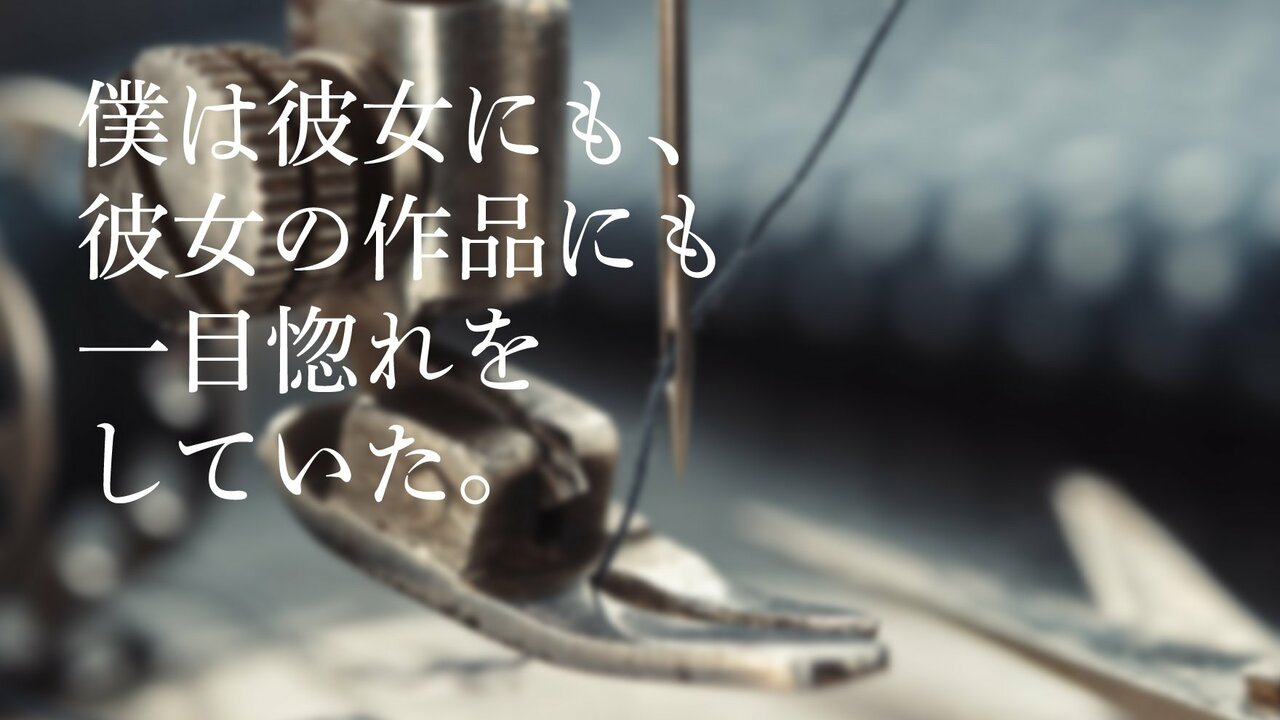生まれてからの記憶がすべてあるけど九九が言えない
「またそれ?」
母はうんざりしながら溜息を吐いた。
「僕は覚えてる。二十三人。あと、小学校の時のクラスメイト出席番号順に一年生から六年生まで全員言える?」
「覚えてるわけないでしょ! そんな下らないこと!」
母は僕の手を放し、学校とマジックアワーの空を背景に感情むき出しで怒鳴った。だからその分だけ僕は落ち着いた声を選んだ。
「僕は覚えてるよ。転校とか転入で多少変わった順番も全部」
「それが何の役に立つっていうのよ! 九九も言えないくせに! いつになったらカタカナのシとツがちゃんと書けるようになるの? ンとソくらいちゃんと書き分けなさいよ! どうしてあなたは、塾に行っても家庭教師をつけても勉強が出来ないのに、下らないことばっかり覚えてるの!」
僕はその理由を知っていた。でも、それを両親に言うと虚言癖扱いされたことがあった。悲しくなった六歳だった僕は、思い出の記憶力の異常な良さをそれからは口にしなくなった。仕方がなく、たまに過去をこんな風に語ってみるけど、やっぱり信じてはもらえない。
だからもう諦めている。九九がちゃんと言えれば違うのかもしれないけど、どうしてもあの表がぼやけて見えて、記憶が出来ないし、声に出しても「さんしじゅうし」と、惜しいことを言っているらしい。
生まれた瞬間からの思い出の記憶が全部あるけど、その代償なのか勉強や集団行動になじめない。授業を聞いていても、先生がどんな服装だったとか、前の席の子が消しカスを集めてまた消しゴムとして使っていたとか、そんなことは覚えているのに肝心な授業内容はほとんど記憶されない。