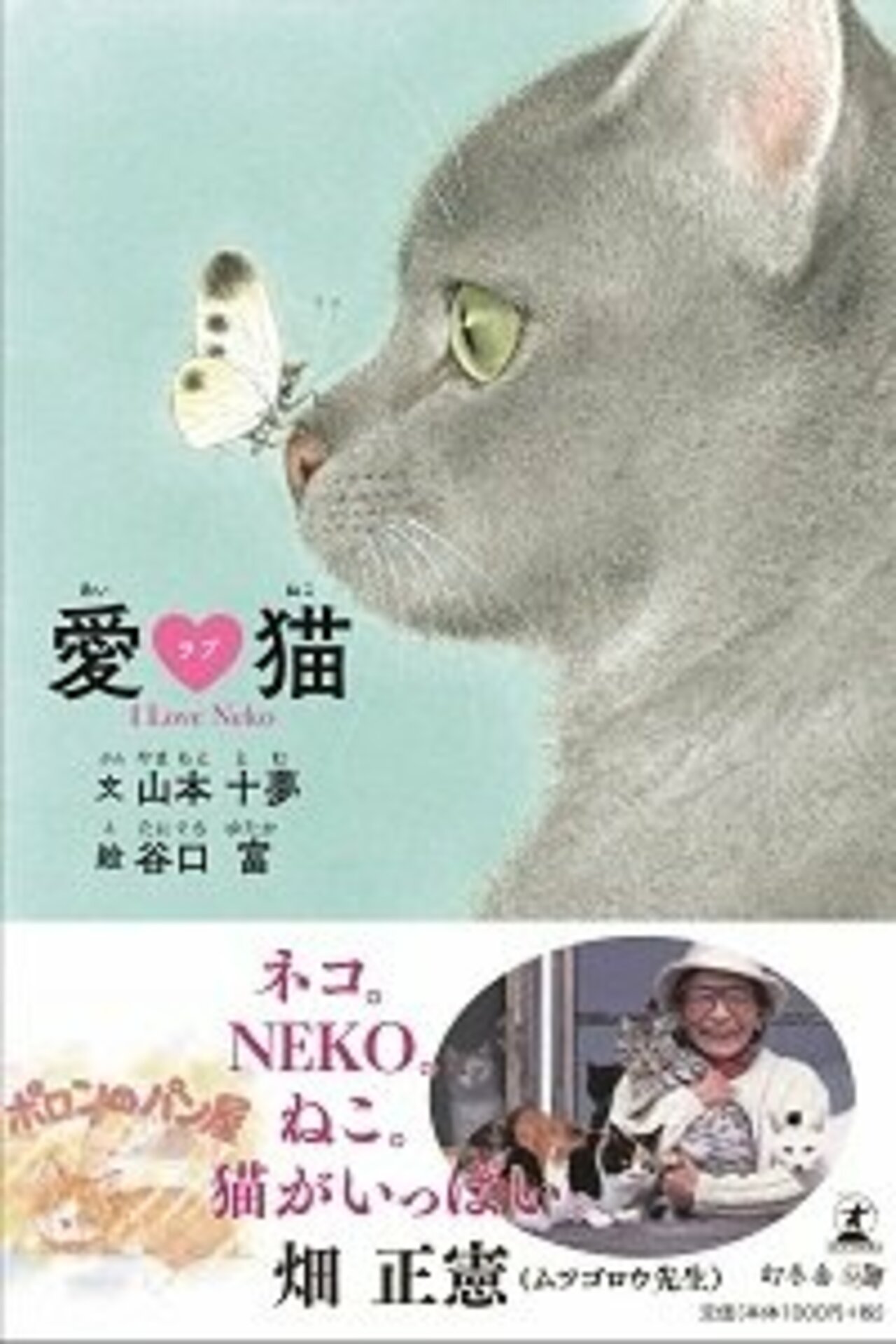ぼくの家族
「ねぇ、このごろ、ゲンキのいたずら半端じゃないわね。どうしたらいいかしら?」
「そうだな。このテーブルの脚もかじられて、だんだん細くなっていくし。そのうちテーブル、かたむくんじゃないか」
「私たちがいないと、いたずらが激しくなるわ。ティッシュを部屋じゅうにばらまいたり、クッションの中の綿を取り出したり。そうそう、この前なんか、私のお気に入りの靴までかじって、ちらかしてたわよね」
ぼくもティッシュをばらまいて遊んだり、クッションをかじったり。ゲンキと一緒にいたずらを楽しむ。でも幸いなことに、おとんも、おかんも、ぜんぶゲンキのしわざだと決めつけている。これも、さんぽに行けない嫉妬の腹いせ。

「そういえば、そろそろ去勢手術の時期かもな」
「そうね。少しはおとなしくなるかも」
数日後、獣医さんのところからゲンキが帰ってきた。いつもとようすがちがって元気がない。傷口が痛いのか、じっとしていておとなしい。

ぼくは心配になって、ゲンキに鼻をちゅんちゅんとくっつけて、体をすり寄せてやった。ゲンキはこれがよほどうれしかったのか、ぼくの体をなめはじめた。この日をさかいに、ぼくとゲンキの愛と友情のきずながふかまる。

数日後、おとんは、いつもよりもあわただしく家を出た。お得意様に朝イチで会社へ来ていただき、プレゼンテーションをする約束があったのだ。