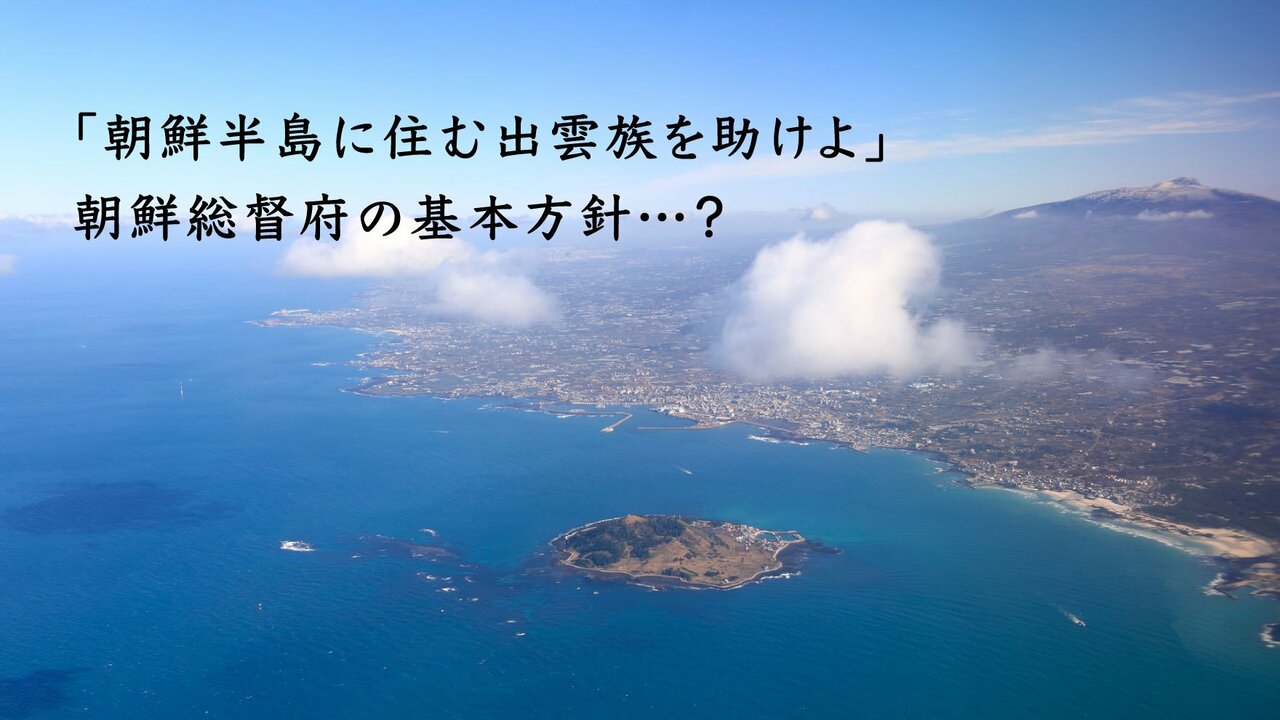これは、描かれている羽衣により、それを身に着け、ここより上は天(景福宮)へと至る(天宮の皇帝に見守られて政を行う)という深い意味も込めていました。
「羽衣」は、天女のみが織れるもの、すなわち、機織り姫によって織られるものであり、題材となった朝鮮の伝説では、羽衣を隠された天女と樵(きこり)は結婚するものの、三人の子供をなしたのちに羽衣を見つけると、再び天へと帰ってしまい、樵は三人の子供たちとともにあとを追って天へと上り、そこで暮らしたという結末になっていました。
ここにも、愛し合うものが一度別れて再び出会うという「七夕伝説」が取り入れてあったのです。
朝鮮半島が日本領のまま終わった表層だけを見て、明治40年(1907年)の訪韓のなかで李王垠殿下と親しく交わられ、帰国後に、韓国語を自ら学ばれた大正天皇、留学中の李王垠殿下を気遣われていた明治天皇の大御心を無視し、大東亜戦争(太平洋戦争)終了から今日まで、現地にいて作業に当たった日本人やその家族に、確認を取ることなく考察されたものでは、贅を尽くした施設が、植民地支配を行った朝鮮総督府や、軍人から選ばれていた朝鮮総督の権威付けのために建設した、または、李王家の権威を貶めるために、景福宮が見えなくなるように、正面に建設したかのような説明がされています。
しかし、李王垠殿下の高位の姫君との婚約発表と同じ大正5年(1916年)に、景福宮敷地内に建設が開始された意味も含めて、この朝鮮総督府新庁舎も、京城駅、朝鮮神宮と同様に、近い将来始まるであろう韓国皇帝の新政のために用意されたものでした。だからこそ、特別な予算を厳しい日本の財政のなかからやりくりして捻出してまでも、朝鮮半島の産物を取り込んだ贅沢な庁舎に仕上げたのです。