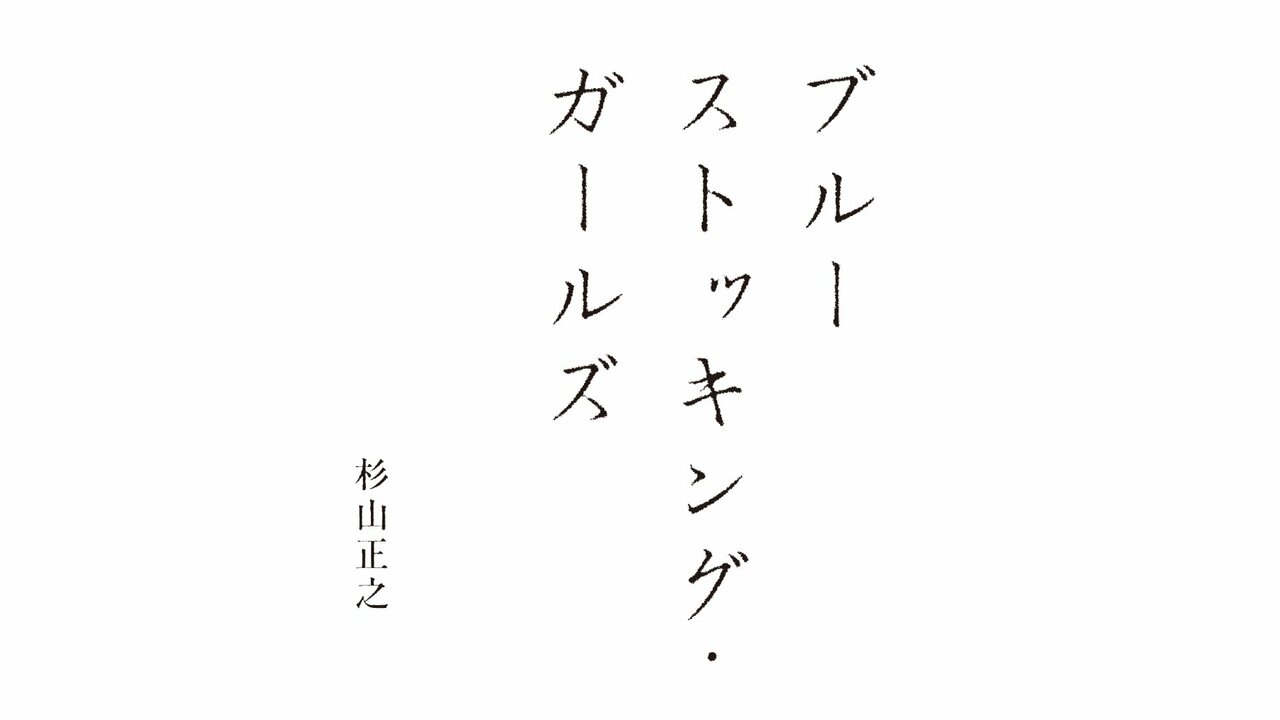第2作『人形』
「おじさん」。突然、鴇子の明るい声がした。彼女は黒い小さな招き猫を大事に抱えていた。ぼくは不思議な緊張感から解放され、安堵した。
「この猫、かわいいね。もしかして江戸時代?」
「はい。安政の頃だと思いますが」
「ホント! やっぱり、私って目利きよね」
「左様で…」
「いくらですか」
「五百円です」
「うっそー。だからこの店って好き」
鴇子は紺のデニム地の財布から、小さくたたんだ五百円札を取り出して主人に渡した。
主人は招き猫を丁寧に英字新聞でくるんだ。
「君も何か見つけた?」
「いや、べつに」。ぼくはあの人形に見入っていた。
鴇子は気付かず、招き猫のウンチクを偉そうに主人に語っている。
それを感じたのは唐突なことだった。あの人形が何かを言おうとしていることが、ぼくには分かった。
それは、確信に近いことだった。でも、その根拠はない。そして「何か」という以上のことも分からない。
「何してるの? 帰るよ」
鴇子の声で、ぼくは現実に引き戻された。
ぼくは新しいことに向かって、積極的に働きかけていくタイプではない。いつもいつも英二や鴇子に引きずられるようにして新しいことを発見する。かと言ってその発見に、べつに心を動かされるわけではない。笑顔で応えるものの、本当に楽しんでいるわけじゃない。
そんなぼくを見透かして、口の悪い友達は「冷めている」と言うし「ネクラ」とも言う。それがぼくに対する妥当な評価なのかも知れない。ぼくはそれを否定するわけでもなく、ましてや反論して怒るわけでもなく「そんなものかな」と思っている。
プロ野球の話題も、アイドルの話題も、ロックの話題も、VANとかいうブランドの洋服の話題も、その話題にのめり込むでもなく、適当に話を合わせて、その輪の中でぼくは笑っている。もっとも、みんな本当にこんな話題に興味を持っているのだろうか、と疑問にも思う。