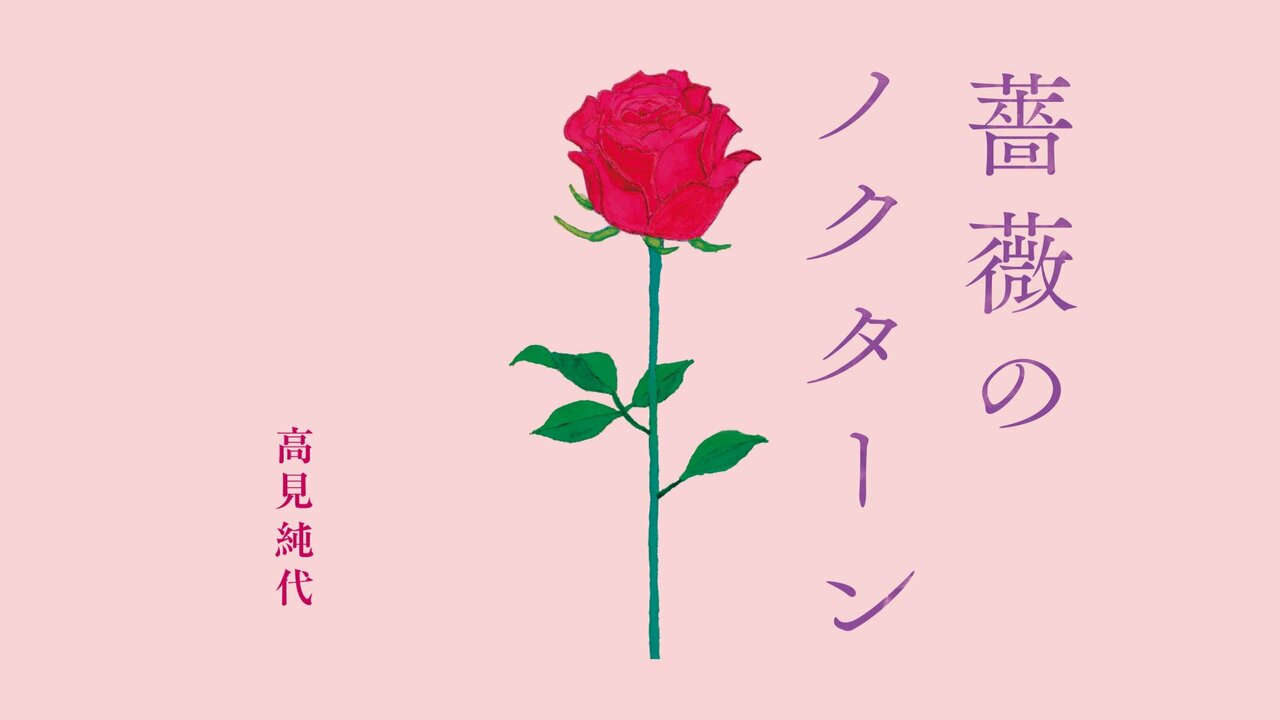辛く長かった夏が過ぎ、澄世は四十歳になった。両脇の傷のテーピングも、T先生に、もう貼らなくていいと言われ、ホッとし、落ち着いた。
十一月末、D先生のカウンセリングに通院し、病棟へ行くと、恵子はいなかった。詰め所で、看護師長に聞くと、つい少し前に亡くなったと言われた。
澄世は涙が溢れ出た。看護師長があわてて、澄世を空いていたミーティングルームへ連れ込んだ。聞くと、娘さんも来られ、静かに安らかに旅立たれたとの事だった。また、恵子は生前に献体を申し出ており、そうしたと言う事だった。
澄世は胸にぽっかり穴が空いたような気がした。そして、尚更、遺言のように恵子が言った言葉が重くのしかかった。
相変わらず、体調は良くなかったが、それより、心の不安が大きくなっていた。婦人科など、行った事がなかったし、行きたくもなかったが、今やハッキリさせるしかなかった。
不安なまま年を越すのは嫌だと思い、澄世はやっと十二月にK病院の婦人科へ行った。十二月十八日(月)、受付で、子宮癌の検査を、特に子宮体癌の検査もお願いしたいと言った。
問診票が渡され、乳癌を切った事や生理が順調な事などを記入し、渡した。診てくれるのは部長のK先生だと言われ、その診察室の前で待った。時間が長く感じられた。一人、二人、と順番に呼ばれ、入り、出てきた。年輩の婦人もいれば、妊婦もいた。
しばらくして、ドアの向こうから声がした。
「楯見さん」
「はい」
澄世は引き戸を開け、中へ入った。髪をきっちり七・三に分けた五十五、六歳の医者らしい落ち着いた雰囲気のK先生が机の向こうに座っていた。「どうぞ」と促され、緊張している澄世は、おどおどと椅子に腰かけた。