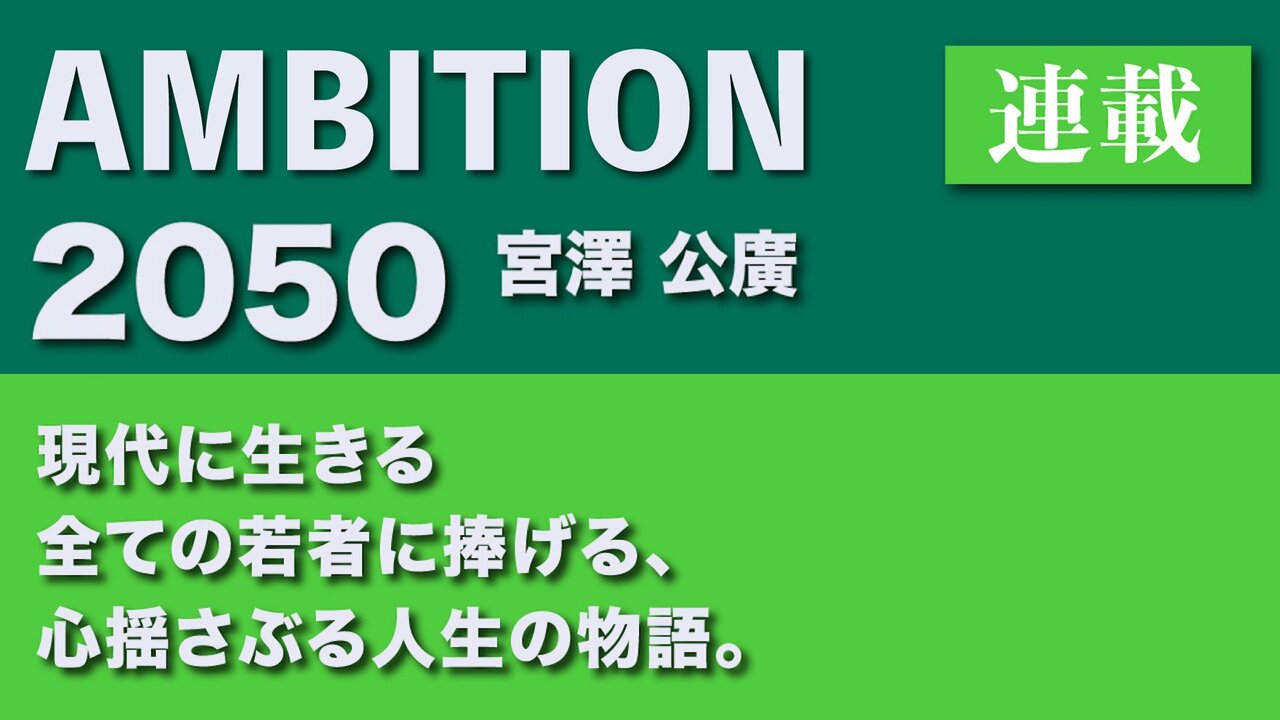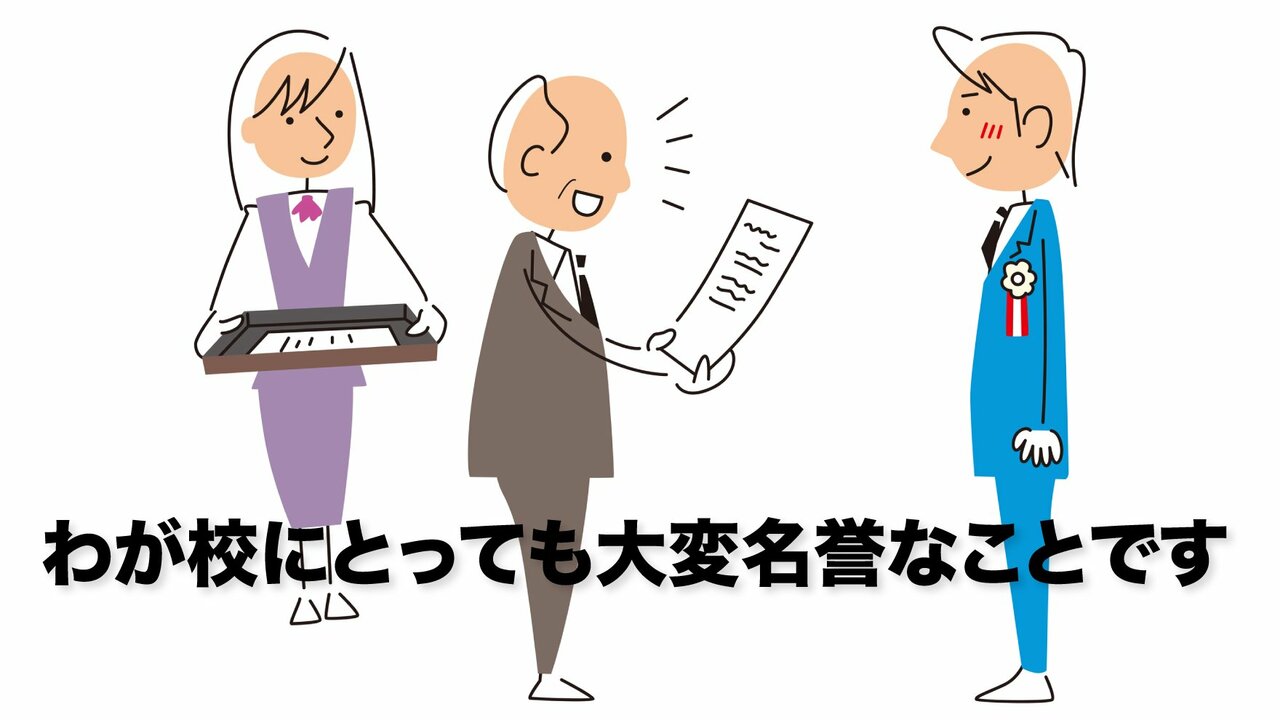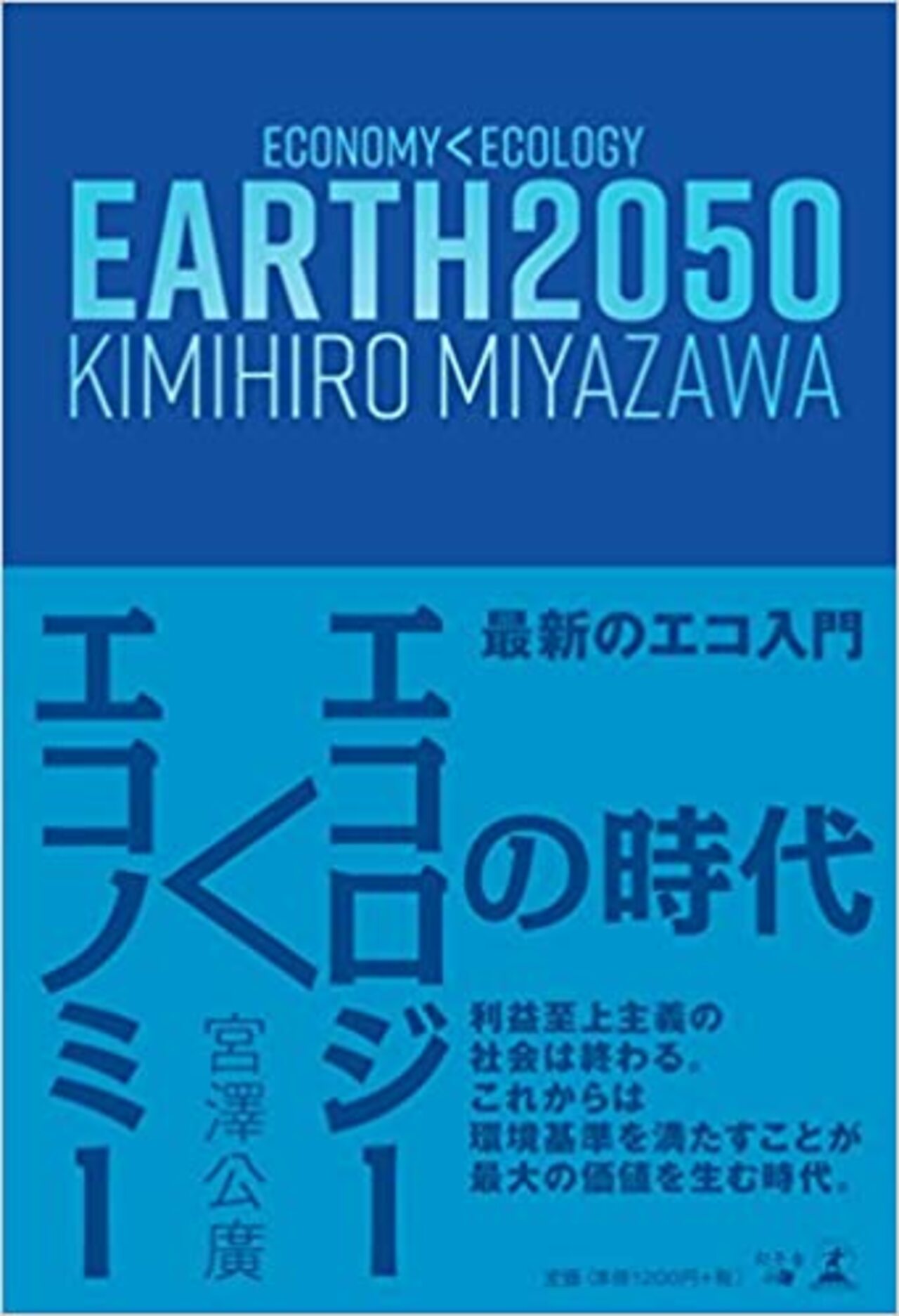第一章 道 程
【2】
宮神が決めつつあった進路とは、カナダへの留学だった。話は、高校三年生に進級した四月にさかのぼる。
前年の夏休みに自由課題に提出した宮神の研究(ハイマツとホシガラスに関する研究だ)が、県のコンクールで優秀賞を受賞して、全国大会にエントリーされた。それは二年越しの取り組みで、山岳に数十回も通いつめて仕上げた渾身のレポートだった。
論文は県庁に一週間ほど掲示され、表彰状と記念品が学校に送られてきただけだったし、本選は主催のお偉いさん達が審査するもので、宮神自身がどこかへ出向いて説明したり答えたりということはなかった。そのため、緊張や気持ちの高ぶりといったものはなく、担任から「選ばれているぞ」と教えてもらっただけだった。
ところが、四月のある日、担任の教師から校内放送で職員室に呼び出された。何ごとかと思って行ってみると、普段は鉄仮面の異名を取る担任に笑顔で迎えられ、用件を伝えられないまま、奥にある校長室へと案内された。扉を二度ノックして「入ります!」と声をかけた担任は一礼してから先に校長室へ入り、次に宮神を招き入れた。
「三年B組の宮神です」
宮神が校長と直接話をしたのは、入学以来初めてだった。校長は老眼鏡を外しながら席を立って、宮神に向かってこう言った。
「宮神くん、おめでとう。君の研究が全国高校生課題研究コンクールで優秀賞を受賞したと、先ほど知らせがあったんだよ。わが校にとっても大変名誉なことです。明日の朝礼で紹介しますから、あいさつを考えておいてくださいね。それから、来月の連休に東京で表彰式があります。私も同行しますから、予定をあけておくように」
このことで宮神は一躍、時の人になった。学校内ばかりではない。受賞のニュースは地方紙にも写真付きで掲載され、地元テレビ局の朝の情報番組でも取り上げられた。新聞記事は小さいものだったしテレビ放送は早朝だったので、気づいている人はいないだろうと高をくくっていたのだが、想像をはるかに超える反響だった。
ハイマツとホシガラスの関係は、宮神が趣味の登山の中で偶然に見つけたテーマだった。子どもの頃から友だちと自然の中を駆け回っていた宮神だったが、中学生になると登山を始めて夢中になった。
宮神の住む街は、八ヶ岳、甲斐駒ヶ岳、北岳、鳳凰三山(地蔵岳・観音岳・薬師岳)など三千メートル級の山々の麓である。好奇心旺盛で体力のありあまっている宮神が、いつまでも里山やハイキング程度で登れる近場の山々で満足するはずがなかった。
とはいえ、頂上を制覇するような登山をしたわけではない。宮神の心を捉えたのは、高山植物の世界だった。厳しい自然環境の中で懸命に根を張って、必死に命をつなごうとする木々や草花に愛おしさを感じていた。
高山植物に囲まれていると、日常の些細な悩みごと(だがその当時の当人にとっては決して小さくない問題だ)などすっかり忘れ、身も心もリフレッシュする。そうした力が植物にはあると確信していた。
中でも宮神の心を捉えたのが、ハイマツだった。ハイマツは、シベリア、カムチャッカ、中国北東部、朝鮮半島と日本(南アルプスの光岳以北)にかけての寒冷地に分布する、マツ科マツ属の常緑針葉樹だ。山の頂上付近、ほとんど養分などなさそうなゴツゴツとした岩だらけの地面でも、たくましく根を張る。
どんなに日差しが照りつけようが、強風に煽られようが、豪雪に埋もれようが立派に耐える。幹はカラカラに乾いているように見えて、強い。腕っぷしの強さに自信がある宮神がどんなに力を入れても抜けず、折れず、曲がらない。
宮沢賢治の「雨ニモ負ケズ」の詩に、自分もこうありたいと感銘を受ける文学青年は多いが、同じように宮神はハイマツの逞しさに憧れに近い感情を抱いた。
マツ科マツ属の植物は、秋になると毬果、いわゆる松ぼっくりができる。これは種子を格納したカプセルのようなもので、成熟するとかさが開いて中の種子が落ちる仕組みになっている。公園などでよく見るアカマツやクロマツの種子は羽根が付いていて、風を受けて宙を飛び、子孫を増やしていく。
ところがハイマツの種子は、アサガオの種のようにボテッとしていて飛び散らない。では、どうやって子孫を残していくかというと、ホシガラスという白黒斑の野鳥が冬の間の食糧として運んでいくのだ。宮神は晩秋の乗鞍岳でせっせと松ぼっくりを運ぶホシガラスを見て両者の共存共栄に気づき、分布と生態を詳細なレポートにまとめたのだった。