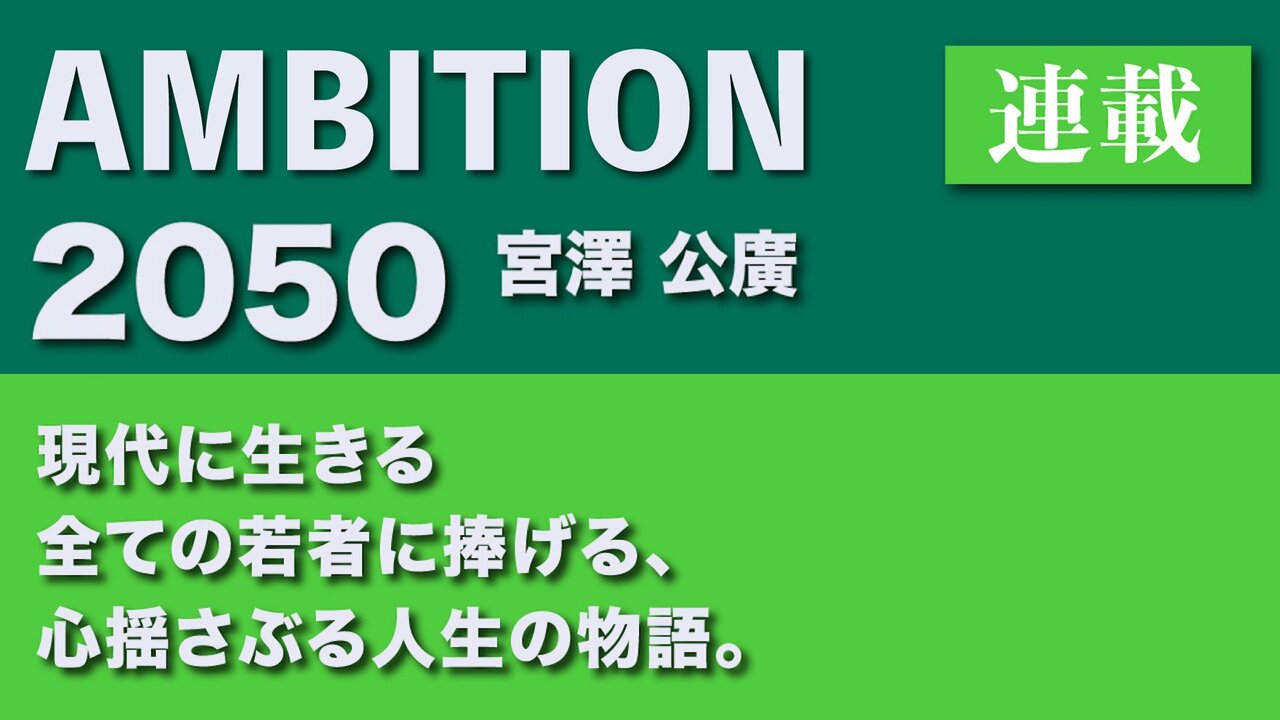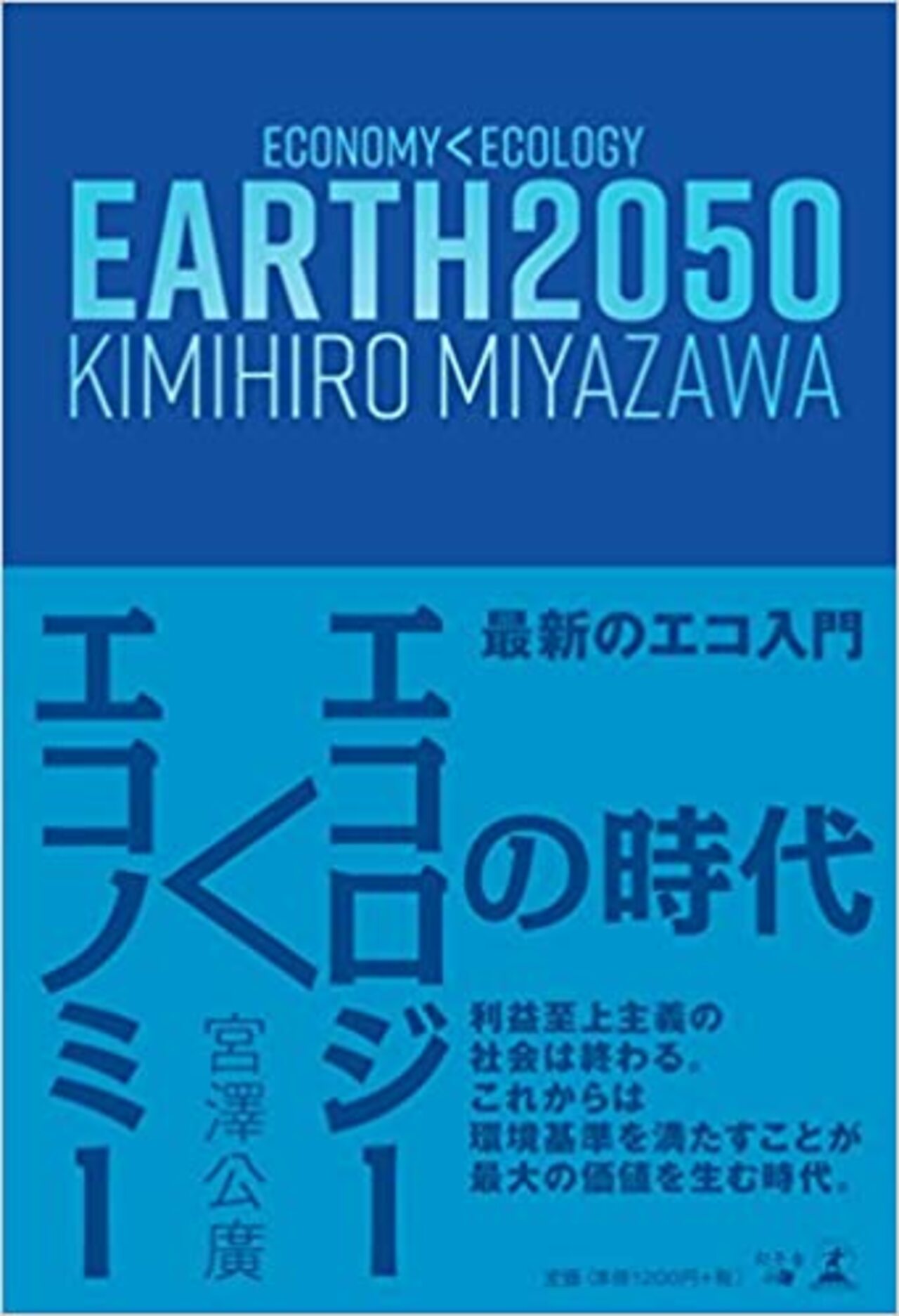第一章 道 程
【1】
遠くでまたカラスが鳴いた。宮神は目を開けると、天井を見ながら深く大きなため息をついた。そして、高村光太郎の『道程』を、声に出してつぶやいた。
僕の前に道はない
僕の後ろに道は出来る
ああ自然よ
父よ
僕を一人立ちにさせた廣大な父よ
僕から目を離さないで守る事をせよ
常に父の気魄を僕に充たせよ
この遠い道程のため
この遠い道程のため
あらためて静寂の中で耳にすると、自分の声はいつもの自分の声でないような感じがした。
この詩を覚えたのは、中学一年生の春だった。国語の授業でいくつかの詩を暗記させられたのだ。ほかの詩はもうすっかり忘れてしまったが、なぜかこれだけは感じ入るところがあって、ずっと心に残っていた。
当初はこの詩から、自分が人生の開拓者になってやるのだという気概に満ちた勇ましさや迫力を感じたものだ。もしかしたら、当時の国語の教師にそういう解釈を教えられたのかもしれない。だが、いまは少し違った感情を持っている。
この詩の「僕」は、先の見えない真っ暗闇の未来に一歩を踏み出さねばならない不安を感じているのではないか。
翌週に高校卒業後の進路について、意思表明をしなければならない三者面談がある。ここのところ、どの道を選ぶべきかで頭がはちきれそうになっている宮神にとって、この詩がいまほど心に迫ったことはない。苦悩の中心にある二つのキーワード、「自然」と「父」が織り込まれていることも、まさに今の心境にぴったりだった。
「自然よ、父よ……か」
そうひとりごとを言って、宮神はまたひとつ大きなため息をついた。宮神が悩んでいたのは、自身の進路のことだった。自分が将来どんな道に進みたいのか明確に定まっている高校生など、ほんの一握りもいやしない。好きなことや夢中になれることはあっても、それがどう将来につながっているのか、まだ社会に出たことのない若者にはわかりようがない。
いや、好きなことや夢中になれることがあるなら、それは幸せなことかもしれない。宮神の友人たちの多くは、自分が何に興味があるのかすらわからず悩んでいる。自分には何ができるのか、何をするために生まれてきたのか。そういうことを懸命になって考え、見つけようとしているのだ。
必死にもがいているうちに、偶然、答えに繫がっていそうな細い糸が指先に触れる。それはまさに希望の一糸だ。糸に触れるきっかけはスポーツかもしれないし、芸術作品に触れることかもしれない。偶然に手にした一冊の本が、未来に通じる道を指し示してくれることもある。あるいは友や師との出会いである場合も多い。
結婚相手とは生まれたときから小指と小指が赤い糸で繫がっているという言い伝えがあるが、親友や恩師とも天職とも何色かの糸で繫がっているのではないだろうか。それは言わば運命の糸である。
運命の糸は複雑に絡まり、どこに繫がっているのかまるで見えない。そこを丁寧に解きながら伝っていくと、糸はやがて紐になり、紐は縄になり、だんだんと手応えを増していく。そうしてあるところで、それが自分の進むべき道に繫がっている――そう信じて若者は社会に飛び込んでいくのだ。
宮神もまた偶然に見つけた糸口を手繰り寄せ、縄を摑みかけたところだった。しかし、それは父によってあっけなく奪われてしまった。この一年でようやく答えらしきものを見つけられたと思ったのに、振り出しに戻ってしまった。
「甲一! 甲一!」
母親の声が聞こえた。まだ夕飯の時間には早いし、級友から電話があっても自室にいるときは声を掛けないでいてくれる。宮神は立ち上がって窓から顔を出した。母は縁側から宮神を呼んでいた。
「清川さんが訪ねてきたよ」
「おおコウか! わかった、いま行くよ」
先ほどまで曇っていた宮神の心がパッと晴れやかになった。内側のガラス戸を閉めると急峻な階段を後ろ向きに降り、入口に並べてあったサンダルをつっかけて庭を横切り、清川の待つ玄関口の方へ走っていった。