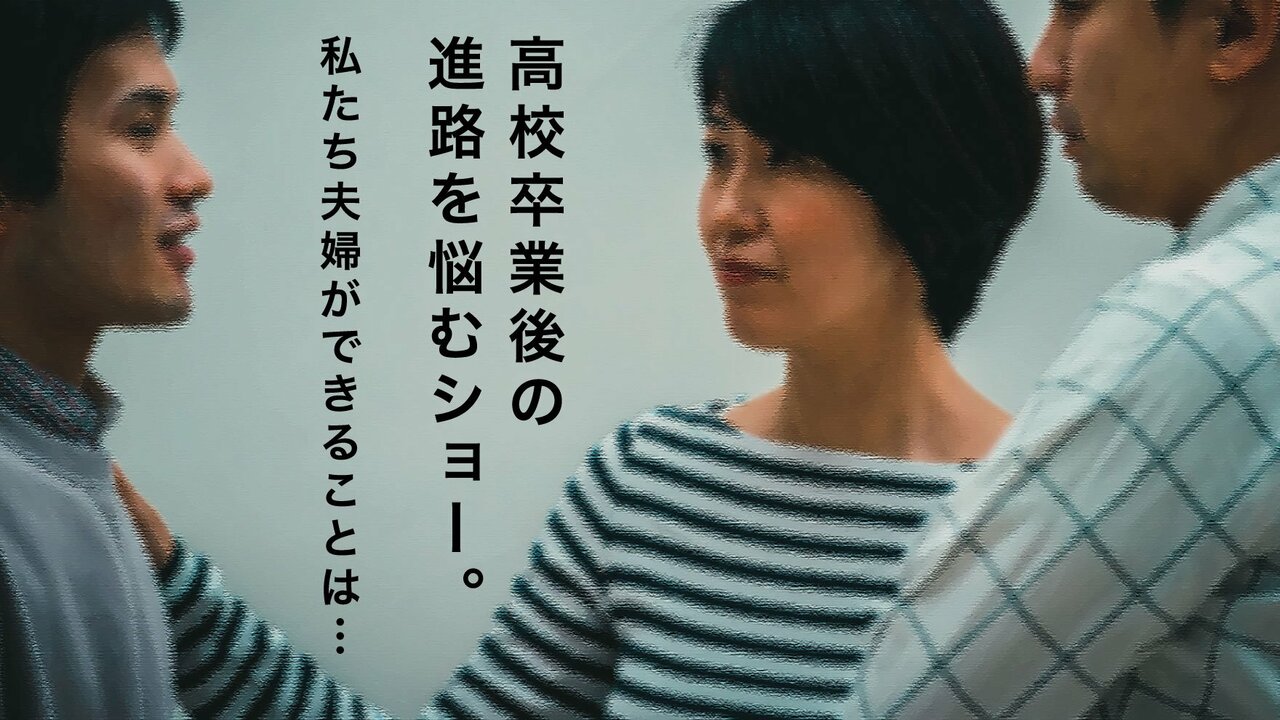第一章 ショーが居なくなった!
車外を見ると、真っ赤な夕日も沈みかけている。もう既に午後の四時を回った。
苛々しているうちに乗換駅であるJR船橋駅に到着した。私はすぐに、駅構内に設置してある公衆電話に飛びつき電話した。しかし、誰も出ない。
「ルルルー。ルルルー」という呼び出し音が虚しく聞こえてくる。妻は外で探しているのだろう。二、三度電話を掛け直したが結果は同じであった。
私は気持ちを切り替え、電車に乗るため一刻も早く東武線乗り場に向かった。ギリギリで、発車真近の電車に飛び乗ることができた。
空席をみつけ席に座るとホッと一息ついた。ふと窓の外を見ると、夕日が地平線の中に吸い込まれ夕闇が迫っていた。
最寄駅である東武線K駅に着いた。足早に家路を急ぐ。県道を越え、児童公園を横切り左手に真っすぐ行く。
すると、とある電車の遮断機がある。それを越え、右手に行った所が私の家である。
遮断機の手前から我が家のマンションが見えるが、明かりは点いていない。誰もいないようだ。いつもだったら、ピンク色のカーテンが明るく光っているので誰か居ればすぐ分かる。
私たちが結婚したのは三年前。私が大学四年、妻が大学一年の時から付き合っていたので、かれこれ十二、三年位の付き合いだ。
妻とは大学のサークル・映画研究会で知り合い、映画、飲み会等一緒に行くようになり、いつの間にか付き合うようになった。しばらくすると、当時流行っていた曲、「神田川」や、映画「同棲時代」に影響されてか分からないが、二人は同棲するようになっていた。両親の手前、同棲もだらだら続けている訳にもいかず、妻が卒業して数年後に結婚した。