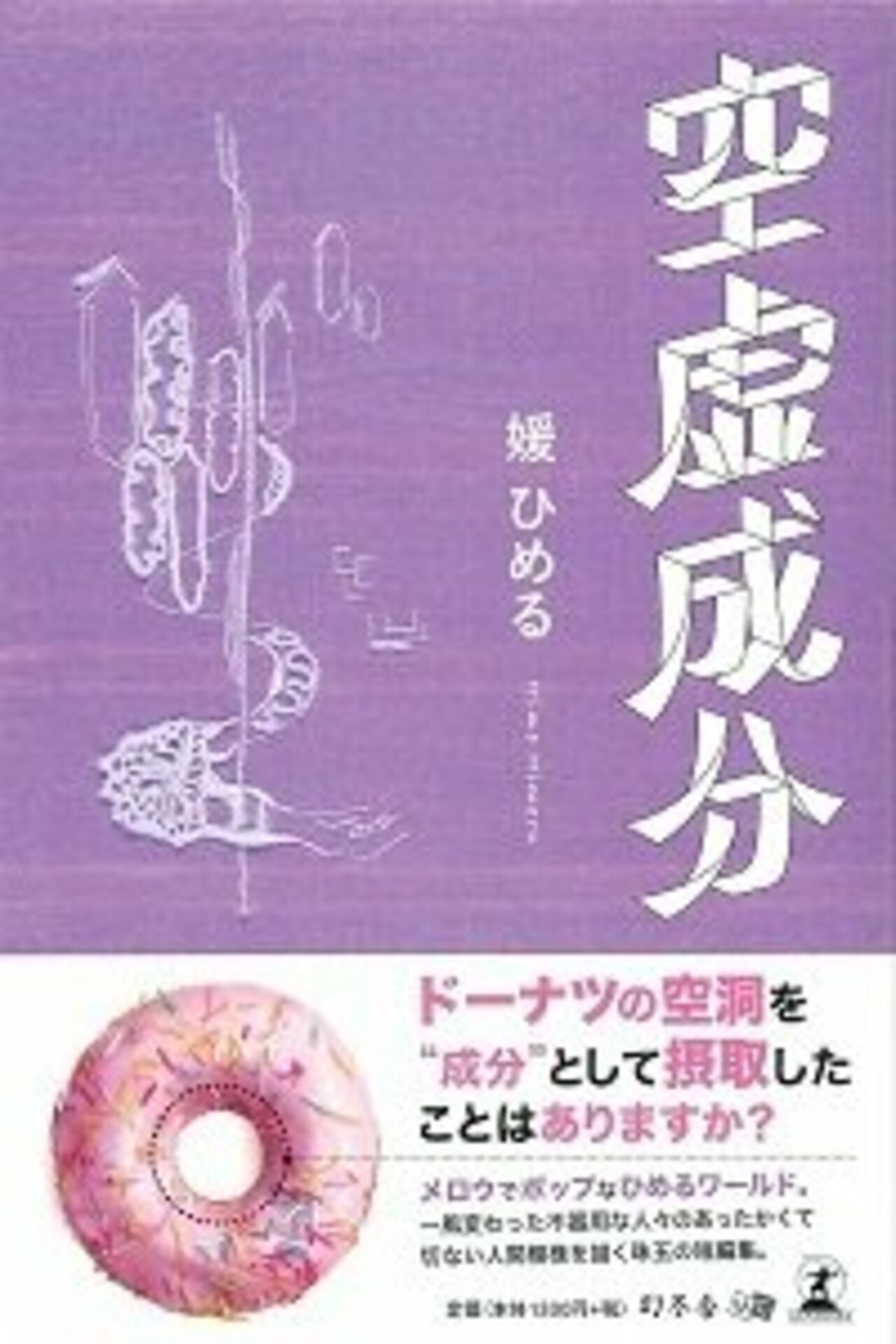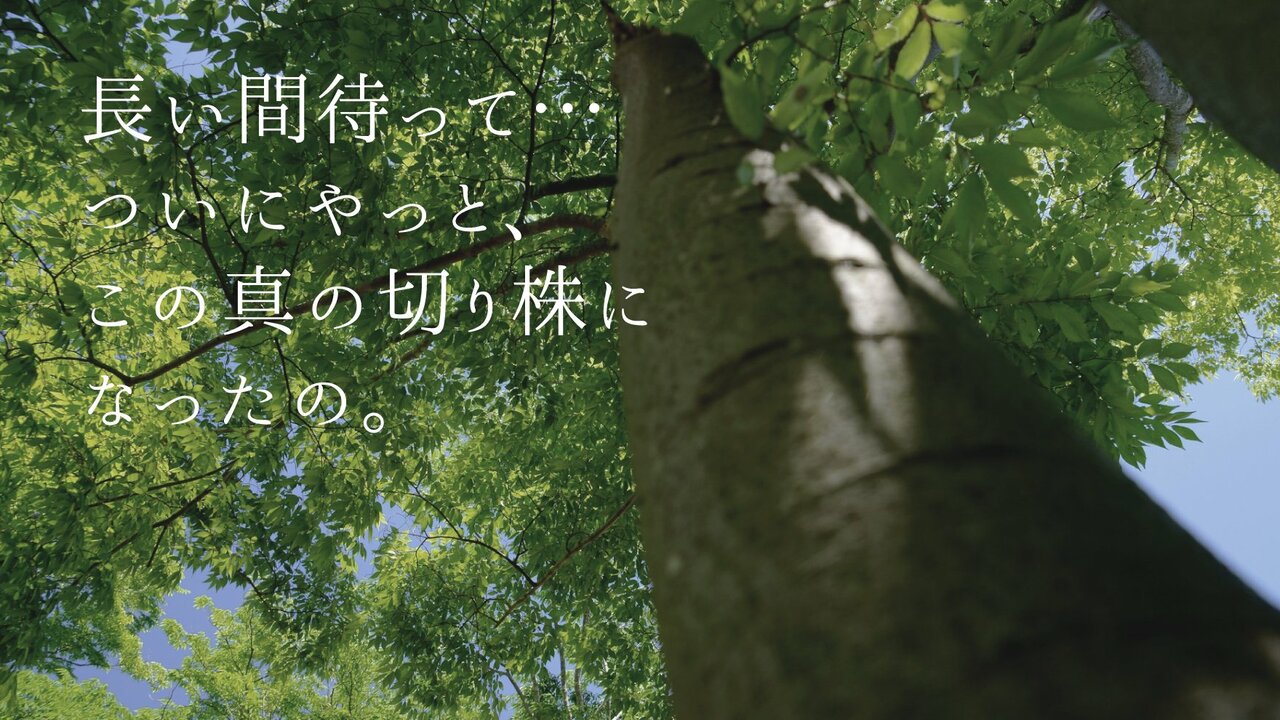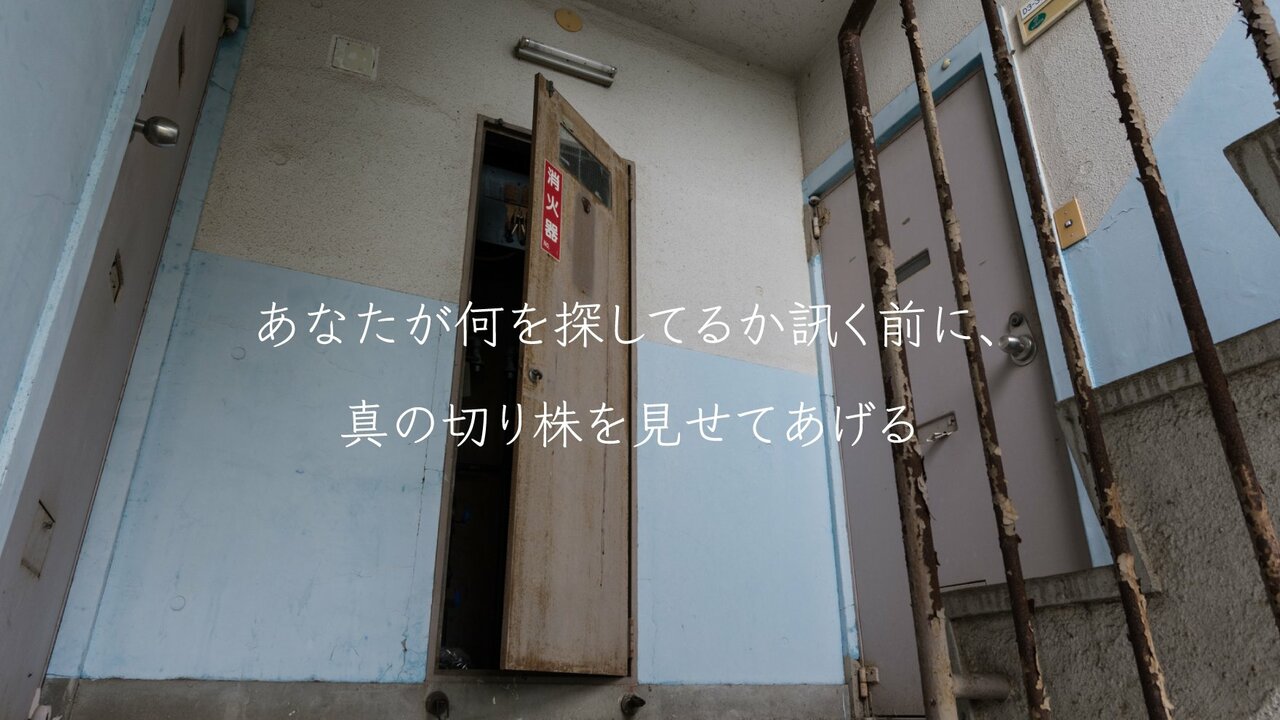短期で入っていた配送の仕事が終わり、次は何をしようかと考えていたある日、ポストにウェイター募集のちらしを見つけた。フレンチレストラン、アンフィニの文字を見ても、最初あそこだとは分からなかった。
地図を見てやっと、ああ、と気付く。面接を受けにいくと、いかにもレストランの店長らしい、おなかが突きでてぽっちゃりした人物が出てきた。きっとこの人は食べるのが人一倍好きなんだろうな、と当たり前のことを洋一は思った。
バターをたっぷり使った料理の味見をしたり、こってりした残り物を厨房の隅で食べたりしているうちに、自然とこんな体形になってしまったのだろう。店長の外見に、洋一は好感を持った。
店の窓から見えていた、暖かそうで優雅な雰囲気を、店長の外見と雰囲気は裏切っていなかった。
「うちが一番忙しいのはクリスマス時期です」店長は仕事内容を簡単に説明した後、洋一の履歴書に目を落としながら言った。「まぁ当然だけどね。だからその時期は絶対休めないよ。彼女と過ごしたいと思っても、まず無理だから。ここでもし働くとしたら、そういうのは諦めなきゃいけなくなる」
「大丈夫です」洋一はすぐに言った。「僕、彼女いませんから」
「あ、そうなの」店長は顔を上げてチラッと洋一を見た。「今はいなくても、この先は分からないじゃない」
「大丈夫です」
洋一は繰り返した。なんとなく、この先当分、彼女ができない自信がある。店長の言う通り、先のことは分からないが、勘のようなものだ。過去を振り返ってみても、洋一の勘は結構当たる。
「本当に大丈夫そう? やれるかな?」
「大丈夫です。やれます」
洋一は力強く答えた。そこでやっと、店長は口元を緩めた。
「じゃ、よろしく」
一週間後、洋一は店のジャケットを着て、ウェイターとして働き始めた。いつも前を通り、窓から中を眺めていた店に、自分がその一員として働いているのは少し不思議な気がした。