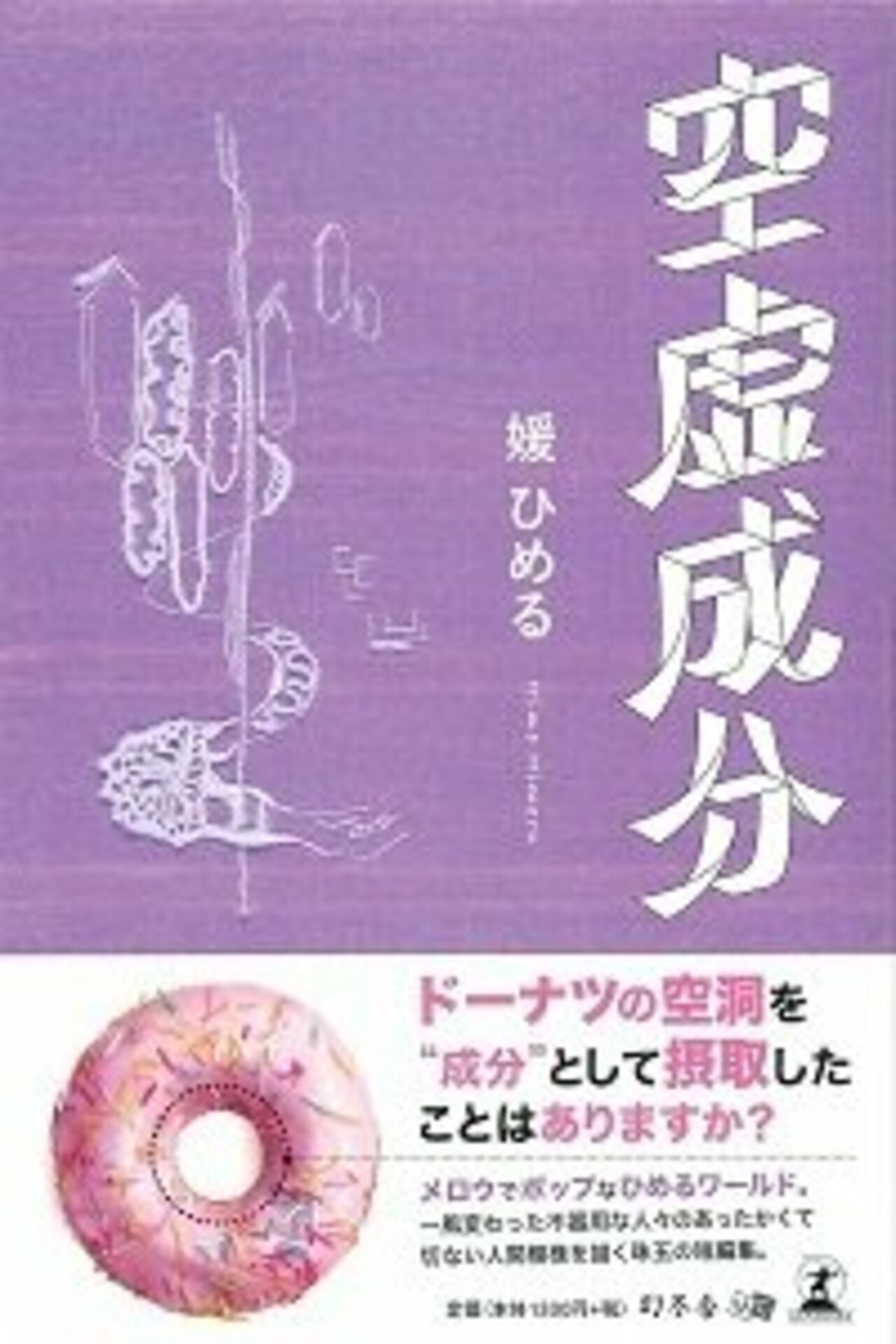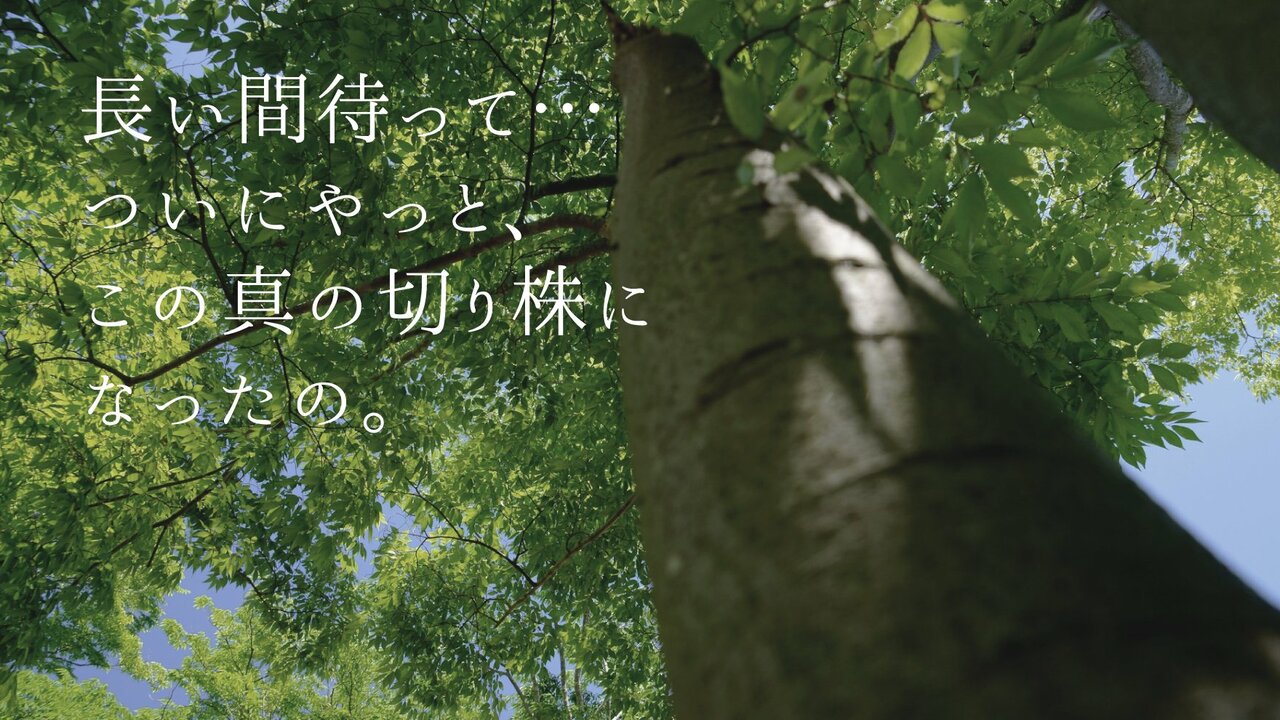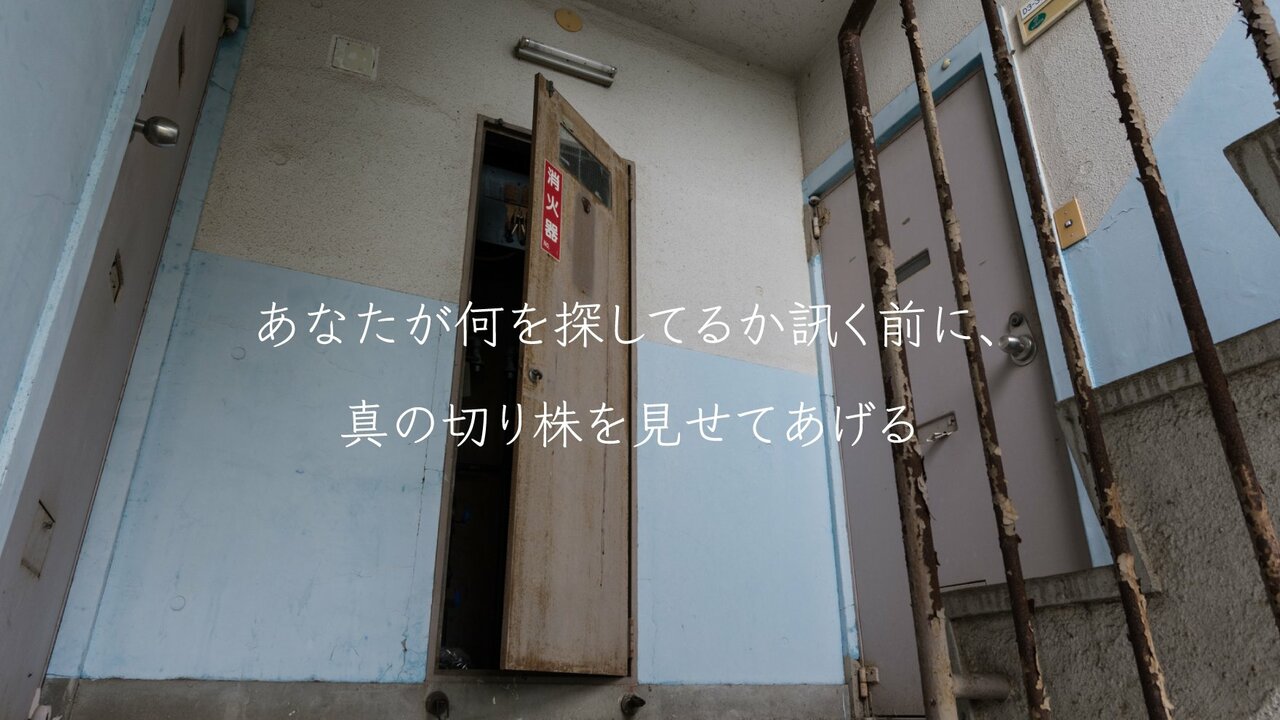くしゃみとルービックキューブ
2.
多くの若者の例にもれず、洋一は朝が弱い。あと十分、いや、あと一分でも寝かせてくれたら悪魔に魂を売ってもいい、と本気で思うほどに弱い。
その日は夢の断片が残っていた。洋一はやっとのそのそと起きだすと、なんとか夢の内容を思いだそうと努めた。
──そうだ。確か、ドラム4のくしゃみの人物が出てきたのだ。ドラム4は恰幅が良く、独特な威圧感があった。今度、参院選に出馬するんだ、と低い声で洋一に言った。顔の部分は黒っぽい雲に覆われていて見えない。
グァンッ!とくしゃみをしたときだけ雲は一時的に移動するのだが、すぐまた元の位置に戻ってきてしまう。さすが根っからの悪人は違うなぁ、と洋一は夢の中で妙に納得していた。
朝食はいつも決まったものを食べる。レンジでチンしたコーヒー牛乳とトースト一枚。トーストには、これでもかというほどにマーマレードを塗りたくる。甘酸っぱいトーストを齧りながら、壁に貼ったカレンダーをじっと見る。カレンダーは、イスに腰掛けて顔を上げたとき、自然と目に入る位置に貼られている。
今日の日付を洋一は確認する。オレンジのペンで丸がついているところはフレンチレストラン、アンフィニに入る日だ。だいたい週四日入っている。残りの日は単発のバイトを入れる。たとえば交通調査とかコンサートスタッフとかちらし配りとかだ。
これは生活に変化をつけるためである。アンフィニ一本にすると、飽きそうな気がするから。飽きることを、洋一は密かに恐れている。飽きてしまうとやる気がなくなる。惰性で仕事をしたくない。
アンフィニは、こぢんまりとした一軒家のレストランだ。地元の新聞に、隠れ家的名店と紹介されたことがある。開店してから二十年近く経っており、毎年、誕生日や何かの記念日になると訪れる常連客が多い。店は、洋一のアパートから徒歩で十分ほどのところにある。
そこで働くようになる前、洋一は毎日のようにアンフィニの前を通っていた。店の外観は淡いピンクで統一されていて、壁には蔦が適度に絡まり、暗くなると蔦に沿って掛けられたイルミネーションが上品にまたたく。窓からもれる暖かそうな光が、通りをほんのりとオレンジ色に染める。
当時、配送という肉体労働をしていた洋一は、疲れて帰ってくるとき、おいしそうな料理を食べながら談笑している人達を、羨ましく眺めながら通り過ぎたものだ。
窓の向こう側では、いかにも優雅な世界が繰り広げられているように思えた。店の前を歩くとき、洋一はそのおこぼれにあずかり、ほんの少しだが心に余裕が生まれるような気がした。