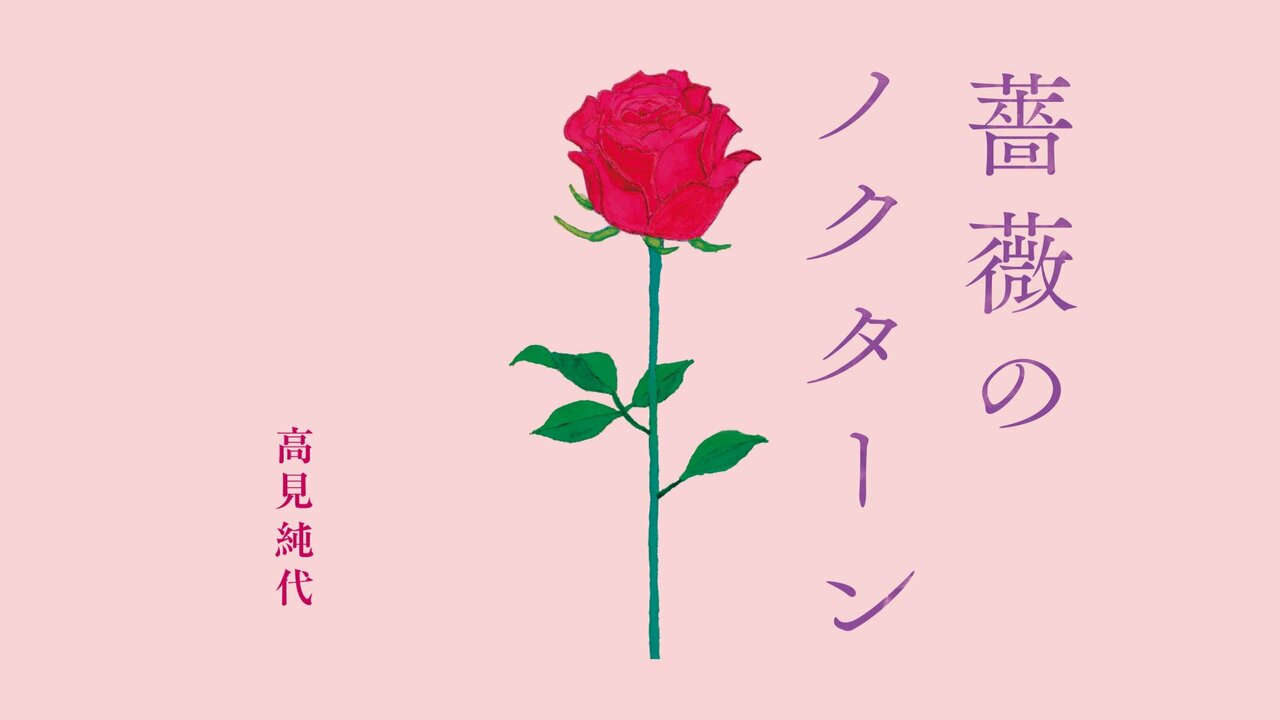二
そのうち、声が全く出なくなった。平成十八年春、澄世は三十九歳になっていた。またK病院の心療内科のD先生にかかった。
「声も出ないって言うでしょ。そう言う心境なんです。ゆっくり休みなさい」
そう言われて、K病院に入院した。入院中、口のきけない澄世は、病室で、ひたすら花の絵を描いた。
花が好きな澄世は、机にいつも花を飾り、枯れる別れが淋しくて、絵に描き残そうと思ったのがきっかけだった。絵筆を持ったのは中学生以来だと思われたが、不思議と筆がすすんだ。何枚も何枚も、花の絵がスケッチブックに描かれていった。
そんな澄世に、病棟で友達が出来た。六十歳、肝臓癌末期の森山恵子だった。廊下やトイレで顔を合わせ、会釈するだけだったのが、話しかけられる様になり、いつしか一緒に、花壇がある屋上へ散歩するようになった。
失声症の澄世は、もっぱら聞き役だった。それが恵子には良かったのかもしれない。ある日、屋上のベンチに二人で腰かけていて、恵子が言った。
「私にはね、貴女くらいの歳の娘がいてね、結婚して東京にいるの。……心も遠いの」
「……」
「私、離婚してね……一人暮らしなの。職場でも孤立しててね、淋しくて……」