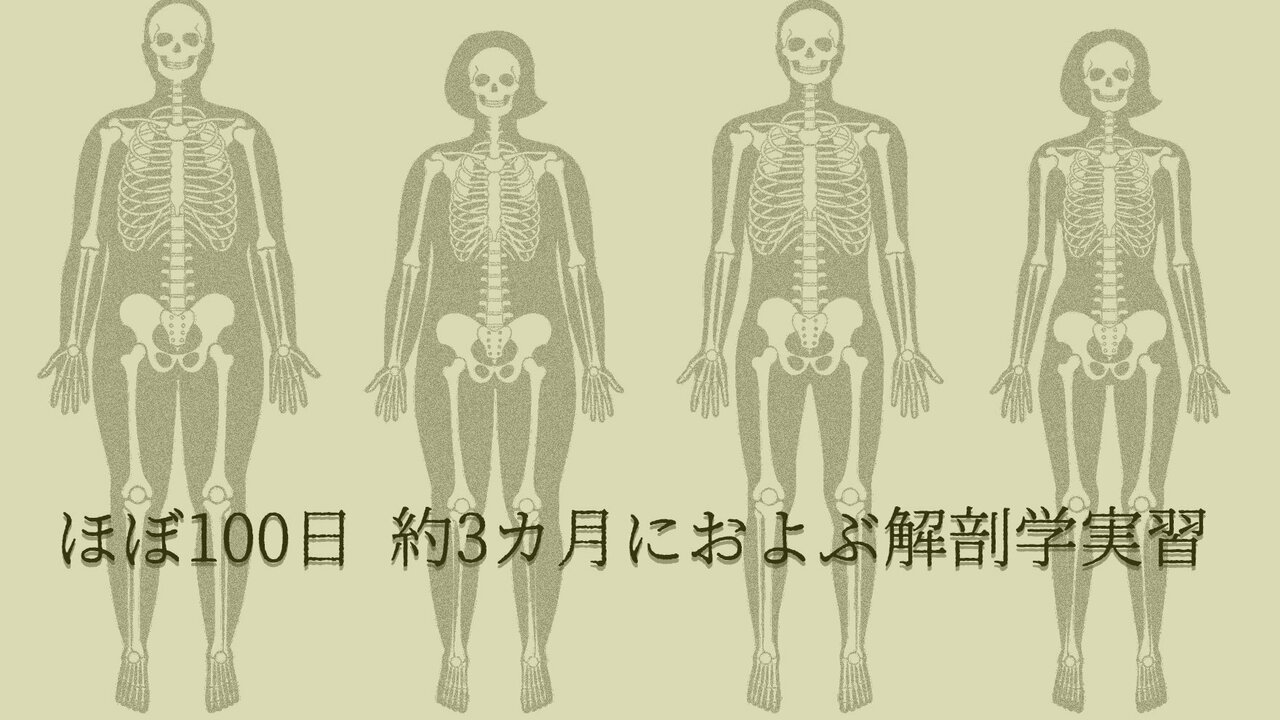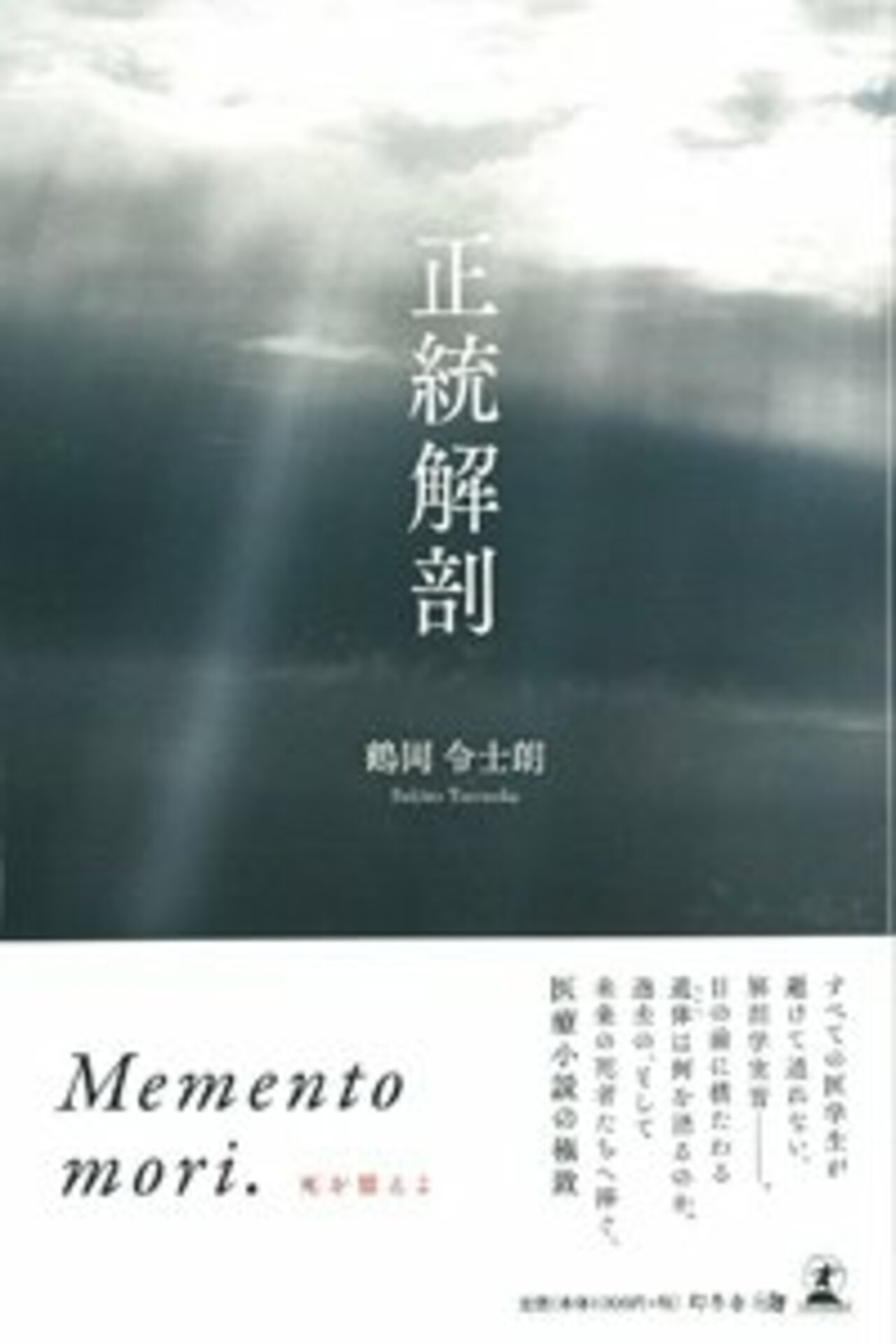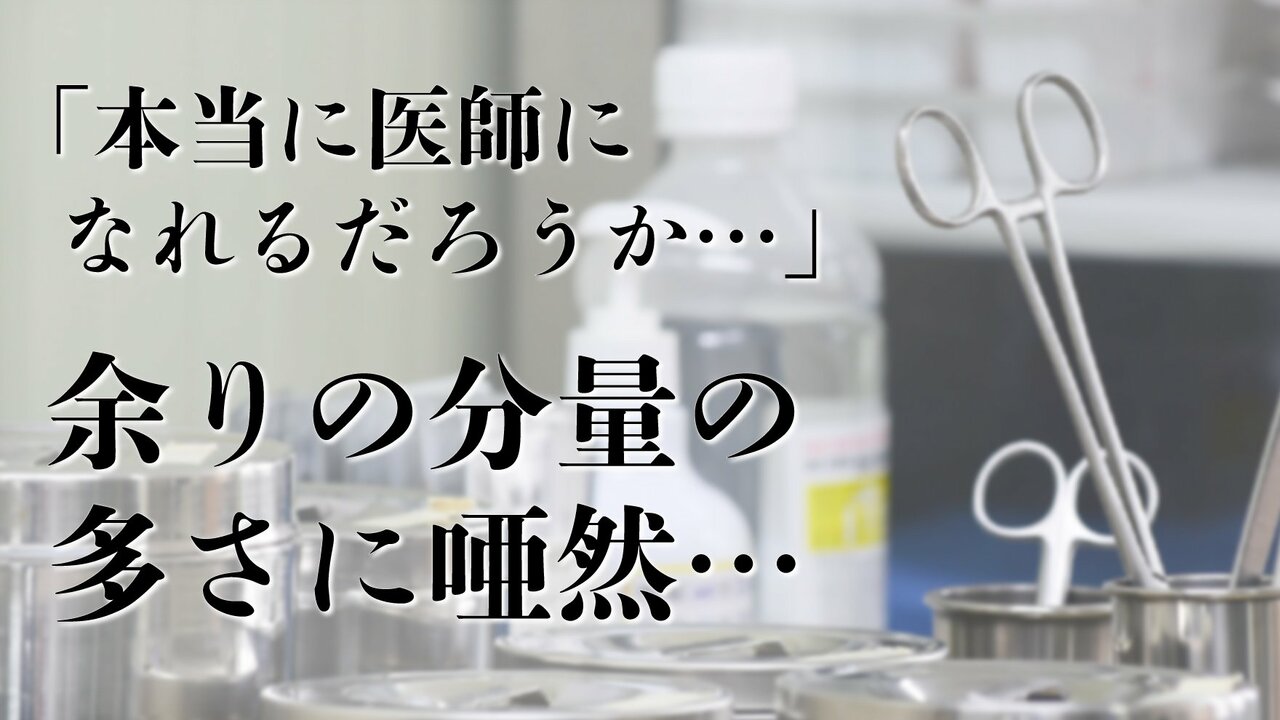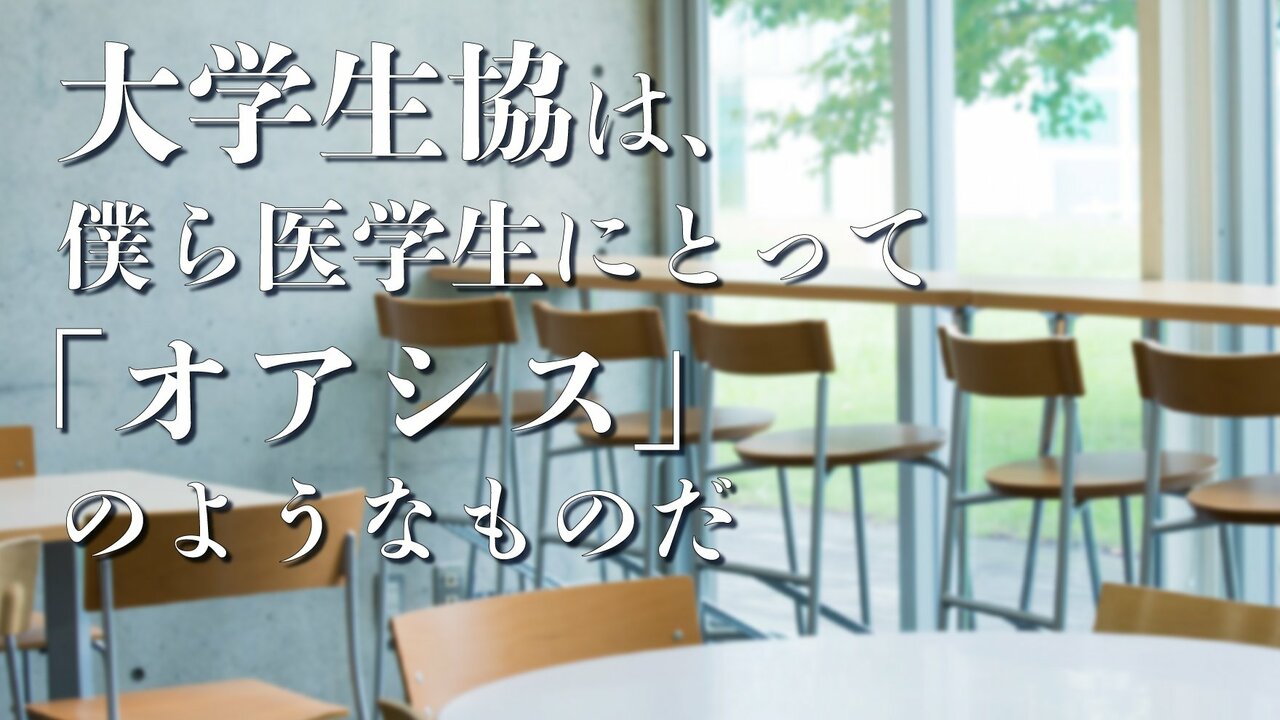第一部 序章 はじまり
今日の昼下がりの空は、全天が薄墨色の低い雲で何重にも被われ、周囲は夕方のようにうす暗い。いかにも鉛のように重そうな黒ずんだ雲は、やがてこの地上全てを押しつぶしそうにさえ思える。それは、何かを厳粛に暗示しているかのようだ。
集合場所に指定された、9階建て研究棟の南前コンコース広場に、開始時刻の少し前から、同級生たちが集まっている。誰もが真新しい教科書を手にして、等しく緊張している。迫り来る何かに身構えているかの様だ。得体のしれない不安を紛(まぎ)らわせるために、各人がところどころで近くの同級生と会話し、ざわめく声が耳に交錯する。
新学年が始まり、格別に優秀な生徒でも無く、それほど情熱に溢(あふ)れていたわけでもない、平凡な一人の医学部生の自分であったが、さすがにこの第3学年を迎えて覚悟する所があった。何しろ、これからほぼ100日、約3カ月におよぶ解剖学実習が始まるのだ。
広場の西側にある研究棟の隣に、付属する3階建てがある。その一階の不透明なスリガラスの向こうの部屋の気配に、誰もが注意を向けていたが、物音一つしない。そこはまさに去年、骨学実習のあった部屋だった。
すでに去年、骨学の実習は終えていた。初めて教室に入って、目の前に大きな、ホルマリンの強烈な臭気を放つ、直方体の木箱を前にした時の事は今でも鮮明に覚えている。閉じてあった蓋を開けると、まるで棺桶の中をのぞいているかのように、骨が詰め込まれていた。
初めて触る人体の骨だった。白さが、ひどく目に滲みた。骨学実習担当の高本教授の合図で、めいめい恐る恐る手を出して、最初は取りあえず何も分からないまま、ただ触ってみる。何でも、種々の経緯でインド人の標本ということだ。
大抵の者は声に出したいのを我慢しているのに、これが人間の骨かあ、と誰かが声をあげるのが聞こえた。軽蔑と、代弁してくれた事への感謝が同時に起こる。
とにかく机の上に全部中身を広げなさい、という高本教授の一声で、目の前の細長い骨をゆっくりと手に取ると、石の様に冷んやりした感触と非日常的な固い反発が、他者に触れられることを拒絶しているかのように感じられた。
注意はしているが、箱に当たったり、机の面に少し乱暴に置く時のカタンという乾いた音が、何の縁で異国の地にこのような形で来る事になったのかという、運命への恨みのように聞こえた。