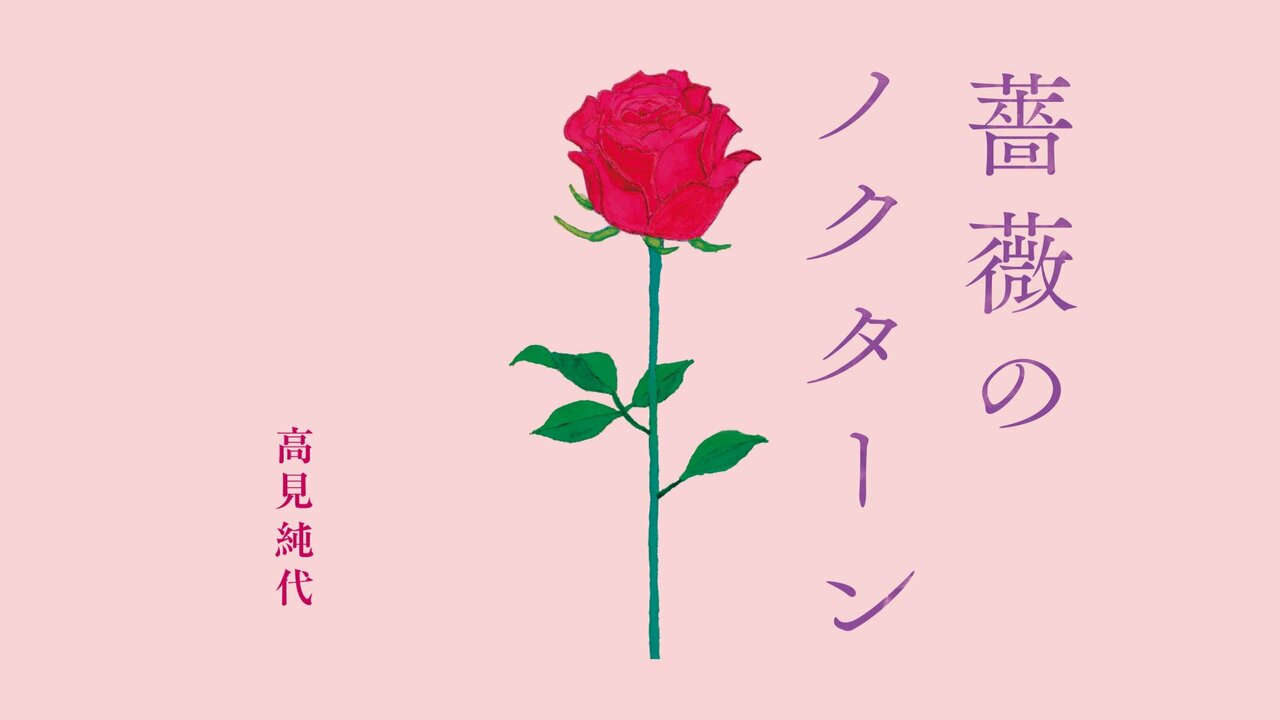二
雑誌「とらばーゆ」や新聞で、秘書の求人を探した。平成五年五月のある朝、S新聞の朝刊の求人欄を見ていて、目が釘付けになった。
「S新聞社 大阪本社 役員秘書募集。短大卒以上、二十五歳以下、正社員雇用。」
澄世は二十六歳になっていた。しかし、どうしても諦める気になれなかった。書かれてある人事部へ電話をし、募集人数を聞くと、一人だと言われた。狭き門だ……。
しかし、自分はS社のショールームの仕事で接遇マナーを培ったし、M社で、テレビと新聞のちがいはあるにせよ、マスコミの空気を知っているし、事務も経験した、行くしかない!と澄世は思った。
履歴書を書き、写真を貼り、生年月日を正直に書き、年齢の欄には「二十五歳」と偽りを書いて、投函した。程なく、書類審査を通ったとの知らせが届いた。
喜ぶと同時に、指定された自己PR文の作成に力を注ぎ、面接の日を待った。面接の日、ボブカットの髪をとかし、きっちりと化粧をし、青いスーツを着た。スカートは膝丈で、白のパンプスに白のバッグを持ち、清潔感を心がけた。
新聞社へ足を踏み入れるなど初めての事で、ドキドキし、緊張した。受付に言うと、人事部の男性が来て、古びた廊下を歩き、控え室に案内された。先に一人いて、澄世は二人目だった。
あと三人が来て、五人になったところで、さっきの男性が「では」と面接室の方へ、五人を先導した。面接は、来た順に一人ずつだった。
澄世は二番目に呼ばれ、中へ入った。大きな会議室で、向かい側に面接官の男性が四人並んで座っていた。澄世は落ち着いて一礼し、椅子に腰かけた。
まず、先に提出した自己PR文に基づき、色々と質問を受け、冷静に答えた。質疑応答が終わったかと思われた時、右から二人目の眼光の鋭い恰幅のいい男が言った。
「ところで、君。生年月日から計算すると、年齢が合わないんじゃないですか?」
澄世は、来た!と思ったが、ここでひるんでは、元も子もないと思い息を整えた。