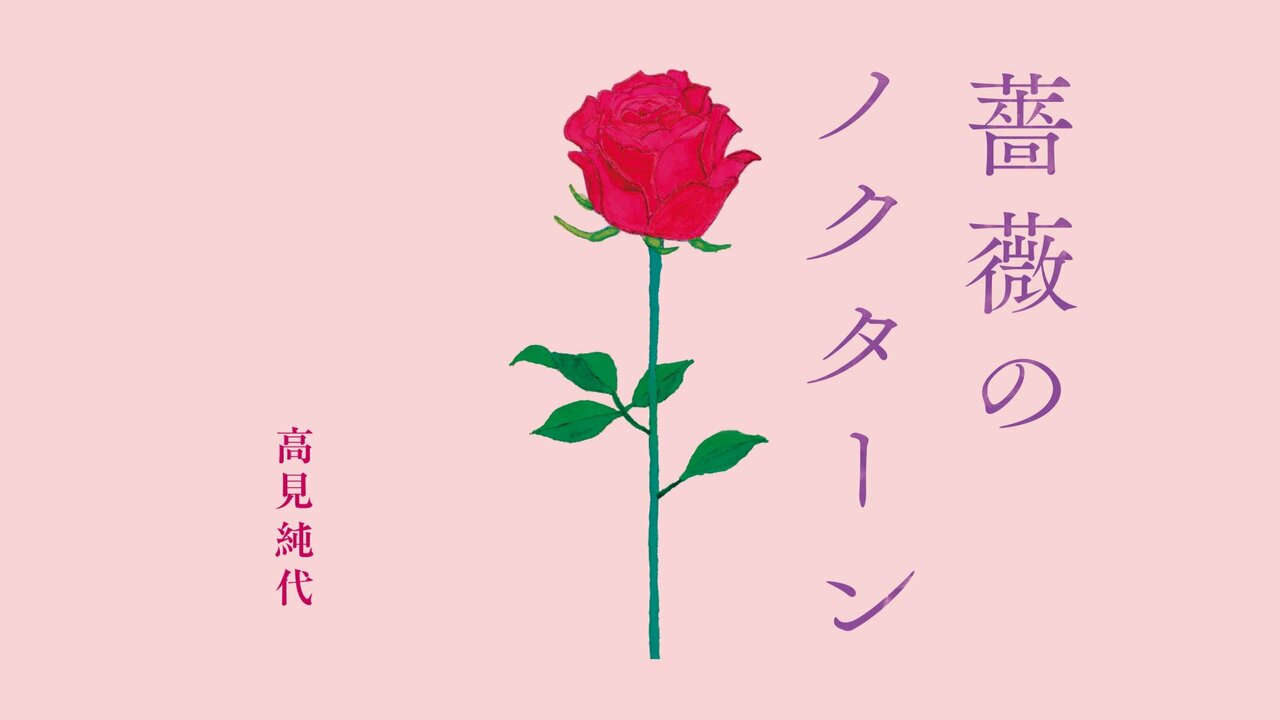一
あの夏のあと、澄世はすぐに会おうとはしなかった。和彦は初めて女にじらされて、イライラした。
九月を過ぎ、十月の半ばに誘ってみたら、澄世から「入院している」と返信メールが来て、驚いて電話をかけた。
「ごめんなさい。持病の喘息がでたの」とか細い声が答えた。
十一月の始めに退院したと連絡があり、和彦はしばらく待った。十二日(日)に、やっと会えた。
「昨日、京都の大覚寺でお花の講座があって行ってきたの。滅多にない文人華を習えて楽しかったわ。もう元気よ。嵐山の紅葉が綺麗だったわ。これお土産」と、渡月橋の紅葉の絵が描かれた栞を和彦に渡した。心なしかやつれたように見え、連れ回す気になれず、その日はそのままJR大阪駅で別れた。
澄世はいつものように、大和路快速に乗って法隆寺へ帰って行った。和彦は神戸線に乗り、芦屋へ帰る電車の中で、澄世のくれた栞を見つめた。
あの人はいったい何を求めているんだろう?
いや、ひょっとして何も求めていないのか? 他の女性とはまるでちがう……。
十二月十八日(月)、二人の忘年会をしようと夜に会って、カラオケBOXへ行った。澄世はまだ喉がよくないからと言って歌わなかったが、和彦が何を歌っても、喜んで拍手をしてくれた。曲の切れ間に、澄世が言った。
「彼女って、何歳?」
「三十二歳だけど?」
「じゃぁ、もう結婚しなさい」
「まだそんな関係じゃないよ」
和彦は十月で、三十八歳になっていた。今日こそは色々と聞き出して、澄世との交際を考えている事を伝えたかったのに、出鼻をくじかれた。
急に澄世が一曲歌うと言ってリモコンを押した。
「ずっとそばにいるとあんなに言ったのに今はひとり見てる夜空はかない約束……」