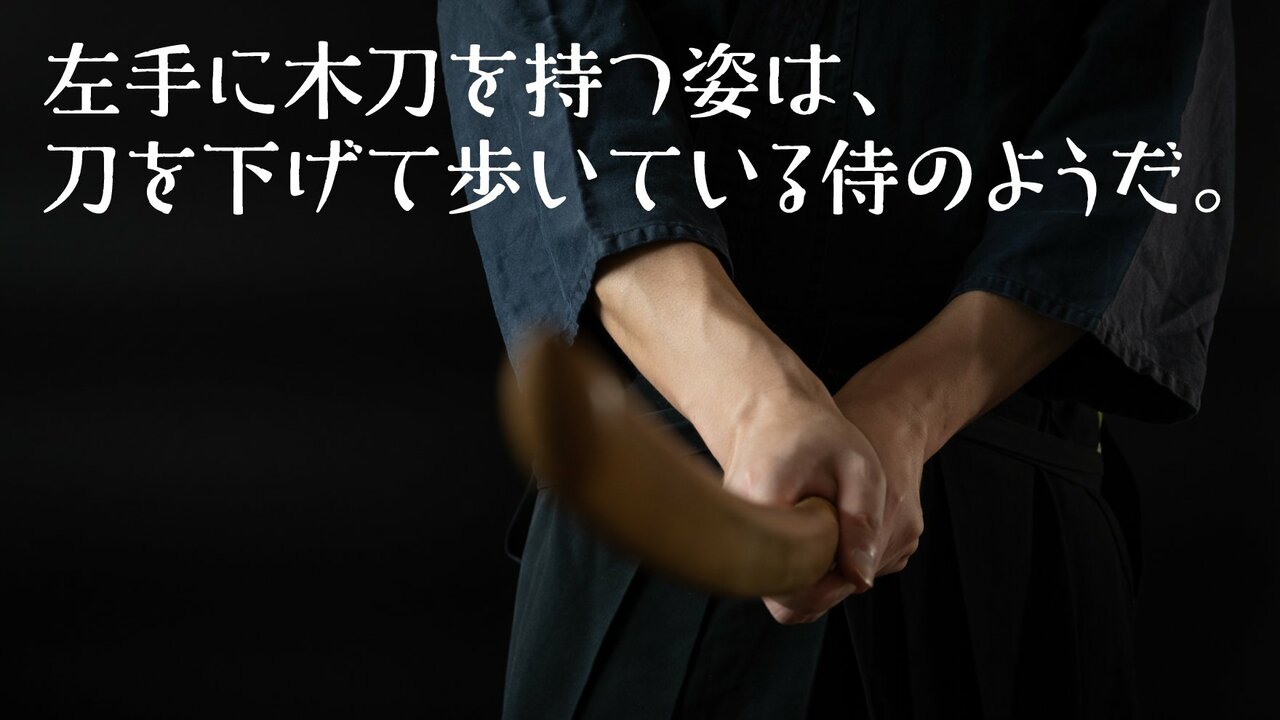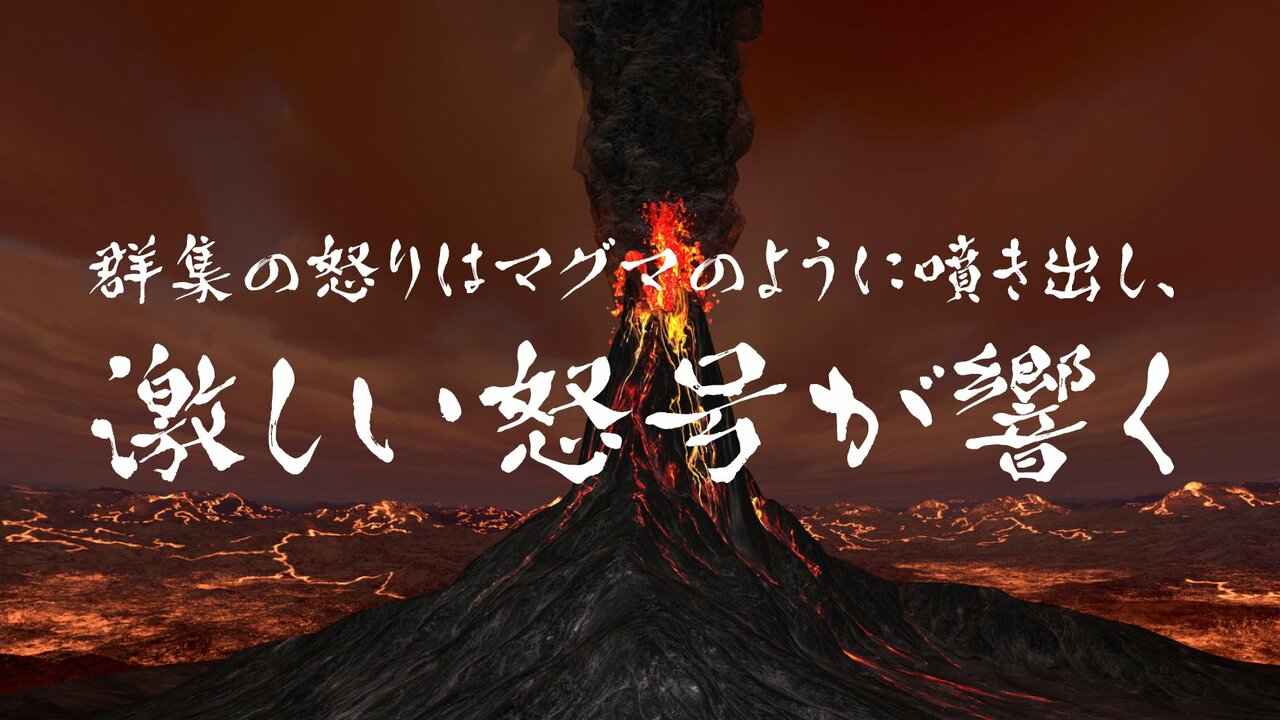幸子は四歳から、家族でインドのデリーに住んでいた。
母親は幸子が五歳の時、お産のために日本に戻った。その後、日本で生まれた妹の良子(りょうこ)に聴覚の障害があることがわかり、母親と良子はそのまま日本で暮らしている。
良子がかすかに聞こえる音を頼りに、「くちびる」を読み、正しく声を出して発音ができるようになるまで、日本で生活をすることを母親が望んだからだ。そのため、幸子は母親と離れ、その後の五年間、父親と二人で暮らしていた。
父親は海軍上がりの警察官で、インドにある日本大使館で警備をしている。
父親は普段から帰りが遅く、仕事で家に帰らない日も多かったので、幸子は大使館の敷地の中にある小さな部屋で、独りで過ごすことも多かった。そんな生活でも、幸子は父親との二人の暮らしが好きだった。
それは、自分勝手に過ごせることが気に入っていたこともあるが、父親は休みになると旅行に連れて行ってくれたからだ。旅行は幸子の何よりの楽しみだった。
鉄道列車に乗り、デリーからインド国内のいろいろな街を訪れた。
ピンク色の建物が並ぶジャイプール。タージ・マハルがあるアーグラ。フランシスコ・ザビエル終焉の地であるゴアなどを見て回った。
幸子は旅行に連れて行ってもらうため、おとなしく留守番をした。母親が日本から持ち込んだ「学習ドリル」で勉強し、本を読み、星座を覚えた。父親が帰るたびに、新しく勉強したことを披露して、褒めてもらうことが楽しみだった。
父親が留守の間、食事は大使館の料理人がつくる「まかない」を運んでもらっていた。
毎日、同じおかずを食べることも多かったが、それでも、食事があるだけ幸せだと思っていた。大使館の外では、多くのインド人が満足に食べられないことを知っていたからだ。
幸子は十歳になった今、日本での生活の記憶が無く、デリーでの生活が普通だと思っていた。
ところが、父親が急に新しい任務に就くこととなり、帰国を命じられた。新しい任務地に向かう手続きのため、二人は練馬にある自宅に戻っている。