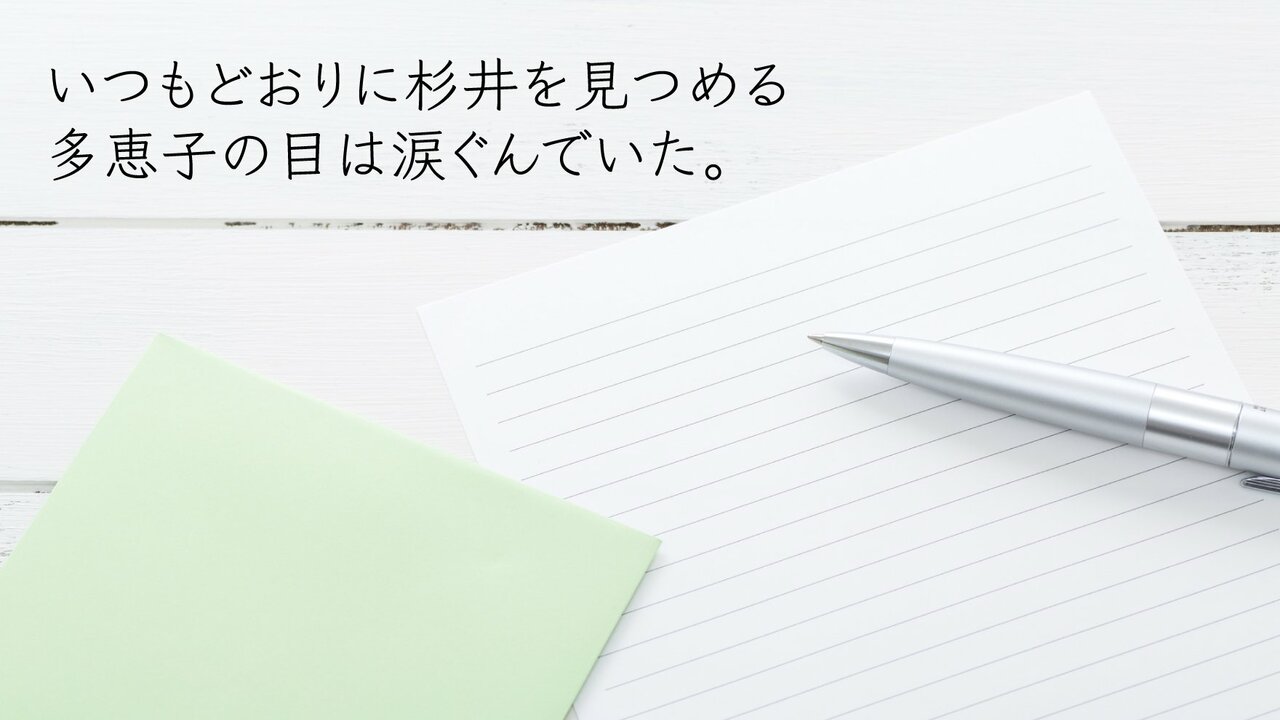第一章 新兵
徴兵
「人間が周囲から祝福される瞬間というのは、存外その人間が幸福とは言えない瞬間なのかも知れない」
晩秋の微妙な冷気を帯びた風を受けてやさしくはためきながら、それでいて妙に誇らしげに青空に林立する「のぼり」を見ながら、杉井謙一はそう考えた。
昭和十三年六月、その年に二十歳を迎えることになっていた杉井のもとに徴兵検査の通知が届いた。
検査場は、城内地区の静岡連隊区司令部で、いままで何度も前を通ってその存在は知っているものの、いざあの無言の威圧感を感じさせる茶灰色の門をくぐることになってみると、やはりそこには今までにあまり経験したことのない緊張感があった。
当日は陽射しの強い汗ばむ日で、司令部に向かう途中、右手の駿府城内堀の堤の上の木々の葉がその陽射しをさえぎって、堀の水面に鮮やかな斑模様を形成していた。司令部の門の中では、既に百名近い若者たちが玄関前に集まっていた。
商業学校の同級だった岩井、片桐、高崎もこの日に呼ばれていた。皆揃って新調と思われる開襟シャツを着て、その白さが眩しかった。
誘導されて入った検査場は椅子を並べれば三百は入ると思われる大会議場だった。両胸のポケットに鉛筆を二本ずつ差した三十二、三歳の担当官が大声で検査の手順を説明していた。
「裸になって二列に並べ」
指示のとおり、杉井もふんどし一つになって、列の中程に並んだ。
戦地に赴いても耐え得るかどうかのチェックのわりに検査は簡易なものだった。視力検査、身長体重の測定が終わると、あとは聴診器を胸と背中に当てながらの問診だけだった。両あごの張ったゴマ塩頭の軍医は、杉井の胸を調べながら言った。