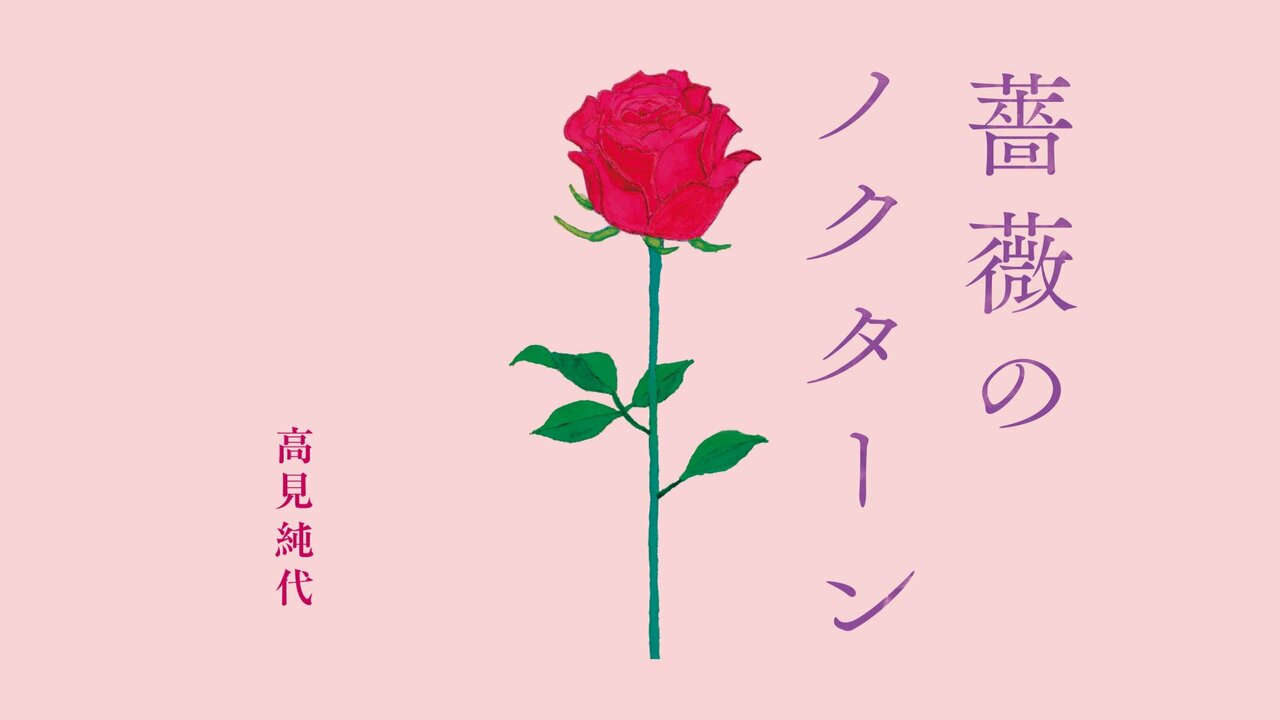一
「私はお世辞は言わないわ、本当にそう思ってよ」
周りがざわつきだし、席が混んできた。カシスオレンジが来て、二人はグラスを合わせカチッと乾杯をした。
ステージが始まり、石丸幹二が登場した。澄世は明るい笑顔で、拍手を送っている。
『キャバレー』のメドレーで始まり、『キャッツ』の「メモリー」、『ジキル&ハイド』の「時が来た」等、ミュージカルナンバーが次々と歌われ、彼のオリジナル曲「こもれびの庭に」「再会」等も歌われた。ラストに「マイ・ウェイ」が歌われ、彼はサックスも吹いた。
澄世は終始上機嫌だった。実は、この日、和彦は浮かない気分だった。澄世もそれをとうに察知していた。
「軽く飲み直さない?」
「ああ、いいね」
二人は、ヒルトンホテルのラウンジに入った。
「僕は水割り。貴女は?」
「私は赤ワイン」
ボーイが去ったあと、二人はクスッと笑い合った。初めて会った日と同じ注文だったのが可笑しかったからだ。
「貴女はよほど赤ワインが好きですね」
「ええ。ところで、何を悩んでるの?」
「えっ? わかる? まいったなぁ」
「いいから白状しなさい」
澄世はお姉さん気取りで追究した。どうやら、和彦が企画し、プレゼンも成功し、上手く運んでいる仕事が、やってもやっても上司に認められない、認められないどころか中止しろと言われている。
取引先の先方も乗り気だし、絶対成功するプランなので、悔しい、何がいけないのか皆目わからない。同僚のAは大した仕事もしていないのに上司に認められ、本来、自分が行くと噂されていた部署へ、Aが栄転した。と言う仕事の悩みだった。
ジーッと聞いていた澄世が言った。
「それは嫉妬よ。ジェラシー、わかる? あなたは有能だからこそ、蹴落とされたのよ。ここで自信をなくしたら、相手の思うつぼよ。あなたはエリートの上にハンサムで有能、それって彼らには面白くないのよ。人間て結局、嫉妬なのよ。
いい? 組織で上手く泳ぐには、上司にゴマをすれとまでは言わないけど、貴方はちょっとドジで三枚目を演じないとダメね。仕事で認められたいって凄くわかるけど、貴方の場合は難しいわね。クレオパトラの鼻が低かったらの、たとえ話の逆になるけど、貴方の背が低かったら、実力で成功しやすかったと思うわ。