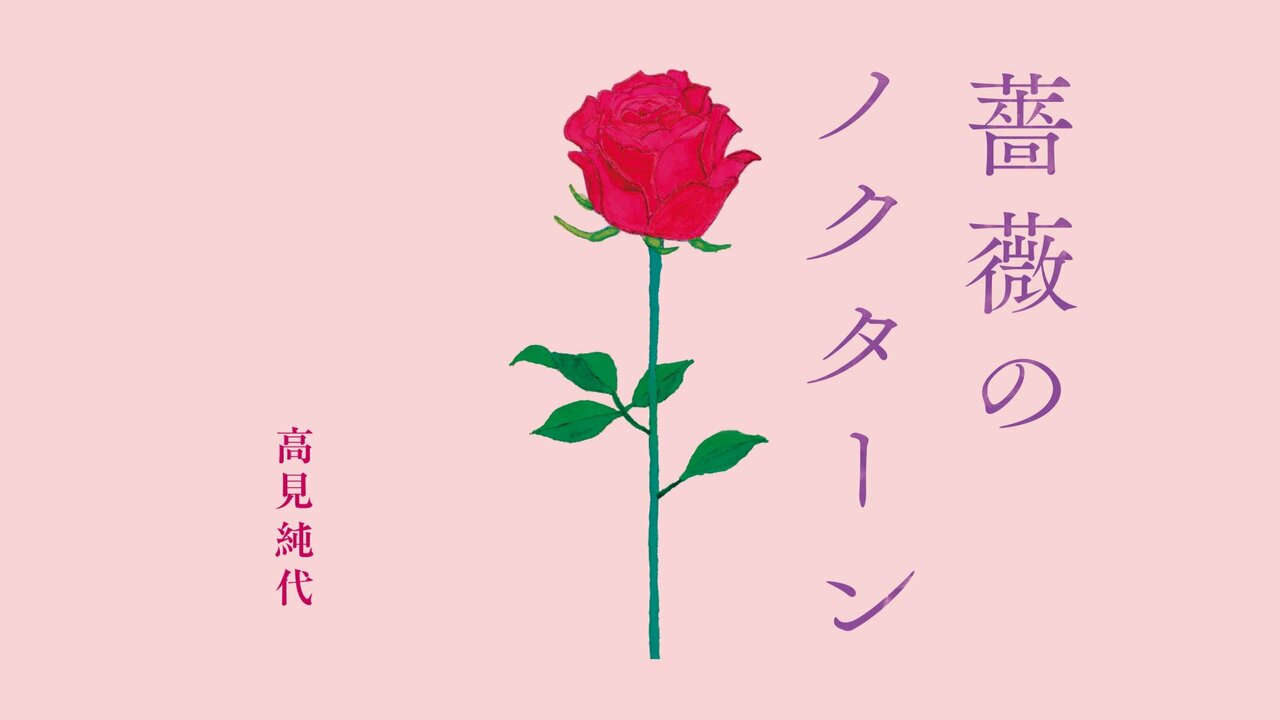一
「へー、凄いですね。流石、いけばなの先生ですね」
和彦は感心した。食事はもうメインディッシュのステーキが来ていた。
「それで、デモンストレーションだけど、舞台に大覚寺のお坊様十人が左右から五人ずつ出てこられ、ずらっと並ばれて声明(しょうみょう)から始まったの。それが素晴らしい合唱なのよ。そして、お坊様方が散華(さんげ)をされ、会場の前列に居た私の膝にも紫の散華が一枚舞って来て、まず感動したわ。それから、私の先生、嵯峨御流の今の華務長なんだけど、辻井ミカ先生が、最初に『荘厳華(しょうごんか) 』をいけられ、次に北海道と沖縄の景色をいけられて、京都の御所車をいけられ、最後に、この日の為に、この季節に奇跡的に咲かせた嵯峨菊五本で、お生花(せいか)をいけられたの。『荘厳華』は沖縄の神様にお祈りを捧げていけたって先生が説明されたけれど、あの声明と『荘厳華』で、沖縄の哀しい英霊も慰められたんじゃないかしらって、ご一緒に行ったお友達とも話したのよ。本当に素晴らしかったわ」
おとなしい澄世だが、華道の話になると別人のように、よく喋った。話が一段落したところで、和彦は、ピアノを弾いた時、なぜ泣いていたのか聞こうと思った。正にその時、澄世のナイフとフォークを持つ手が止まった。
「ショパンのバラード……一番だわ」
とつぶやいた。和彦は言われて店内のBGMに耳をこらした。聞き覚えがあった。
「あっ、羽生結弦がショートで使ってた曲ですね。あれは本当に良かった」
やっと話を変える糸口がみつかったと喜んだ和彦は、次の瞬間に驚いた。澄世の目にみるみる涙が溢れ、頬をつたい始めた。澄世は茫然として、涙をふこうともせず、ピアノの音に聴き入っている。和彦があわてて自分のポケットからハンカチを出し、澄世の手に押しつけた。
「ごめんなさい」と、澄世は我に返って、自分のバッグからハンカチを出して涙をふき、和彦のハンカチを丁寧に両手で返した。またか……、和彦は全く面食らった。和彦はもてはするが、誠実で優しく、女を泣かせた事はなかった。目の前で、こんなにも泣く女は初めてだった。
「大丈夫ですか?」
「……」
「次はデザートとコーヒーだから、落ち着いて……」
和彦には、それ以上かける言葉がみあたらなかった。澄世は頷いて、ウェイトレスが皿をさげるのを待った。コーヒーをすすりながら、和彦は次の言葉を探った。
「貴女はピアノに涙もろいんですか?」
「いいえ……あえて言うなら、ショパンですわ」
澄世は自分にも言い聞かせるようにキッパリと言った。これはいよいよ、わけありの女性だな、と和彦は思った。だが、不思議と不快ではなかった。むしろ興味をそそられた。澄世のバッグからマナーモードがブルブルと鳴るのがわかった。
「ごめんなさい」
澄世はバッグを開け、携帯を出し、メールのチェックをした。ガラケーだった。和彦はまた驚いた。今時、スマホを持たないなんて、珍しい人だな。いったい幾つなんだろう? ぽかんとしている和彦に気付き、澄世が言った。
「ガラケーでびっくりした? 可笑しいかな? 私、若い頃、新聞社で役員秘書をしてて、情報に疲れたから……私、時代についていけないの。テレビも殆ど見ないわ」
秘書だったとは、なるほど言われてみれば澄世にピッタリに思えた。二人は何となく、また会う約束をした。
七月一日(土)夕方、澄世の方から誘い、二人はビルボードライブ大阪へ行った。澄世は石丸幹二が好きらしく、今日は彼のライブだった。澄世はノースリーブの赤いドレスで現れ、和彦の意表をついた。肩から手まで、たるみのない白い腕がさらされていた。赤を着た澄世は、華やかで若々しく、けれど色気ではなく上品さをたたえていた。二人は、ステージ正面のテーブルに案内された。
「カクテル、よく知らないのでお願いします」
「カシスオレンジなんかが飲みやすいんじゃないかな?」
「じゃぁそれで」
「カシスオレンジを二つ、それから生ハムとチーズとサラダを」
和彦がさっさと注文をした。
「貴女はクラシック好きだと思ってたから、今日は意外です。どうして石丸幹二が好きなんですか? 僕は正直、『半沢直樹』の時の浅野支店長役の悪いイメージしかなくて……」
「私はちょっと変わってるの。十年程前にDVDでディズニーのアニメ『ノートルダムの鐘』を観て、カジモドに凄く共感して感動して、その役の声を石丸さんがやってたの。歌声が素晴らしくて、彼のCDを二枚持ってるわ」
「へぇー……。てっきり好みのタイプかと思って、ちょっと妬いてたんですが……」
「貴方の方がずっと素敵よ」
「ありがとう、お世辞でもうれしいです」