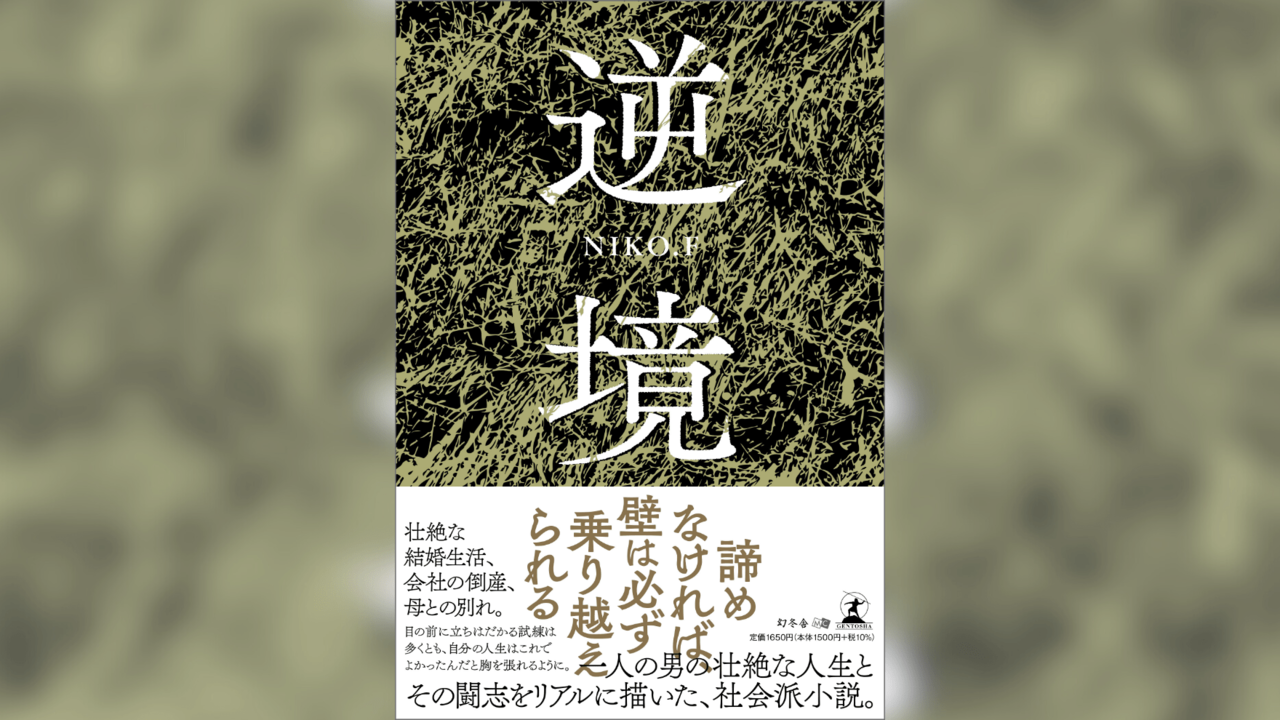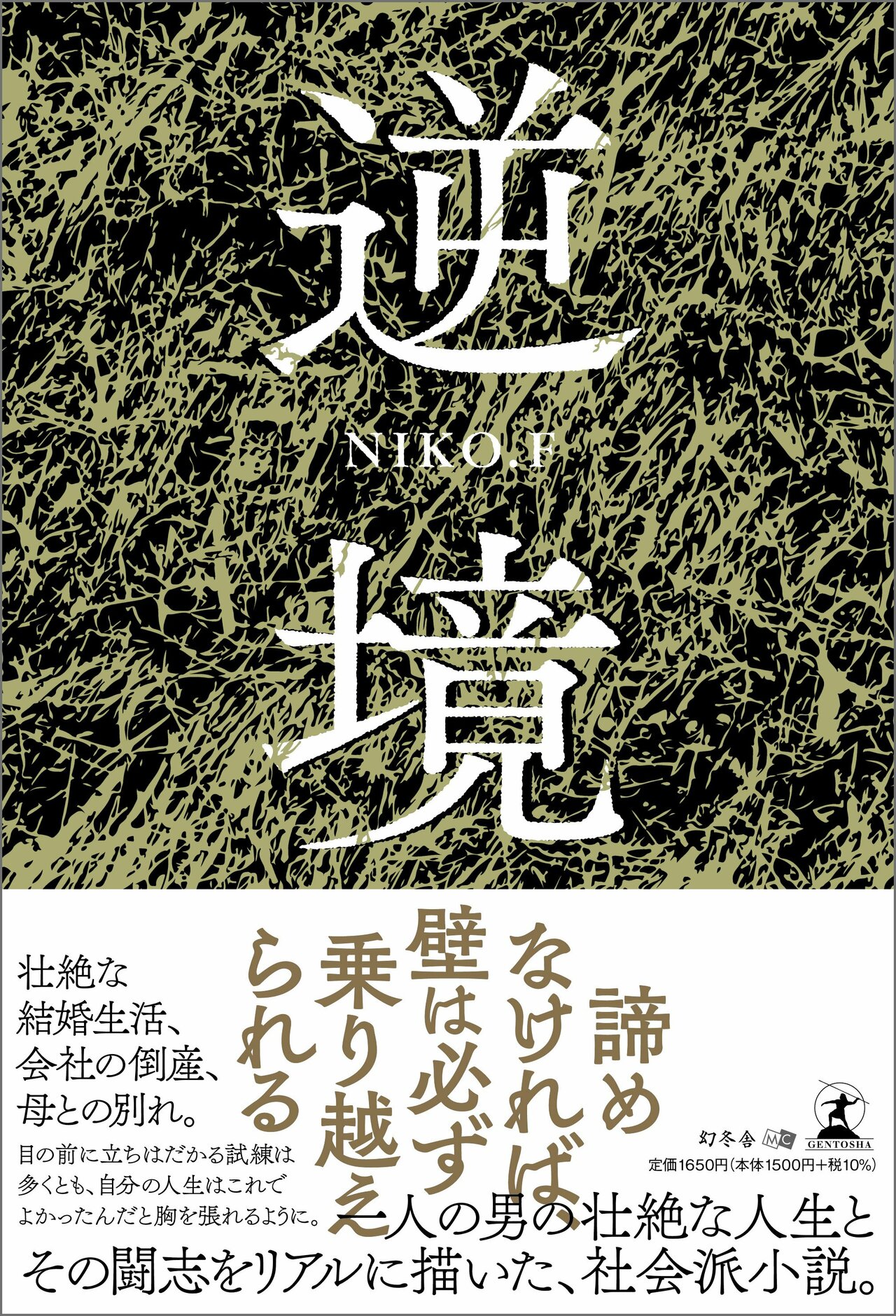【前回の記事を読む】「一度だけ江美をものにした」江美に認められたくて必死だったあの頃。恩師はすでに手をかけていた。
独立
そうこうしているうちに、恩師の息子が声をかけてくれた。息子は恩師と業種は同じだが、プラント工場ではなく、建設現場の仕事をしていたので、本格的に息子に付いて仕事を覚える事になった。
勝也はこの仕事でやっていくと決め、必死で覚えた。休憩の時、昼ご飯の時、いつも息子と仕事の話ばかりして頭に叩き込んでいった。熱意が伝わったのか、認められたのか、いつの間にか現場を任されるようになっていた。
いつものように同級生の従業員の家に迎えに行くと、従業員が家に居なかった。それから一切連絡がつかなくなってしまった。数日後、やっと連絡がつくと、従業員は、辞めたいと言う。勝也は嫌々働いてもらっても良くないと思っていたので、引き留める事はしなかった。
きちんと働いた分の給料を渡し、直ぐにでも次の仕事を見つけるように言った。後に知人から話を聞いたのだが、反社会的な方面の人と付き合っていたようだ。勝也は後輩と二人になり寂しくなったが、こんなところで悩んでいる場合じゃないと思い、とにかく仕事に集中した。
ある日、中学の同級生であり、親友とも言える友達から連絡があり「オレの嫁の親戚の子を雇ってあげてほしい」と言う。勝也はとにかく一度会わせてくれと言い、喫茶店で顔合わせをした。少し軽い感じの若者だったが、真面目さが伝わったので直ぐに雇う事にした。勝也より3歳下の子で当時17歳。
この頃には次から次と現場を任されるようになっていたので、仕事も安定していた。
大きなスーパーの新築現場を任されていて、人手が足りなかった時には、若い子を見つけると仕事に来ないかと誘っていた。
健康ランドの大浴場で大学生の男の子と出会い、夏休み中だけでも良いからと無理を言い、バイトに来てもらったりもしていた。
忙しく人手が足りないので、中学校を卒業したばかりのヤンチャな15歳の子を雇った事もあったが、まだ遊びが勝っており、直ぐに仕事に来なくなる。