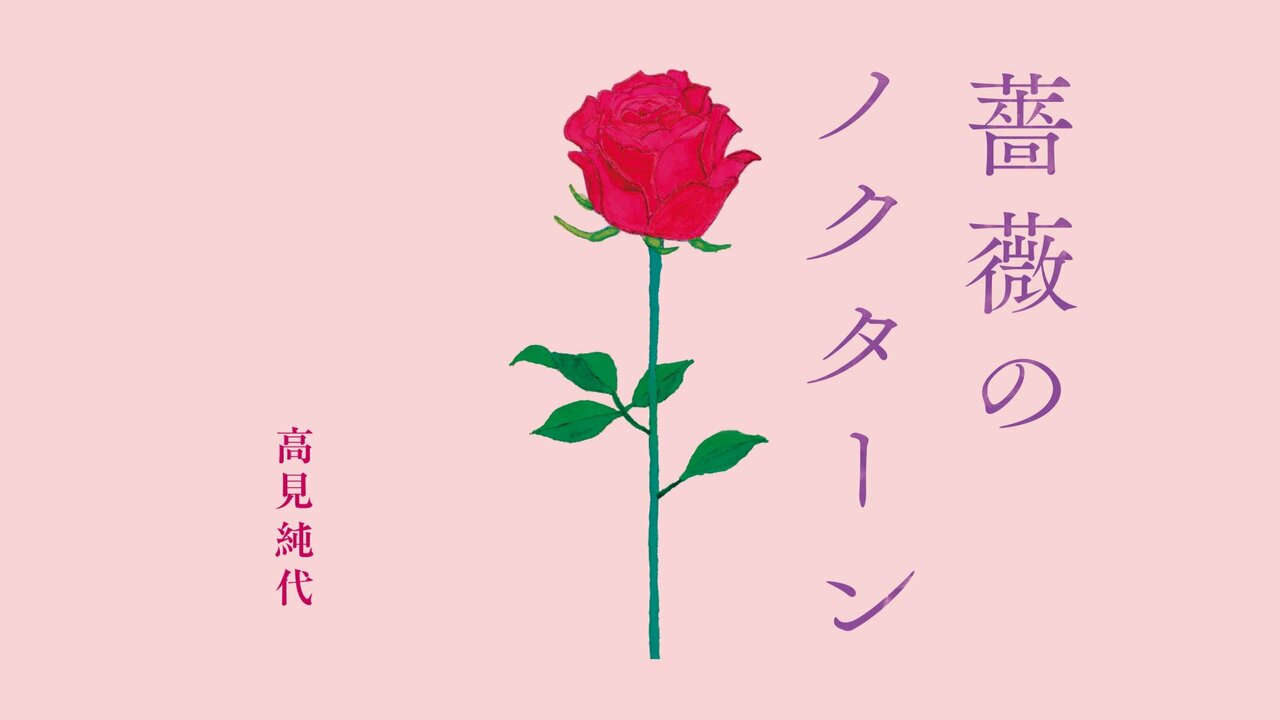一
「楯見さんは独身ですか?」
「澄世って呼んで下さっていいのよ」
「はい。で……澄世さんは独身ですか?」
「ええ」
「失礼だったらご免なさい。ずっと独身ですか?」
「ええ」
和彦は驚いた。何故だ? 高望みし過ぎたのだろうか?
歳だけはくって、実は男と付き合った事のない澄世は、相手がいぶかっているのを感じ、またか……と思った。いつもそうだった。
見合いでも、正直に男性と付き合った事はないと言うと、ある男に「君、それ売りなの?」と言われ酷く傷ついたのだった。以来、見合いをしなくなった。澄世は和彦の関心を他に移そうと思った。
「彼女、いらっしゃるんでしょ?」
「ええ」
「女性は花が好きだから、贈ってあげるといいわ。何がいいか困ったら、メールでも下さい。お花の事ならお役に立てると思うわ」
「いや、まだそんな付き合いじゃないので……」
今度は和彦が困惑した。こんなふうに、年上の綺麗な女性と食事をしていると知ったら、絵里は怒るかな?と不安になった。しかし、橋の上で出会ってから、さっきのピアノ演奏といい、謎の涙といい、和彦は澄世に何かしら惹かれている。
(まっいいか、絵里には黙っていよう)
二人は当たり障りのない話をして時を過ごした。時計が九時を指そうとした。
「今日は本当にありがとうございました」と、澄世がきりだした。
「こちらこそ、素晴らしい演奏をありがとう」
澄世がテーブルナンバーを取ろうとしたので、和彦はあわてて立ち上がった。
「僕が払います。その代わり、また会って下さい」
言ってから自分で驚いた。結局、涙のわけは聞けなかった。
四月二十九日(土)、ようやく澄世と和彦は再会した。和彦が仕事でベルギーへ出張していたのと、澄世が華道の関係で沖縄に行っていたせいで、お互い日程が合わず、この日になったのだ。