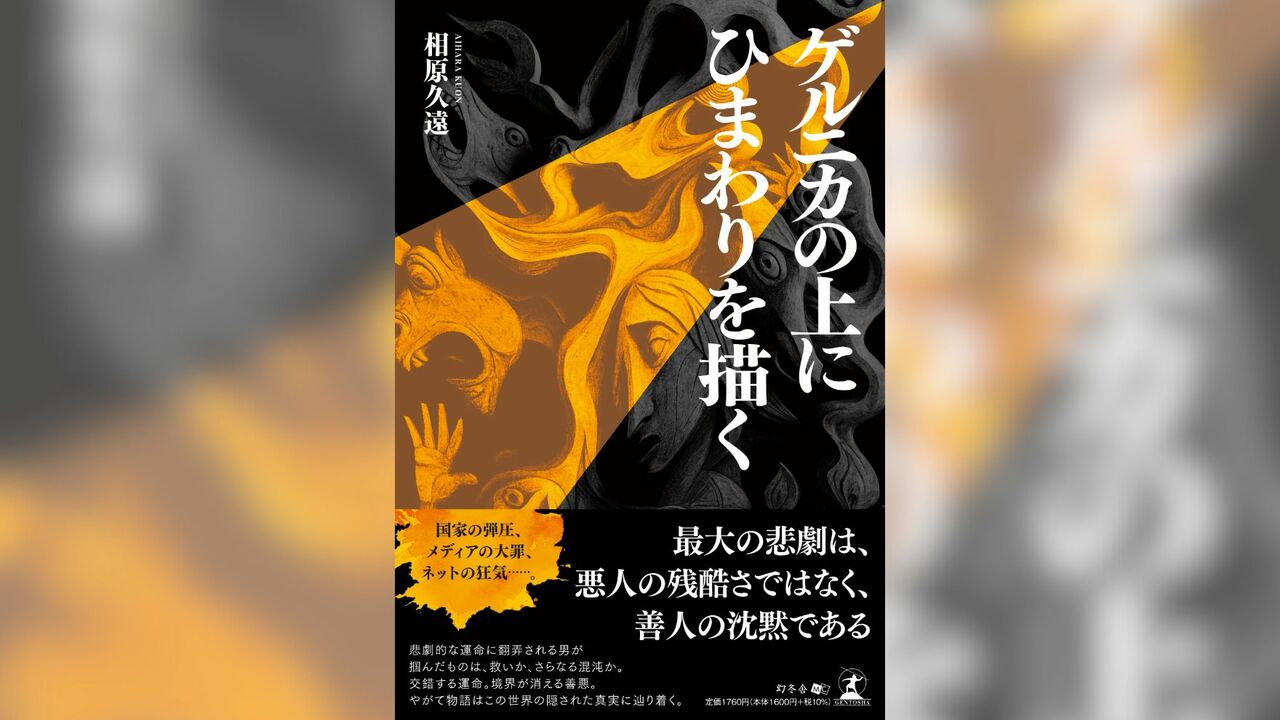神は死んだ。神は死んだままだ。
そして私たちがそれを殺した。私たちはあらゆる
殺人者の中の殺人者である私たち自身を
どうやって慰めたらよいだろう。
フリードリヒ・ニーチェ
プロローグ
大人になるにつれ、辞書をめくるのが怖くなった。言葉は万能ではなく、この世界には、辞書にある言葉では掬いきれないものが多過ぎることに気付いたからだ。
あの事件もその一つであった。長年、検事という職に従事してきたが、これほど異様な事件に出会ったことは今までなかった。事件が思わぬ形で解決に向かった時、あるプログラマーと小説家と画家が、事件の裏で動いていたことは、ほとんど語られていない。
国家が、全ての権力を振りかざし、歴史から葬り去ったはずの事件が、何の後ろ盾も、特別な力も持たない者達の手によって、白日の下に晒され、国家の中枢が崩壊してしまったこと。
私はあれからずっと、一つの問いに囚われている。彼らはなぜ、国家の圧政に怯まず、命をいとうことなく、この世の真理を追い求められたのか。
これまで、真理の追究のために死んでいった数々の歴史の犠牲者であり、同時に勇者でもある者達に想いを馳せる。ある種の真理の追究とは、いばらの道で、得てしてその人間の一生を狂わす。志や理想は、時にその所有者を容易く殺してしまう。
なぜ、そこまでして真理を追究しなければならないのか。多くの人がそうであるように、私もそれには答えられない。なぜなら、それは自分への問いでもあるからだ。
私は、検事として、国家権力の末端として、真理を揉み消した側の人間である。私の犯したルール違反は、真理を遠ざけ、間違いだらけの世界を近づけた。ヒトラーやスターリン、かつての権力者達と同じように。
私は、間違いを裁く検事でありながら、長らく、真理を追い求めることに息苦しさを感じていた。真理というものがこの世界を大して変えなかったこれまでの歴史にも。
世界を恨み続けてきた私は、彼らの真理が、なぜ世界を変えられたのかを知りたいと思った。そうして、彼らの足跡を辿るうちに、私の中にある仮説が浮かんだ。彼らの追い求めた真理とは、この世界の仕組みへの、弔いであったのではないかと。悲劇がありふれ、奇跡が起こらないこの味気ない世界への、彼らなりの抵抗なのだと。
私はこの仮説を、消えてしまった彼らの物語をここに書き記すことで証明したいと思う。どんな悲劇に見舞われた人間でも、どんな記憶を背負った人間でも、たった一つの人生を投げ出さないでいられる世の中を近づけるために。
これは、真理を追い求め、運命に抗い続けた彼らの闘いの記録である。