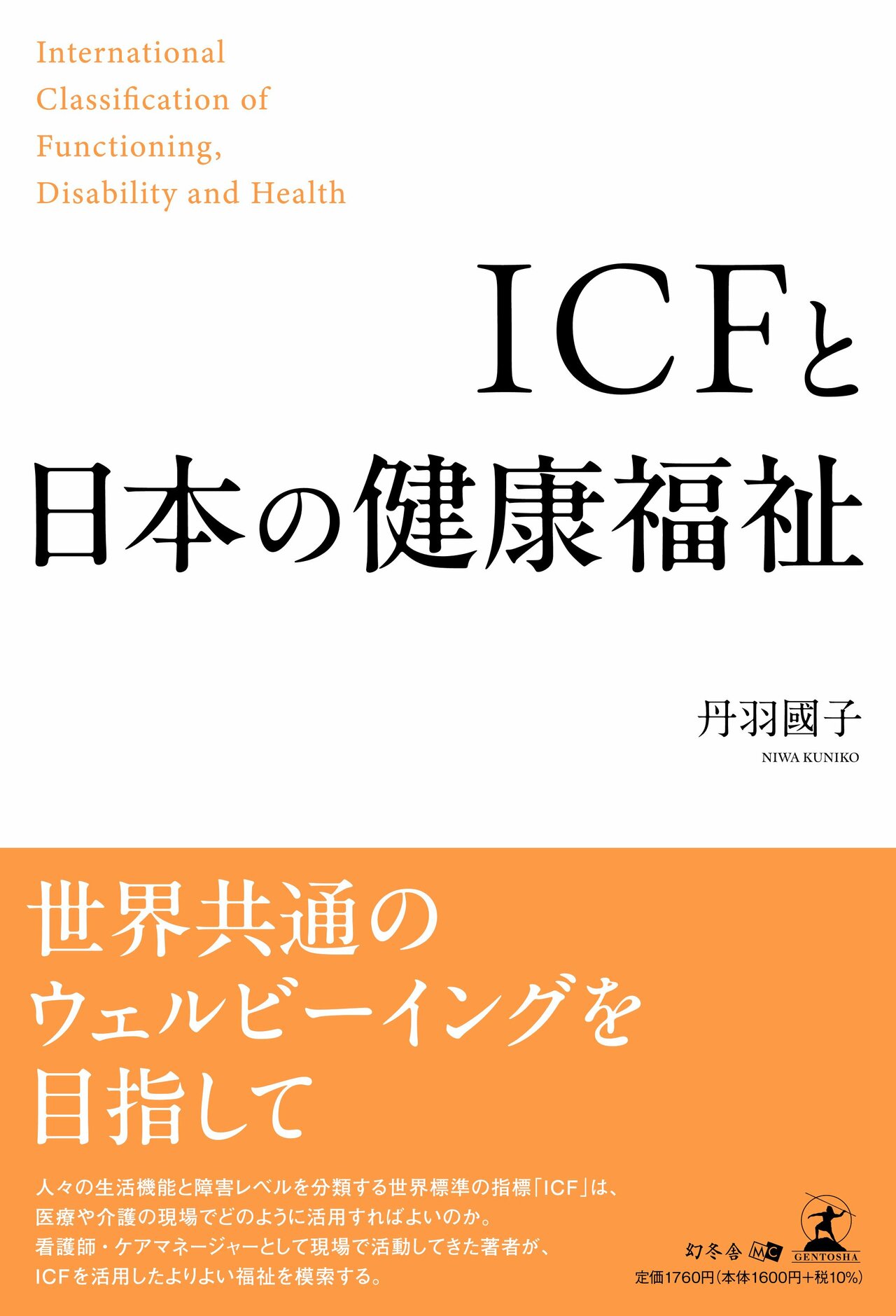幸い2001年、自然科学と社会科学の叡智を結集した世界共通用語として、ICFが WHO加盟国の満場一致で採択され、個人の自己評価とともに、健康福祉政策や教育・労働(雇用を含む)・家庭・地域・地球環境等の社会政策における個別的対人社会サービスの質の保障と評価ツールの実用が可能になりました。
そのため、「社会システムが整えば、障害に遭遇する機会は減少する」というICFの理念に基づいた複眼的視野を持って、一人ひとりの福祉の全体性を健康(= Health)の原点に立ち返って捉え直し、総合的な社会制度に再構築をすることが重要です。
さらに、21世紀に入り、一人ひとりの健康を科学的に研究する顕著な成果がつぎつぎに発表されました。
1.2009年にノーベル生理学・医学賞を受賞したエリザベス・ブラックバーン氏と、エリッサ・エペル氏は
「私たちの躰を創る一つ一つの細胞にある細胞核の遺伝情報を載せた染色体の両端にあるテロメアが長寿を伸ばす方法の鍵であり、テロメアが全身の健康状態を表す指標の一つとして注目され、どのように老いるかを左右するのは、細胞の健康状態なのだ」
と細胞レベルでの健康を気遣うことが健康寿命を伸ばす究極の方策と言っています。
2.同年、一般社団法人エジソン・アインシュタインスクール協会を設立した鈴木昭平氏と篠浦伸禎脳神経外科医は、子育ては「脳育て」であり、「現代日本の教育は、極端に左脳に偏った教育であり、多くの子どもは、本当の意味で、幸福感のある人間関係を周囲の友人と築けずにいます」と述べています。
3.2013 年に、東北大学大学院医学系研究科の大隅典子教授は研究室で、脳の機能と栄養をテーマに「母体から胎児、母乳から乳児と、脳の発育には重要な必須脂肪酸の摂取を与え続けること。出来れば母乳での授乳が大切」と発表しています。
この結果を医療現場の順天堂大学大学院医学研究科の清水俊明氏は「ここ数年、新たに ARA(=アラキドン酸)が脳の成長と発達に重要だとわかって来た。脳は1歳で大人の 70%、3歳で約90%できる。
小児科では胎児の時から生後3年ぐらいを ARA がとくに必要な時期とみている」そして「母乳から摂取することが理想」で「生後6カ月頃からは、離乳食に肉や卵や魚介類の摂取のバランスが大切」と言っています。(2013年3月7日産経新聞『企画特集』)
【イチオシ記事】「今日で最後にしましょ」不倫相手と別れた十か月後、二人目の子供が生まれた…。W不倫の夫婦の秘密にまみれた家族関係とは
【注目記事】流産を繰り返し、42歳、不妊治療の末ようやく授かった第二子。発達の異常はない。だが、直感で「この子は何か違う」と…