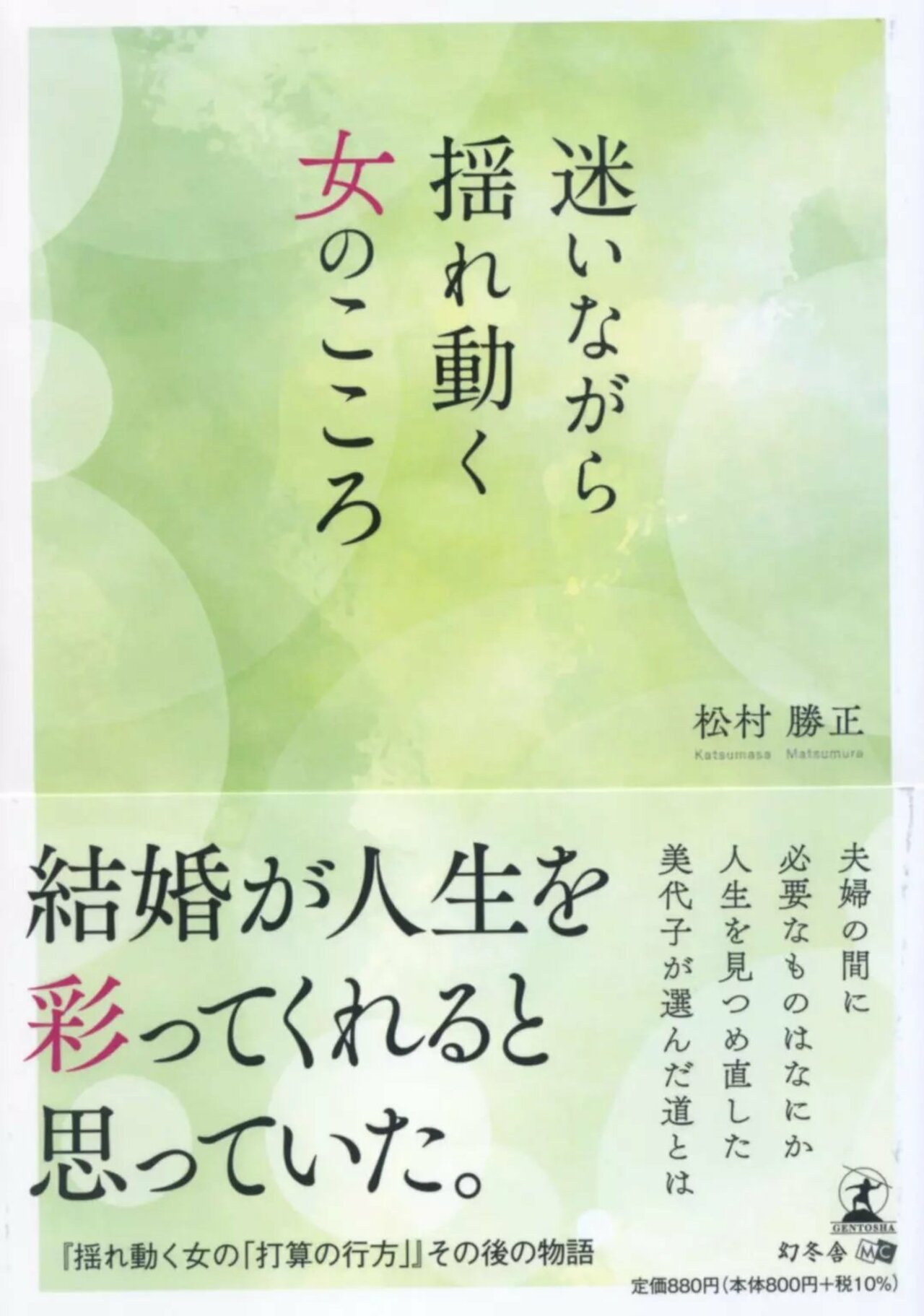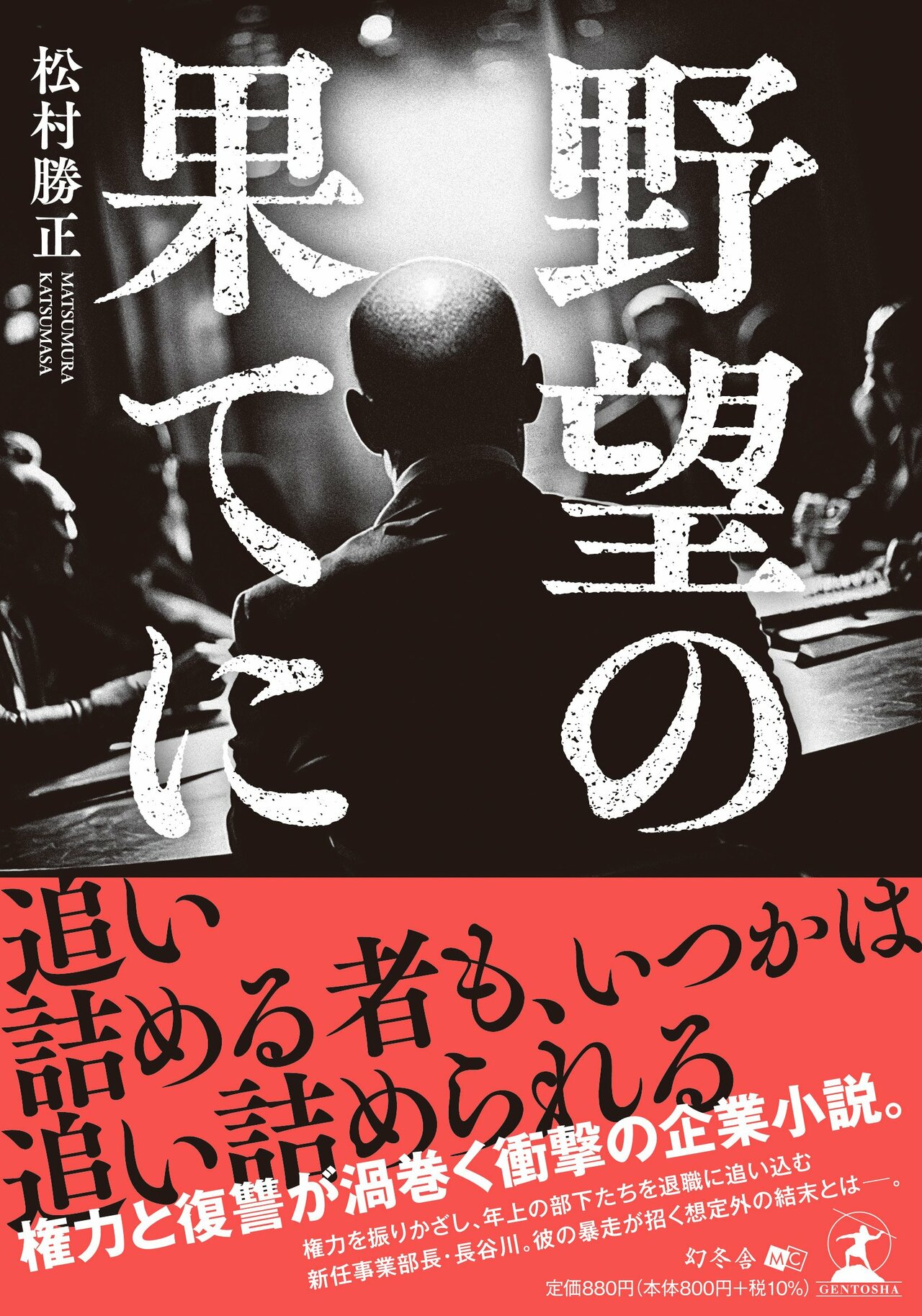「美月さん、今晩はびっくりするくらいの本場のパエリアを作りましょう。正直なところ私は結婚前もほとんど台所に立ったことが無かったの。でも、味覚には自信があります。会社勤務時代から友人と美味しい料理を食べ歩いていましたから。先日パソコンでパエリアのレシピを“本場のパエリア”で検索して、大事なポイントはメモに取りました」
話を聞いていた美月は「羨ましいですね。私なんか福島の片田舎だから、美味しい料理を食べ歩くことなんか夢のまた夢でした」と少し美代子の方を見て、すねた顔をして見せた。
「ごめんなさい。そんなつもりで言った訳じゃないんです」
「分かってますよ。でも東京での外資企業勤務に憧れますね」
美月は自分が高校生の時に両親が亡くなり、肩身の狭い生活を強いられたことなど、話すことが辛かったのでこれまで封印してきた。美代子とは生活環境も違いすぎるので、過去を思い出すことが自分を生んでくれて、一生懸命生きた両親に対して申し訳ない気持ちで一杯だった。
瞼を閉じて、何かを思い出すように、数秒間の沈黙を要した。小中学生の少女時代を過ごした福島の田舎の風景が、秒速で浮かんできた。一人っ子だったので両親は愛情たっぷりと接してくれて、いつも食事時には笑いが絶えない毎日だった。
美月はどうしてか子供の時を過ごした幸せの絶頂期しか思い浮かばない。両親が病弱だったので、高校三年生の時、相次いで亡くなったときは、あまりのショックで涙も出なかったことを覚えている。溺愛してくれた両親の死を受け入れることが出来ず、今日までことあるごとに両親と会話している自分がいて、寂しく思ったことはなかった。
「美月さん、始めましょうか」という美代子の声で現実の世界に引き戻された。
美月も我に返ったように、「どんどん指示を出してください」
「じゃあ、お願いしますね。先ず大きなフライパンがあるかしら? 出来たら底が平らなものがいいですね」
「普段は小さなフライパンしかここには置いてないから、納戸にしまっているかもしれません。見てきます」