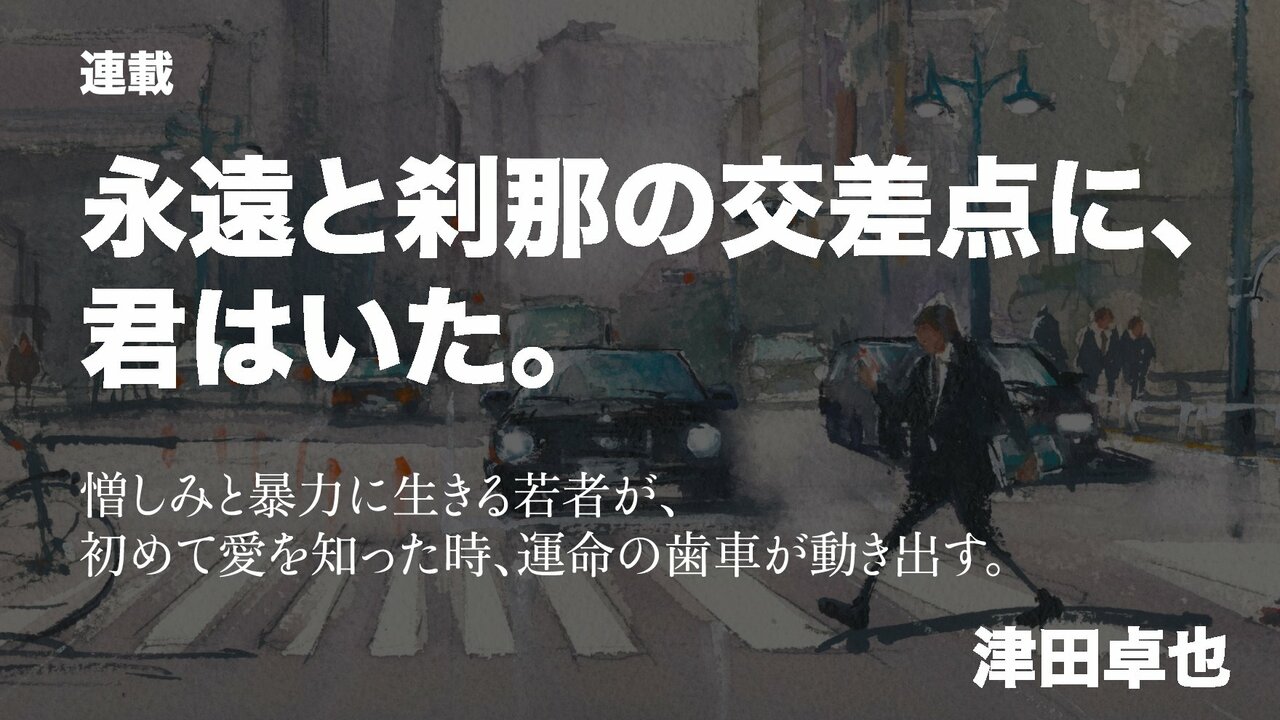第一章
6
夜更けにケータイが鳴った。画面に風間の名前が表示される。電話に出る。
「よお、工藤ちゃん。成人式おめでとう」
「なんだ?」
「きょうはちょっと謝らなあかんなあ。成人式やったのすっかり忘れてたわ。こんな日に仕事頼んですまんかった。ほんま、ごめんやで」
「くだらねえ」
「機嫌悪いなあ」
「用件は?」
「特にないけど、工藤ちゃん、あのなあー」
博昭は電話を切った。テレビをつけた。ニュースを観るためだった。
渋谷で事件が起こっているかもしれない。チームのメンバー数名から切迫したメールが届いていた。骸は浜田山愚連隊のメンバーだけでなく、友好チームや関係者まで無作為に襲撃を仕掛けていた。
あちらこちらから苦情の連絡が入っていた。ニュースは成人式での事件を流していた。酔ったヤンキー共が成人式の会場で暴れまわり、注意した中年のオヤジに暴行を働き重傷を負わせた。
弱い奴ほど弱い奴に手をかける。博昭は父の顔を思い出した。
コメンテーターたちが、物知り顔で暴行を働いたヤンキー共を非難している。
「ゲームの影響もあるでしょうね。リアルとバーチャルの区別もつかないんだ」
「スポーツとか武道とかを子供時代からやらしたほうがいい」
「いや、親の影響ですよ。親が友達みたいになっちゃった。世の中に怖い人がいなくなったんですねえ」
「食べ物の影響もありますよ。今の若者はセロトニンを分泌するような食べ物を摂取していませんから。ジャンクフードばっかり食べているからすぐキレたりするんです」
「この国には恥ずかしいという文化がなくなってしまったんだ。どうして学校は道徳とかをきちんと教えないのかねえ」
「学校や教師に威厳がなくなってしまった。モンスター・ペアレントへの恐怖もあるんでしょうけれどね」
コメンテーターの偉そうな顔を見ながら、博昭は不思議に思った。なぜこいつらはいつも何もかもわかったかのように言うんだろう?
恥ずかしいという文化をもっとも体現していないのはお前たちではないか。おまえたちがこのクソみたいな国を作ったのではないのか?
こんな奴らはどこにでもいる。ガキの頃からたくさん見てきた。養護施設の職員、学校の教師。言動と行動が一致しない大人たち。
奴らは必ずこう言った。おまえたちはまだ子供だから、子供のくせに、子供にはまだわからない。そのくせ子供は宝だとほざく。博昭は子供と言われるのが大嫌いだった。子供はひとりでは何もできないと言われることが何よりも頭にきた。
だから、何でもひとりでやった。ひとりでご飯を食べ、ひとりで学校に行き、ひとりで眠った。ひとりで歩き、ひとりで夜空を見上げ、ひとりで本を読み、ひとりで冒険をした。相手が何人だろうが、ひとりで喧嘩をした。