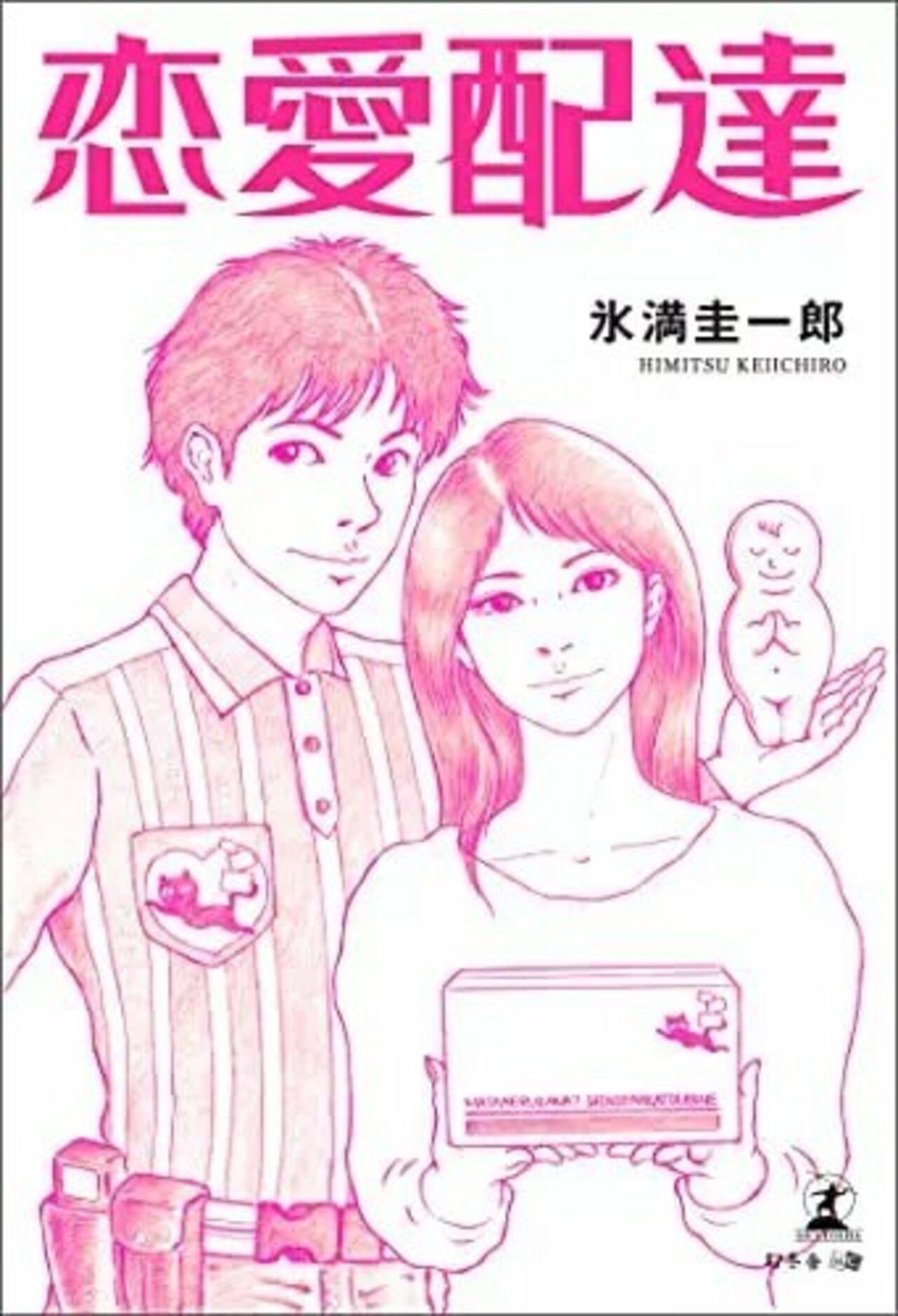「植物は無駄なことは一切していない。他の生き物の害になるものを排泄しない。光合成をして光で水を分解して酸素を作り二酸化炭素を還元して糖にしている。それに必要なのは太陽の光と水で、こんなにエコな生物は他にいないだろ」と父親に言われたので僕は頷いて返事した。
「それなら、植物はなんのために生きてると思う」と聞かれたので、他の生物のためなのと答えると、「それは自分たちが生きるためだ。決して他の生物のために生きてるんじゃない。でも自分のために生きることが結果……他の生き物のためになるんだ」と僕の頭を撫でてくれた。
「だからユウもお母さんと一緒に植物をよく観察して彼らから学ぶんだ。彼らを見習わないとダメだぞ。ユウは他の人が嫌がることをせず、嫌なことも言わず、自分のために生きていれば必ず……それがいずれは他の人のためになる」と哲学者みたいな話もしてくれた。
『大人になるための準備ノート』を閉じて外に出た優凪はカタバミの前に座ると母親に報告した学校での出来事を話し始めた。
彼の一日はカタバミに始まりカタバミで終わるのが常で、毎朝起きるとすぐ外に出て庭に育つカタバミに挨拶し彼らを観察した。学校から帰ると今日学校で経験したことを彼らに話した。
カタバミと生活を共にし、それが彼の生活サイクルを構成している。
まだ彼が幼かった頃、自宅の庭を手入れする母親の横で庭に育つ草花に触れていた時のこと。
そこで誰かに話しかけられたような気がしたので、その声のする方を向くとそこにはたくさんのカタバミの姿があり彼らは自分を見ていた。彼らは声を合わせて何かを訴えているようだったが、まだ言葉を話せない自分には何を言っているのか理解できなかった。彼らはしきりに自分に何かを頼んでいるように思えた。それはカタバミが自分たちの運命を優凪に託した日となった。
それから同じ事が何日も何度も続いたが、残念ながら彼はまだそれを理解できる年齢にはなっていなかった。そのたびに彼はカタバミに返事をすることができず撫でるしかなかった。
そして時の移ろいと共に彼らの声はだんだん聞こえなくなってしまった。
だがカタバミに話しかけられ何かを頼まれたことは記憶にしっかり刻まれていた。
それが何かを知りたくて彼はカタバミと会話を始めた。