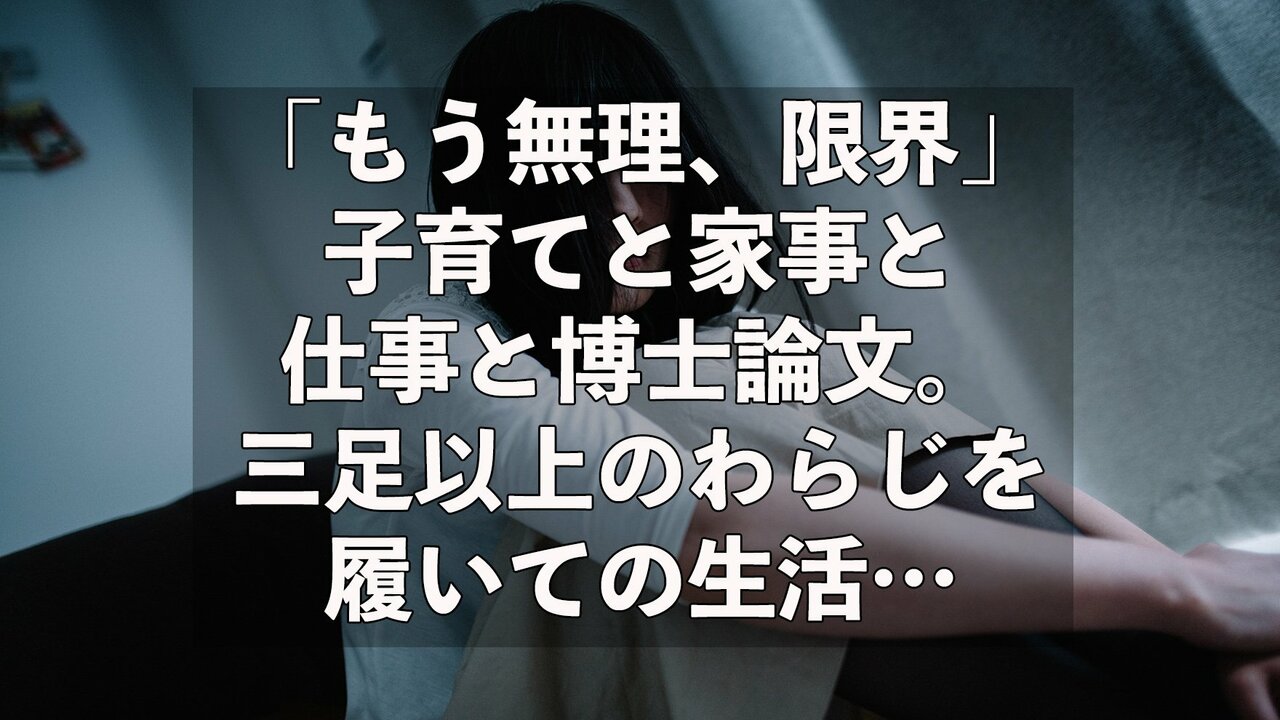【前回の記事を読む】「仕事を辞めてほしい」共働きで経済的不自由もない、幸せな家族だったはずが…
第三章 ぽんこつ放浪記
5.人生の転機
転職劇の始まり
大学という職場は、実際には権力争いが絶えない。
特に、短大の大学化が急がれるギスギスした雰囲気の中、教育の質や教師の人間性よりも業績や権力者とのつながりが優先されていった。
その中で、私も、新しくやってきた教授に、これでもかというほどのパワハラを受けた。
子どもを保育園に迎えに行く直前に五分おきに内線電話をかけてくる。教授会では私の悪口、謎のファックスにあることないこと書かれて送られる等。へとへとになって家に帰ってくる私に夫がそういうのも無理のないことだった。喘息も発症。
幸い、他の大学から「うちに来ない?」とお誘いが来た。夫の稼ぎだけでは経済的に厳しかったし、転んで幸いとばかりに即決、大学を移った。が、うまい話には訳あり、仕事ずくめ。やはり子育てには非常に厳しい職場環境だった。
私は分娩教育担当だったので、学生の分娩介助のたびに分娩室に呼び出され、お正月休みもなかった。
お正月、温泉宿から分娩室とやりとりをしていた時、夫が「正月まで仕事か!」と怒った怖い顔が忘れられない。
子どものいない同僚教員には理解されず、仕事を代わってもらうことなどできなかった。子どもが熱を出して遅刻した時には呆れられた。かなり辛辣な言葉も浴びた。それでも仕事に穴はあけることなく必死にやってきたのだけれど。
こんな特殊な職場で子育てを続けるのは無理、しかも大学からは教員として残るために博士号も取得しろと言われ、大学院博士課程で学ぶ身だった。
仕事と博士論文と子育てと家事、三足以上のわらじを履いての生活だった。やりすぎ、欲張りすぎと思われるかもしれないが、看護職を続けながら子育てする友人は皆同じ状況だった。
でも、「もう無理、限界」心底、そう思った。夫は育児に協力的とは決して言えなかった。しかし、その頃、ようやく夫の会社経営も軌道に乗り始めた。月五万円しか生活費を入れられなかった夫だったが、私が辞めても生活できそうな経営状態になった。
私は助産師教育のキャリアを捨て、子育てに専念することにした。そして再起を目指して博士論文を書いた。子どもが保育園を卒園したことも契機だった。それでも妊産婦と赤ちゃんに関わることを諦められなかった私は、市の委託母子保健訪問指導員を二年勤めた。たくさんのママと赤ちゃんとの出会いがあった。この二年は、不思議なほど幸せな時間だった。