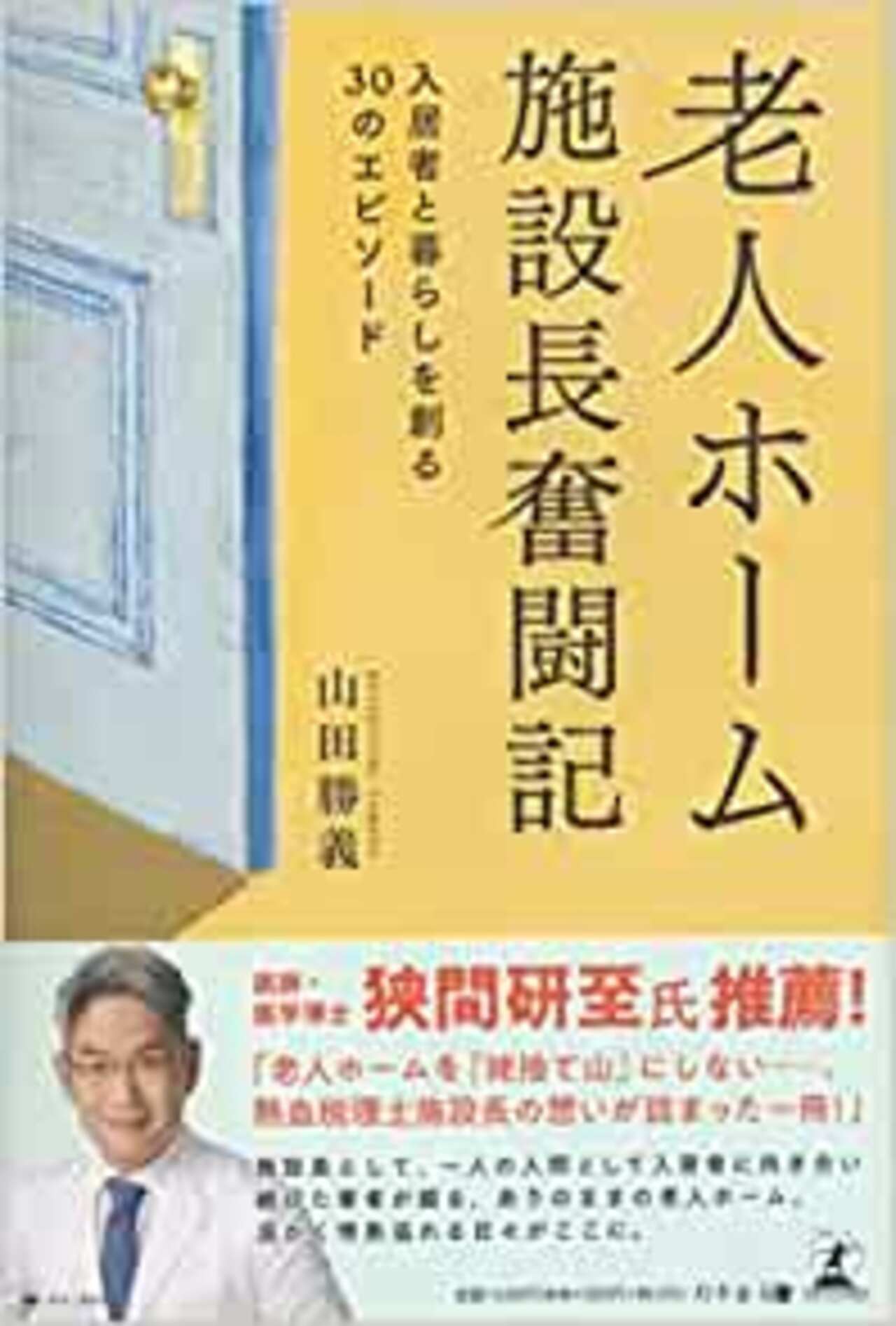老人ホームの職員も、このような状況の中で必死です。自分の家族のことも心配でしょう。しかし、このような非常災害時であっても職員が悲壮感を持って対応していると、入居者の皆さんの不安感は、より高まってしまいます。しかし施設の職員は、非常に献身的に、かつ笑顔で、それぞれの役割をしっかりと果たしてくれたのです。
こうして地震の当日、老人ホームの施設運営において、入居者の命を守り、事業継続性において、できる限りのことを手当することができました。
しかし、私は非常災害時で「何とかしなければ」という焦りと共に、心の中には言い知れぬ不安感に苛まれていたのです。
「この状況、いつまで頑張れば良いのか」
テレビ報道から、刻々と入る未曽有の災害状況に圧倒されながらインフラが寸断された大規模老人ホームの責任を背負う自分は、「どのくらい、どのように持ちこたえれば良いのか」という思いでいっぱいでした。事実、老人ホームの周辺でも液状化現象が発生し、テレビでは津波が来襲する恐れがあるという情報が出ていたので、この施設は海沿いにあったため、暗くなってから土嚢積みも行いました。
とにかく、当時の私の記憶の糸をたどると、「その日一日、一日を」と心に決めており、他の地域からの救援援助物資が届き始めたのは、震災発生日の3日後くらいからだったと記憶しています。
10日目 手を握り心が通じ合う
大震災当日から、ひとりの入居者の方のお話を取り上げたいと思います。
当時、私の老人ホームでは、高橋さん(仮名)という上品な女性の方が入居されていました。この高橋さんは、東京の青山育ちの生粋のお嬢様。
高橋さんは、自宅で転倒された際に大腿骨を骨折、病院で手術したばかりでした。当時、高橋さんは、仕事をされている娘さんと二人暮らしでした。手術後、退院してすぐにご自宅での生活は難しいとのことから、私が施設長を担う老人ホームに入居いただきました。それは東日本大震災が起こる2カ月前のことでした。