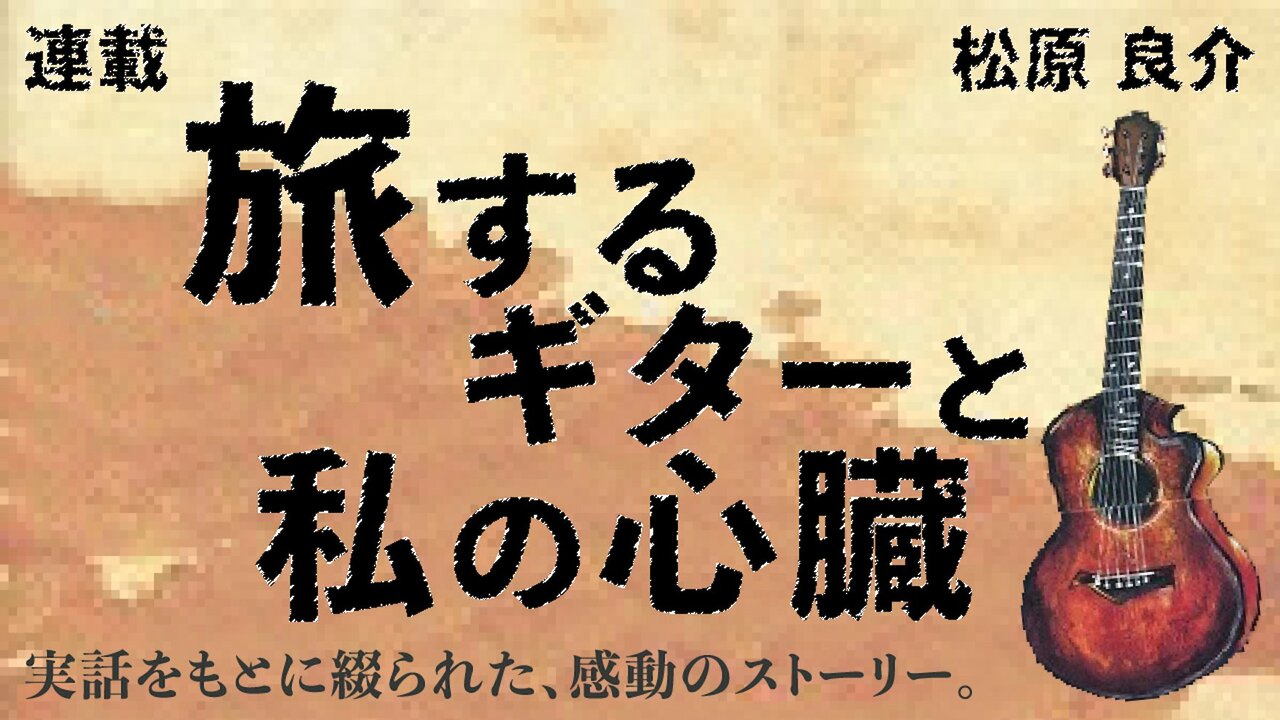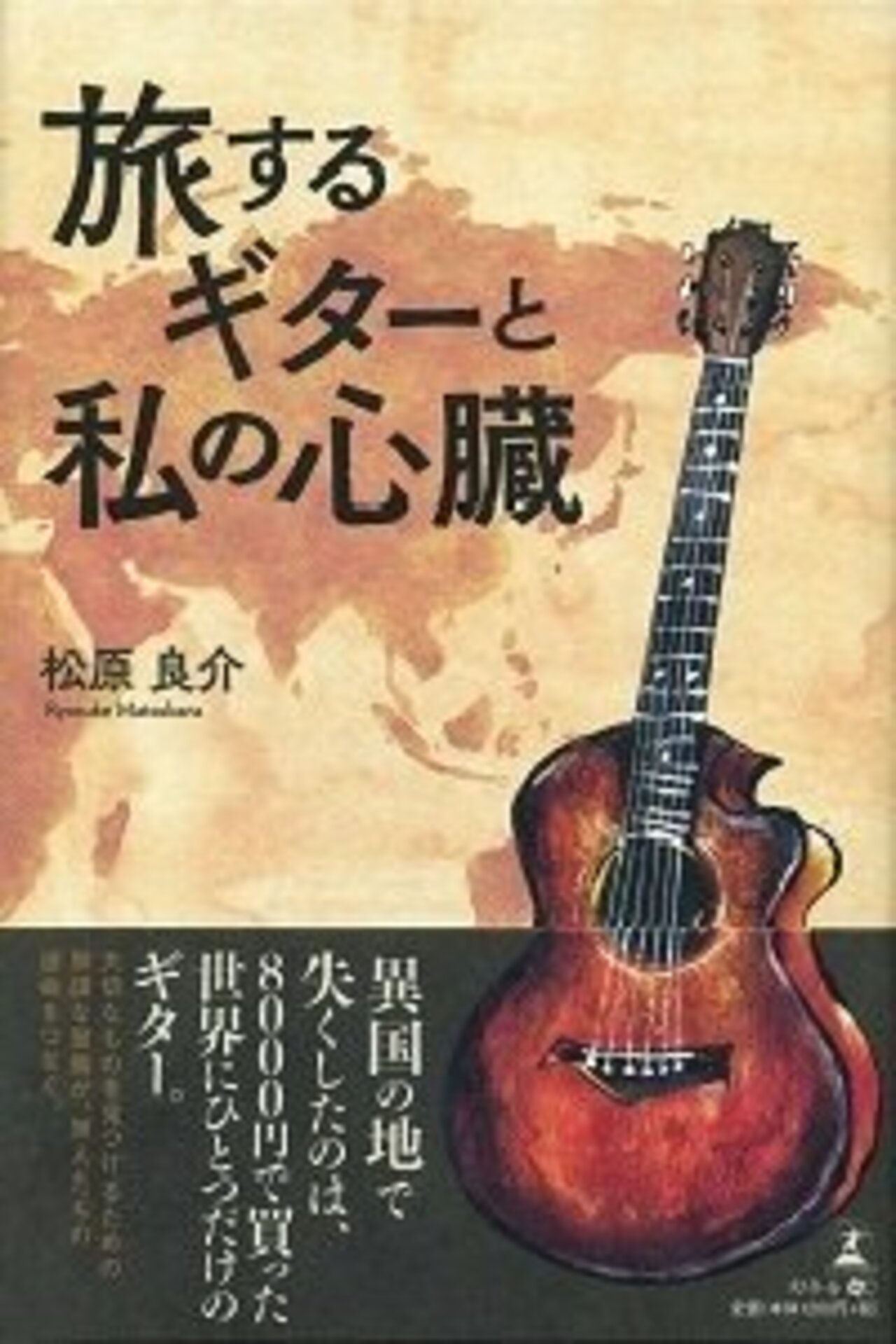片言のハングル(デイジー)
チェンマイの市場で買い物をしてから、デイジーはいつものように〝彼〟の姿を探した。腕にぶらさげた袋からは、さっき買ったセロリがひょっこり顔を出している。やがて市場の先から彼の歌声が聞こえてくると、デイジーは耳を澄ませながらその方向に向かった。
1ヵ月前、初めて彼の姿を見たのは市場の近くにある公園だった。
黒髪で同じアジア人の彼は、デイジーの行動範囲によく出没した。あるときは近所の公園であったり、人通りの多い路上であったり、この市場であったりと、彼は転々としながら、ギターを弾く場所を変えていた。
はじめはお互い目を合わせてニコリと笑顔を作る程度だったが、やがて挨拶を交わすようになると、デイジーは彼と話すようになった。
彼の名前は「テツヤ」。日本人だった。
テツヤはギターを弾きながら世界を周っていて、最近この街にやってきたのだと話した。
旅の話に興味を持ったデイジーは、その日以来、彼の隣に座って話し込むようになり、いつしかそれが日課になった。
ナツミとの出会いで日本に興味を持ち始めていたデイジーは、テツヤと話すうちに日本に訪れたいと強く思うようになっていた。
「デイジーは日本に来たらどこに行ってみたい?」
それほど日本の地理や知識を持っていなかったデイジーは思い付きで「渋谷」と答えた。
以前観た日本の映画で、思いを寄せ合う若い男女が数年後、渋谷のスクランブル交差点で再会するシーンがあったのを思い出したのだ。デイジーはそのシーンが印象的でよく覚えていた。
「じゃあ、デイジーが日本に来たら案内するよ」
そうしてデイジーはテツヤとフェイスブックを交換した。
テツヤは英語を話すのがうまいわけではなく、それを少し気にしていたが、デイジーからしてみれば、テツヤの卓越したギターテクニックとその歌声が立派なコミュニケーションツールになっており、言語の壁をカバーしていると感じていた。
「テツヤはなぜ旅をしているの?」
デイジーがそう尋ねると、テツヤは難しそうな顔をして昔の話を始めた。
彼は何やら病院の話をしていたようだが、はっきりとはわからなかった。やがて言葉に詰まると、両手を広げてあきらめるようなしぐさをして見せた。
デイジーはテツヤに英語を教えるようになり、その代わりに彼はデイジーにギターを教えるようになった。決して流暢に話せるわけではなかったが、いつか家族でアメリカに移住するときのためにと覚えた英語が、こんな形で役に立ったことをデイジーは嬉しく思った。
はじめは週末だけデイジーの知り合いが経営しているゲストハウスに集まって英語を教えていたが、気がつけば毎日顔を合わせるようになっていた。テツヤはいつもノートを持ち歩いていて、そこに覚えた単語や文章を作って書き込んでいた。彼が熱心に書く文字は繊細で美しかった。
頭の良い彼は語学の吸収が早く、英語だけでなく、少し教えただけの韓国語も器用に使って見せた。時折、自分で調べた韓国語を披露してデイジーを驚かせることもあった。
“デイジーまたね。君に逢いたいよ、明日も、その明日も”
あるときテツヤが別れ際に韓国語でそう言ってくれたこともあった。彼の照れくさそうな顔が頭に残って、その日デイジーはなかなか寝付けなかった。
テツヤのギターを押さえる細くてきれいな指も、歌声も、覚えたばかりの片言のハングルも、そのすべてがデイジーの宝物だった。