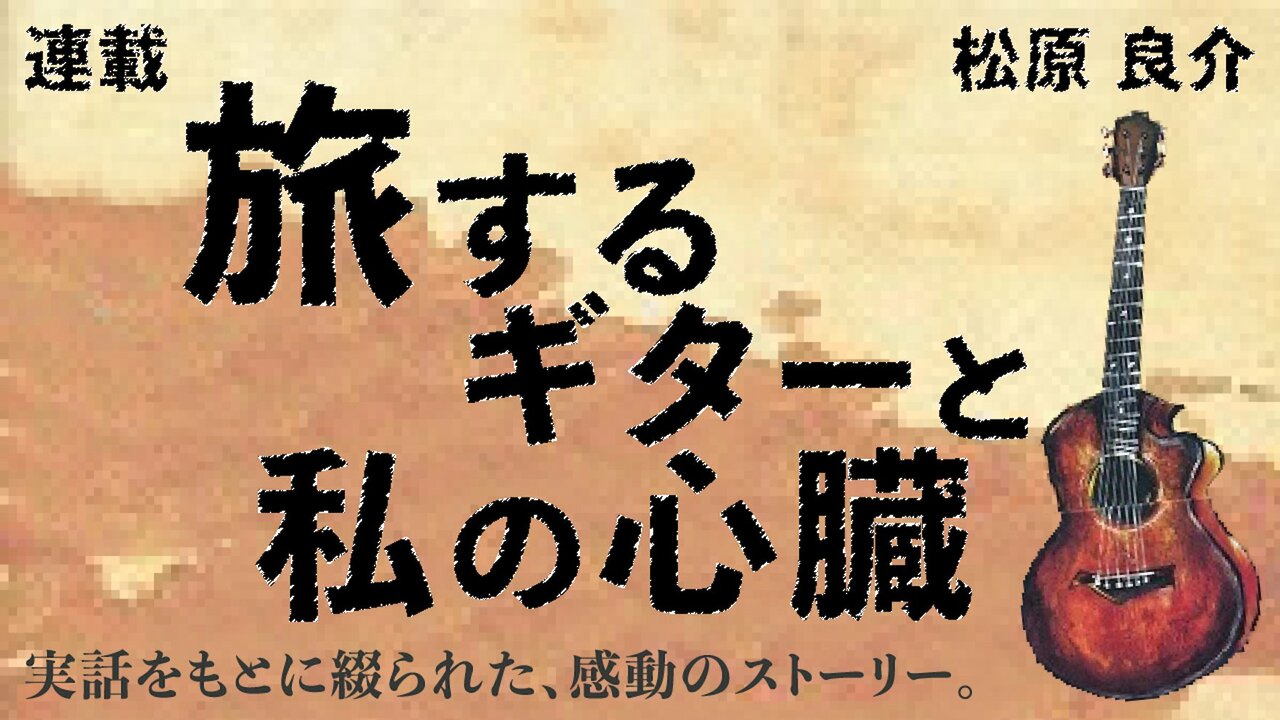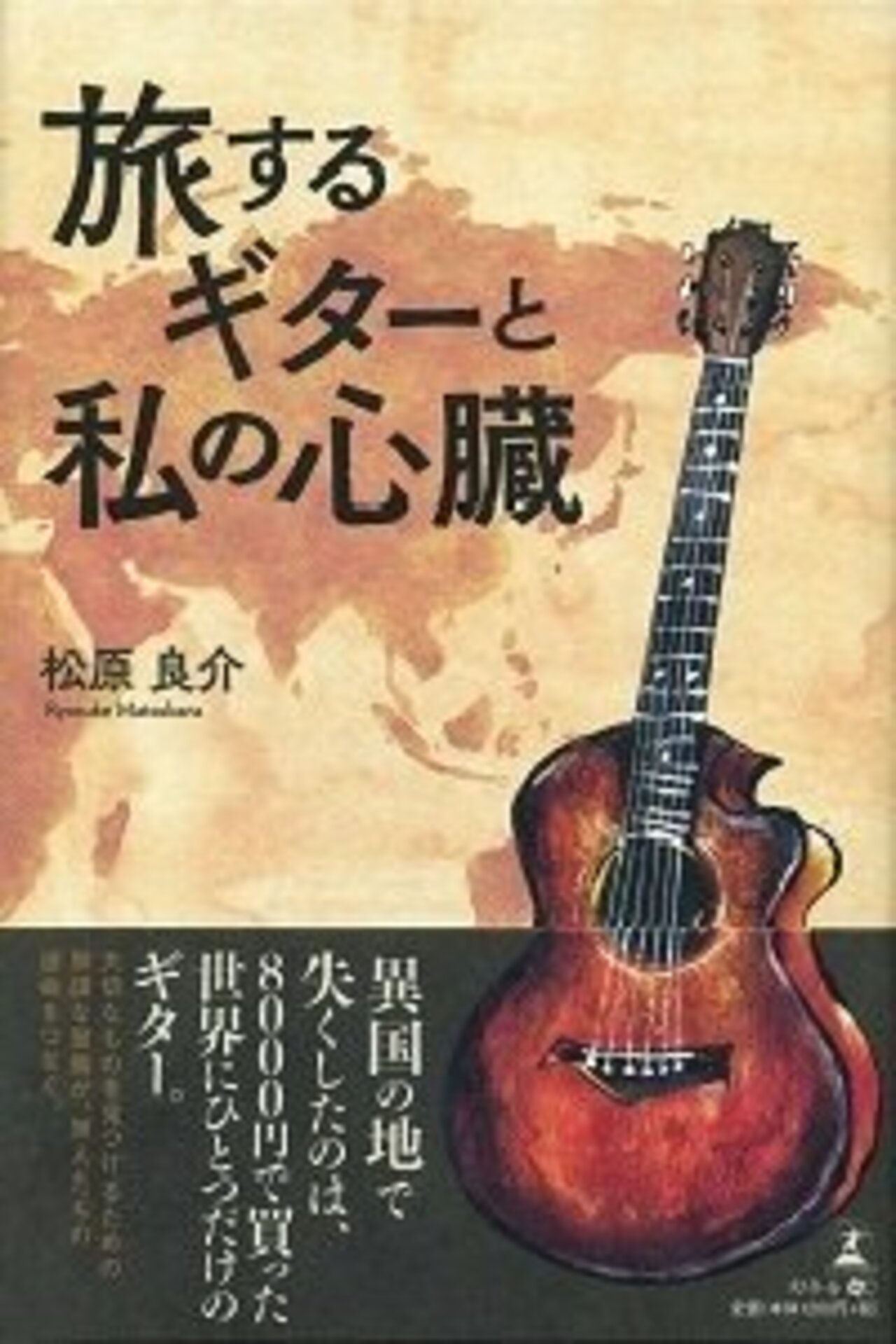メコンナイト(デイヴィット)
2009年5月。
デイヴィットは、兵役を終えると幼馴染のジェイクに誘われるまま、東南アジアを周る旅に出発した。誘ってくれたジェイクもまた、兵役を終えたばかりだった。イスラエルで生まれ育ったデイヴィットは国外に旅行に出るのはこれが初めてだった。
イスラエルに住むユダヤ人と一部の宗派の国民は、18歳になると男性は3年、女性は2年、国防軍に徴兵される。そのためイスラエルでは、兵役を終えた後に大学に進学するのが一般的であり、兵役を終えた若者たちが進学や就職を前に長期の海外旅行に繰り出すのも通例となっていた。
旅先でデイヴィットとジェイクは、今までのうっ憤を晴らすかのようにはじけた。
タイの離島では毎晩のように道行く女性に声をかけた。朝から酒を飲み、夜になるとパーティに入り浸った。デイヴィットはそれまで旅にあまり興味はなかったが、今となっては熱心にこの旅行に誘ってくれたジェイクに感謝していた。
シーパンドンと呼ばれるラオスの中州に位置する小島は、デイヴィットにとって楽園のような場所だった。“4000の島”を意味するシーパンドンは、カンボジアとの国境に近く、ナカサンボート乗り場からボートで20分ほどメコン川を渡ったところにある旅人の隠れ家的な島だった。メコン川に沿って100メートルほどのびるメインストリートには、カフェやバー、ゲストハウスなどが立ち並び、ヒッピーたちで溢れていた。
この島では時空が歪んだような、ゆったりとした時間が流れている。
ビールを片手にハンモックで揺られながら、メコン川に沈む夕日を眺め、夜になるとマリファナを吸ってバカ騒ぎをした。開けっ放しの窓から差し込む朝日と鳥の囀りで目を覚まし、また同じことを繰り返す。二人は流されるまま若さに身をゆだねた。
シーパンドンに着いてから6日目のこと。
その夜も二人は宿に隣接するバーで酒を飲んでいた。やがて遊び疲れたデイヴィットは、ジェイクに宿に先に帰ることを告げて部屋に戻った。
宿の部屋は値段の割に広々としたツインルームだ。デイヴィットは床に散乱した空のビール瓶を避けて歩きながらベッドに向かった。崩れ落ちるようにベッドに横たわると、身体がゆっくりと液体化して溶け込んでいくような気がした。メコン川の波音が心地良く、デイヴィットはそのまま深い眠りについた。
「デイヴィット、おい、デイヴィット」
自分の名前をささやく声でデイヴィットは目覚めた。どれくらい眠ったのだろうか。寝ぼけながら声のするほうに目をやると、窓から差し込む月明かりがベッドの横に立つジェイクの姿をぼんやり照らしていた。
「ジェイク? ジェイクか? どうしたんだ?」
デイヴィットは目を細めながら、酒で焼けた声を絞り出して言った。さほど広くない室内にはマリファナの匂いが充満していた。
「なぁ、デイヴィット、一緒にメコン川で泳がないか?」
「おいおい、今何時だと思ってんだ、勘弁してくれよ」
「スリルがあって目が覚めるぜ、なぁ、泳ごうぜ」
ジェイクの顔は暗くてよく見えなかったが、話す感じからマリファナで気分が高揚していることはわかった。
「ああ、ジェイク誘ってくれて嬉しいけど、明日にするよ、おやすみ」
デイヴィットは目をこすりながらジェイクに背を向けた。ジェイクはそのあとも、ベッドに腰かけてデイヴィットに話しかけ続けたが、やがてあきらめて静かになった。きしむ床の音でジェイクが部屋から去っていくのがわかった。
ジェイクの遺体がメコン川で発見されたのは翌朝のことだった。
もともと競泳の選手を目指していたジェイクは、軍に入隊してからもその技術に磨きをかけ、潜水に関していえばトップクラスだった。そんな男があっさりと溺死してしまったのである。昨日まで元気な姿を見ていたデイヴィットは、現実を受け止めることができなかった。
ジェイクの葬儀は自国で行われた。
遺体を搬送するのにかかった費用などは、すべてジェイクの旅行保険で賄われた。いつもなら保険に加入することなどしないジェイクだったが、まるでこうなることを予測していたように手が打たれていた。
あれだけ馬鹿騒ぎをしていた後だったので、いつか起き上がってきて自分を驚かせようとしているのではないかと思うほどだった。家族は皆打ちひしがれていたが、現実離れした世界での友の死に、デイヴィットは実感がわかず、特別な感情を持てなかった。
デイヴィットは兵役を終えたときにジェイクと交換したドッグタグを眺めながら、涙を流せないでいる自分が理解できずにいた。